紀尾井町の占い師 (後編)
神田伊織の「二ツ目こなたかなた」 第2回
- 講談

神田 伊織
2025/05/27

江藤新平(国立国会図書館蔵『近代日本人の肖像』より)
鎮魂と救い
果たして大正十五年十二月の『週刊朝日』に、「江藤新平の首」という大島伯鶴の講談が載っていた。
芸者の名前が「小友」で江藤新平との面識はなく、宴会で訴えを聞いた大久保が反省をして写真の販売を禁止するという点や、暗殺とのつながりはないところが大きく異なるが、大筋は同じ展開だ。
この講談を踏まえてだろう。政治講談の巨人・伊藤痴遊は『痴遊雑誌』に江藤の首写真を掲載した際、「巷間、伝ふる所の芸妓小友云々の物語は、全然、跡形もなき事にして、見て来たやうな、嘘を吐く、講釈師の出鱈目である」と断じている。江藤と芸者と大久保暗殺にまつわる物語は、講談師の創作をきっかけに広まったのか、元々こうした噂があって講談になったのか、そこは定かではない。
講談では忘れられてしまったこの物語は、実は浪曲で今も伝わっている。演題を『江藤新平と芸妓お鯉』という。
芸者の名前は「小禄」でも「小友」でもなく「お鯉」であり、彼女は江藤新平からただ恩を受けたという設定になっている。世話になった江藤のむごたらしい写真を見て気の毒に思い、意地になって写真を買い集める。やがて政府高官の新年会に乗り込んで、思いのたけを訴える。
お鯉さんのこの演説、クドキが、浪曲の終盤で長い節となって展開される。切々たる心情がバラシの迫力と合致して、聴く者の心を強く打つ。
浪曲では大島伯鶴の講談と同じく、熱弁が実を結んで訴えが通じる。大久保が反省し、お鯉さんの無念、江藤新平の無念が報われる展開にほっとする。心のもやが払われるような気がする。もっとも、そのあとに島田一郎と大久保暗殺への唐突な言及があるので、安心は揺るがされ、奇妙な違和感が残るのだが。
江藤新平は実に不憫な最期を遂げた。捕縛後に急速に行われた裁判では弁明さえ許されず、かつての同僚たちによって惨刑に処された。それが可哀想だから、そんなことがまかり通る世の中であって欲しくないから、物語の中のお鯉さんは世間から奇異の目で見られてもひとり写真を買いあさり続ける。気の毒な死者のために熱情を注ぐ。
日本の古い芸能には鎮魂の役割がある。もしこれが中世の能ならば、江藤新平は亡霊として現れて無念を口にするだろう。文明開化の時代のこの話では、生きたお鯉さんが江藤の思いを代弁する。その意味でお鯉さんは巫女であり、依り代である。
何かに取りつかれたように写真を買い集め、時の最高権力者を前に熱弁をふるうことで、何も言えずに死んでいった敗者の魂を鎮める。一見モダンなこの演目には、そういう古風な構造がある。
現実の江藤新平は無残に死んだ。語りたいことを語れずに死んだ。歴史上の無数の弱者、敗者たちと同様に。虚構を通じてその無念をお鯉さんが晴らしてくれるから、生きている我々は束の間の救いを感じることができる。
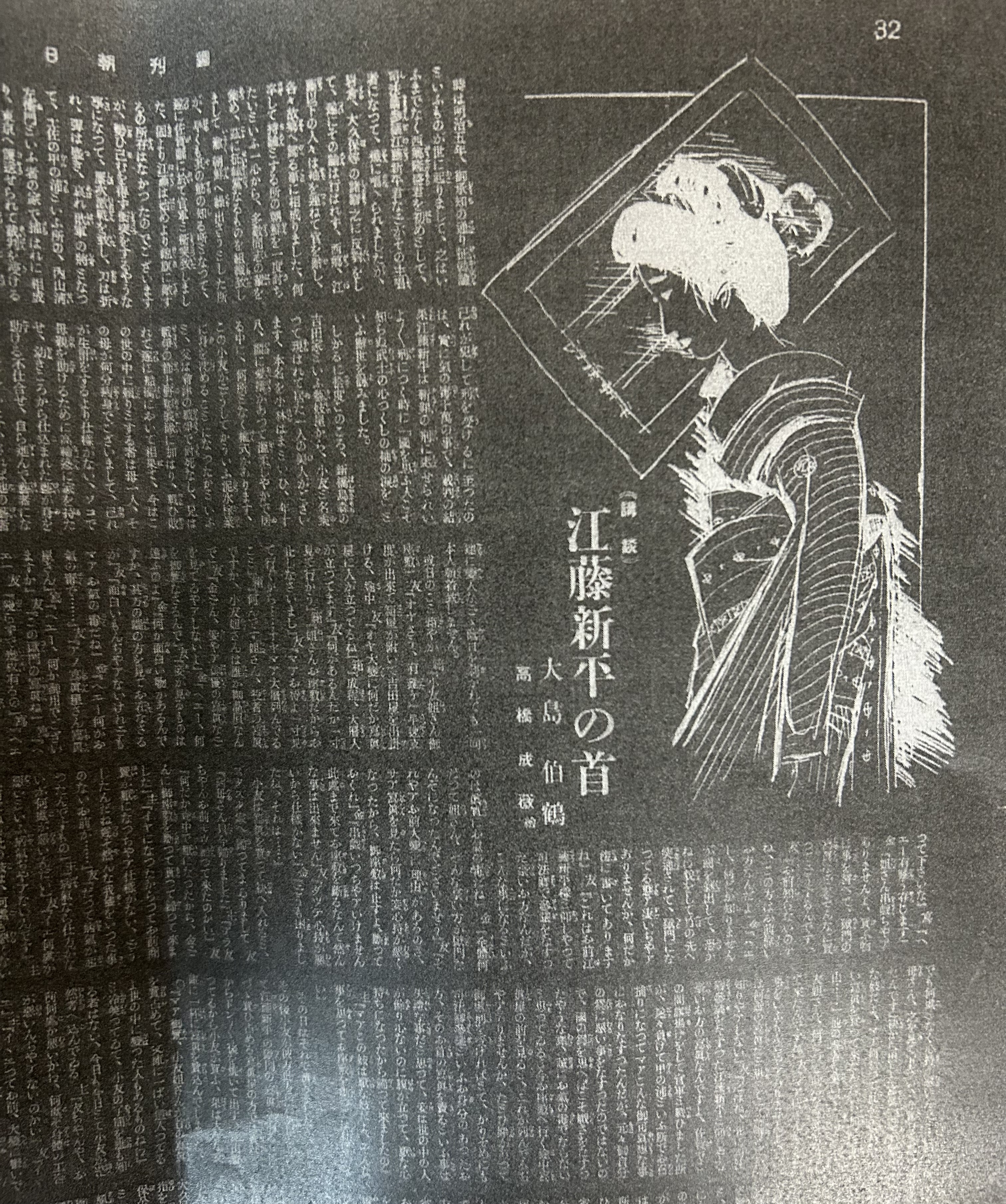
いま読まれています!

「講談最前線」 第14回
2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2026/01/15

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「噺家渡世の余生な噺」 第9回
今年も、自分を悟る一年に
~噺家として育てられてきた時間のありがたさ

柳家 小志ん
2026/01/14

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回
昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!
~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭
2026/01/10

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

シリーズ「思い出の味」 第11回
食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶
~焼肉は落語

桂 笑金
2025/08/17

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第20回
優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(後編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/11/30

「座布団の片隅から」 第9回
大河
~『べらぼう』が残していった、噺家への置き土産

三遊亭 好二郎
2026/01/07

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回
落語家の夢
~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎
2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回
昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!
~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭
2026/01/10

「お恐れながら申し上げます」 第5回
新年のご挨拶
~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太
2026/01/11

月刊「浪曲つれづれ」 第9回
2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)
~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋
2026/01/09

「講談最前線」 第14回
2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2026/01/15

「噺家渡世の余生な噺」 第9回
今年も、自分を悟る一年に
~噺家として育てられてきた時間のありがたさ

柳家 小志ん
2026/01/14

「二藍の文箱」 第8回
麹町の雑煮、目白のおせち
~噺家の正月風景

三遊亭 司
2026/01/02

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回
〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)
~「見えない序列」の正体

杉江 松恋
2025/12/24

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/29

「二藍の文箱」 第8回
麹町の雑煮、目白のおせち
~噺家の正月風景

三遊亭 司
2026/01/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回
昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!
~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭
2026/01/10

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第22回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(中編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第23回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(後編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/31

「講談最前線」 第13回
2025年12月の最前線【後編】 (2025年の講談界ニュース)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2025/12/17

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回
〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)
~「見えない序列」の正体

杉江 松恋
2025/12/24

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回
落語家の夢
~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎
2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第15回
水茄子とジンジャーエール
~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三
2025/11/25

「令和らくご改造計画」
第四話 「初心者よ永遠なれ」
~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/11/12

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回
上方落語大会議「なんぼでなんぼ」
~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎
2025/10/24

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回
シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト
~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭
2025/11/13

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回
ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋
~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春
2025/11/03
編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回
浪曲ほど素敵な商売はない
~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎
2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回
弥勒菩薩(半跏思惟像)
~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿
2025/12/16

「講談最前線」 第12回
2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2025/12/15

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回
にらみ返し、大工調べ、短命
~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平
2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回
今日は宇宙一の美が誕生した日
~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春
2025/12/03


