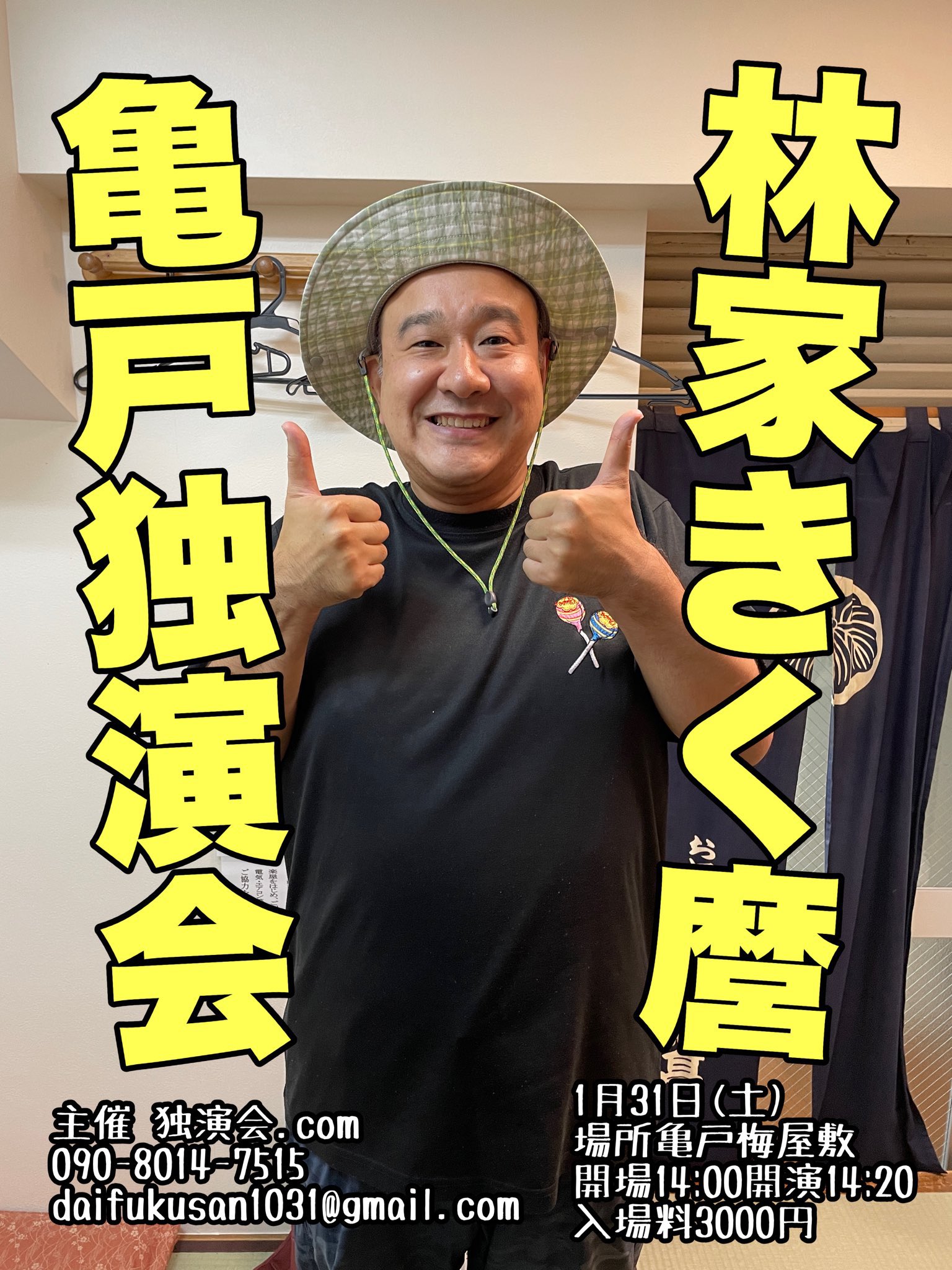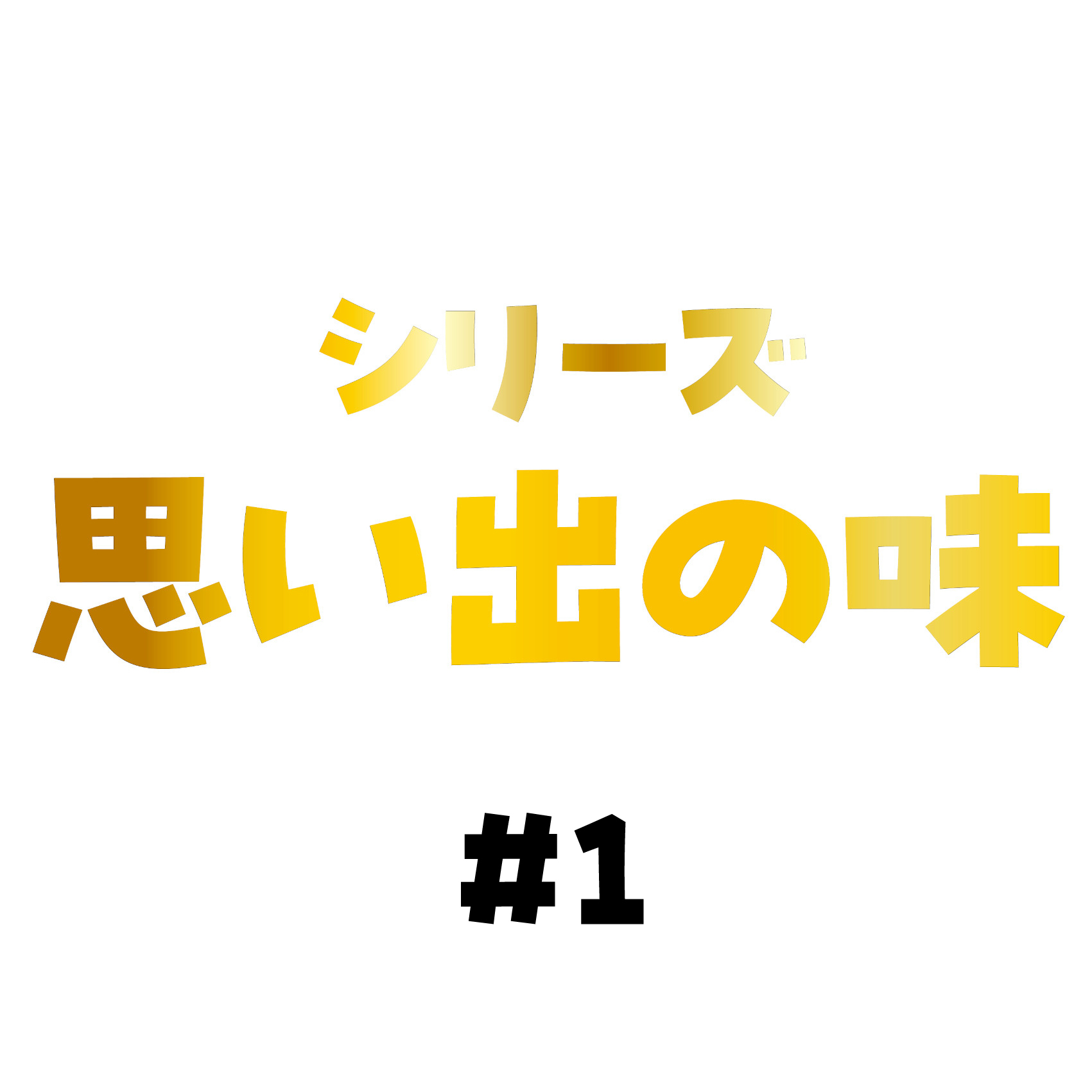2025年7月の最前線(聴講記:神田こなぎ真打昇進披露興行、二ツ目時代、軍談ウィーク。そして「琴調の夏」を前にして)
「講談最前線」 第4回
- 講談
聴講記② ~二ツ目時代
二ツ目は、真打になるための準備期間という見方もある。芸の幅を広げ、自分なりの芸を見つけ、奥行きも深めていく。その間、約10年。この間をどう過ごすかで、真打になってからの道が決まってくるとしてもいいだろう。
先に紹介した神田こなぎも研鑽を重ねた講談協会主催の会に「二ツ目時代」がある。会場はお江戸両国亭で、開催月は「西向く侍」。つまり2・4・6・9・11月だ。その6月22日の会を覗いてきた。
実は前日に「予約が少ない!」という演者からの情報を得て、ならばと日頃の達引(たてひき)の強いところを見せた訳でもある(笑)。
出演者は、一龍斎貞奈、田辺凌天、田辺一記の三人。ここに前座の宝井優星と一龍斎貞介が加わった。あれ? いつもであれば二ツ目はもっといるのに……と思っていたら、この日に会があるのをみんなして失念していて、来られるメンバーが集まったというのだ。みんな、落ち着け(笑)。
前講と呼ばれる前座はこの日、二人。宝井優星は「柳生十兵衛・江の島漫遊」。徳川家光に間者になることを命じられた十兵衛が天竺を目指すと言って江戸を出発。品川で駕籠屋に捕まり、最後に知恵伊豆(ちえいず:松平信綱のこと)に出会うといった展開。確かで、かつ丁寧な読みで安定感あり。ただし、修羅場も忘れないでいてほしい。
一龍斎貞介は、「臆病(おくびょう)一番槍」。テンション高く、押しの強い高座で聴き手を圧倒させる。「床几(しょうぎ:折畳式の腰掛け)」を「将棋」と同じアクセントで読むのが気にかかるのは、最近、ほかの演者でも耳にすることだ。
二ツ目時代のトップは、田辺一記による「黒部の山賊」から『山のバケモノたち』。北アルプスの山小屋の運営に携わる伊藤正一が、山賊の一人である遠山林平との交流から聞き知る山の不思議な出来事の話であり、夏を前にした一種の怪異譚だ。一記という名の由来は、「記録を読みたい」という思いからついたと聞いている。ならば今後、今回のような黒部に起こる山の伝説とどう向き合っていくのか。一記のいい意味での物静かな語り口から、物語に潜む怖さや恐ろしさを読みとしてどう湧きあがらせていくのかに期待したい。
ここで落語家のゲストが入り、中入り後に田辺凌天は「妲己(だっき)のお百」から『海坊主の怪』を読んだ。悪女お百の魂胆とその悪行を、読みのスピードをいつもより抑えつつ、その世界観を描いていく。これまで比較的明るく華やかに感じられる講談が似合っていると思ってきたが、この手の女の悪事を描いた物語も合っていると感じさせた一席だ。

田辺一記。お江戸両国亭にて
この日のトリは、一龍斎貞奈で『長谷川謹介物語』。台湾縦貫鉄道建設に貢献し、「台湾鉄道の父」と呼ばれた人物の伝記で、これがすこぶる面白かった。台湾に講談の仕事で呼ばれた際に、台湾新幹線の中で創作した一席と貞奈は話していたが、鉄道の中という空間感(と言えば良いか)と時間に追われた(?)緊張感が作品制作にいい方向性を与えたのか、濃密でかつわかりやすい、そしてどこかノスタルジーを感じさせる一席に仕上がっていた。
貞奈の読みは、リズム感やテンポを活かして読んでいくというより、話の肝を抑えながら、どこを聴いてほしいのかを考え、言葉の強弱や緩急を自在に用い、そこから話の波を作っていくところにある。この日の高座でも、長谷川謹介の偉業を確かな形で読みながら、その歴史的事実に対する貞奈の考えは、聴き手に同意を求めるがごとくに軟らかく読んでいた。
実は、今回はじめて長谷川謹介なる人物を知ったのだが、講談という芸を通して、また新たな歴史とその歴史を作った人に出会うことができた。舞台を台湾にした講談としては、大先輩の一龍斎貞花が「李登輝(りとうき)伝」や、台湾にダムを建設した「八田與一(はったよいち)」を送り出して好評を得ているが、その作品と同じように、これから先、読み込んでいくことで貞奈の代表作となり得るだろう。
一件。この日、中入り前に上記の事情もあって、落語家のゲストがあった。聴き手として、講談に対する集中力と言えばいいだろうか、それが途切れてしまうように感じた。ゲストの演者が悪いと言うのではない。出演者が足りなければ、例えば、その日、先に上がった講釈師が二度上がりをする等の対応でも良かったのではないか。そうした番組の流れを考えるのも、こうした勉強会での意義と言えよう。次回の二ツ目時代は9月22日の開催で、宝井小琴の二ツ目昇進祝いを兼ねる。