たいこ腹、粗忽長屋、甲府い
林家はな平の「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第2回
- 落語

林家 はな平
2025/06/06
六席目 『甲府い』 ★★★
◆【あらすじ】
両親に先立たれ、親戚に育てられた甲府(今の山梨県)生まれの善吉(ぜんきち)。身延山(久遠寺)に5年の願掛けをして、東京で身を立てようと出てきたが、浅草でスリに会い無一文に。腹を空かせて、出来心で豆腐屋の店先のおからを食べてしまう。
店の若い衆に見つかって殴られそうになるところを親方が止め、事情を聞く。親方も日蓮宗を熱心に信仰していて、これは何かの縁と家に置くことにする。それから善吉が豆腐の荷を担いで「豆腐ーい、胡麻入りー、がんもどき」と売って歩く。
3年後、善吉の働きぶりと人柄に惚れ込んだ親方夫婦は、善吉を娘のお夏の婿として迎える。夫婦になった二人が店を継いで、善吉が東京へ出て来て5年の月日が経つ。身延山に願解き(がんほどき)でお礼参りに行きたいと言う。親方夫婦は、もちろん喜んで送りだすことにする。
翌朝、親方夫婦に振る舞われたお赤飯とお酒を飲んだ二人は、旅ごしらえで振り分けの荷物を持って身延山へ旅立つ。
◆【オチ】
普段、豆腐を売る姿しか見たことのない二人が、旅姿なのを見て驚いた近所の者が声をかける。
近所の者「おーい! お二人さん! どこ行くんだーい?」
善吉「甲府ーぃ」
てえと、後から付いて来たお夏が、
お夏「お参りぃー、願ほどきー」

◆【解説】
「豆腐ーぃ、胡麻入り、がんもどき」と、「甲府ーぃ、お参り、願ほどき」が掛かっている。
洒落で終わるオチは、☆1つにしがちだが、この噺には☆を3つあげたい。3つの単語が掛かっているのも要因だが、人情噺に近く、しっとりした内容で笑いも少ない噺なのに、最後が洒落で終わるところがなんとも可笑しいのだ。まじめな若夫婦に洒落を言わせているのが好きだ。これは筆者の主観だから仕方がない。
オチを善吉ひとりに、ひと息で言わせる型の方が多いと思うが、筆者は夫婦二人の割り台詞にしている。お夏の優しい売り声が噺を包み込むような気がするからだ。
この噺は、とくに山場はない地味な噺だ。信心のおかげか、縁に恵まれ良い人(世話焼きの親方)に出会った主人公が商売をさせてもらい、所帯も持てたというただそれだけの噺だ。
だけど、人の一生はそういう縁の積み重ねで成り立つものだと思うので、筆者には妙に共感がある。
それと「江戸」を「東京」と呼ぶようになったのは1868年の明治以降で、歴史は意外と古い。教えて頂いた方が「東京」だったので、筆者も東京で演じている。
(毎月6日頃、掲載予定)
―― こちらもどうぞ。林家はな平の「オチ研究会」シリーズ連載一覧
いま読まれています!

「二藍の文箱」 第5回
異国の路地、迷子の入口
~誰もしらない自分に出会う旅

三遊亭 司
2025/10/02
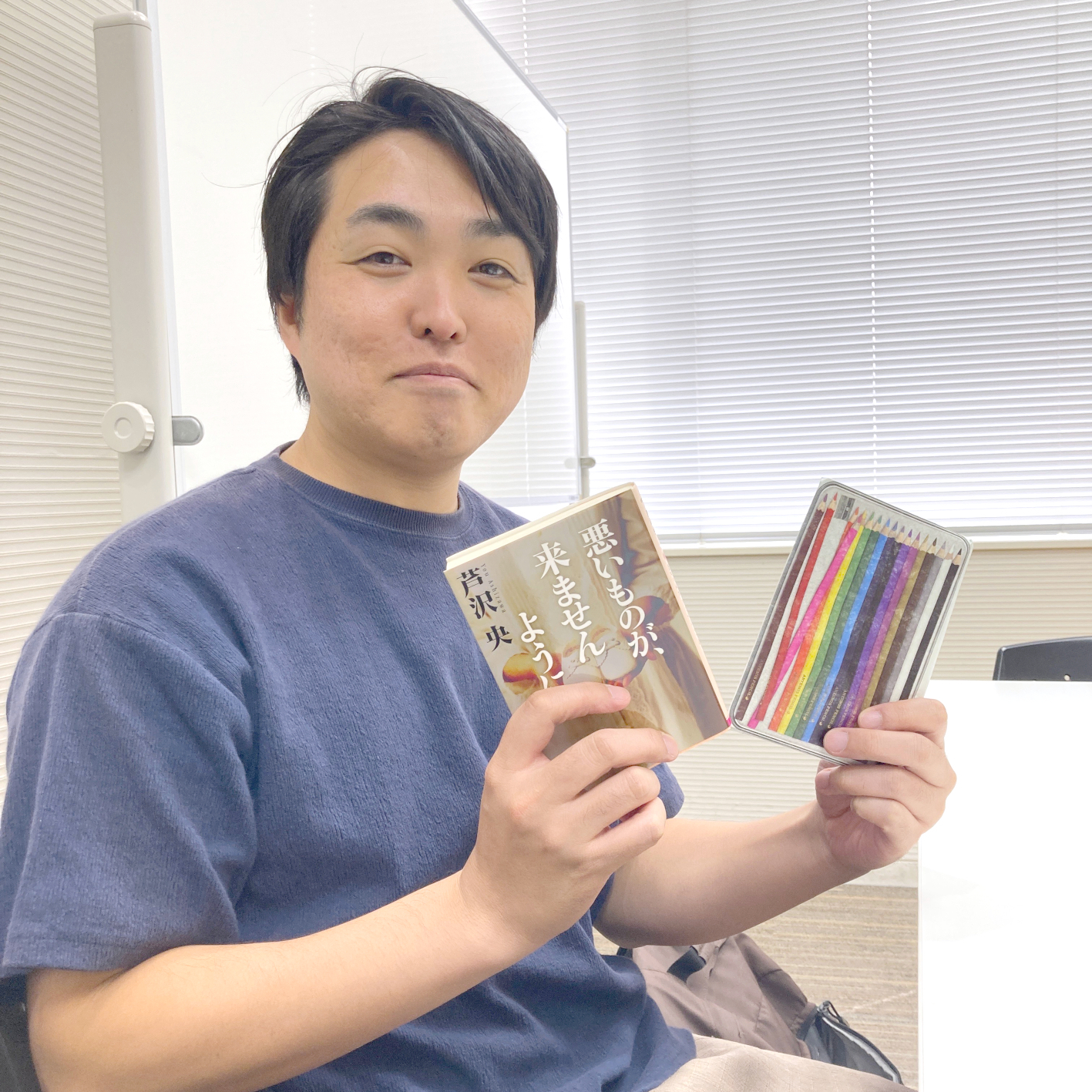
「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回
〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)
~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光
2025/09/30

「酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~」 第3回
三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉
~幕末ロマンと伏見の名酒を楽しむ、幸せな旅

松林 伯知
2025/10/01
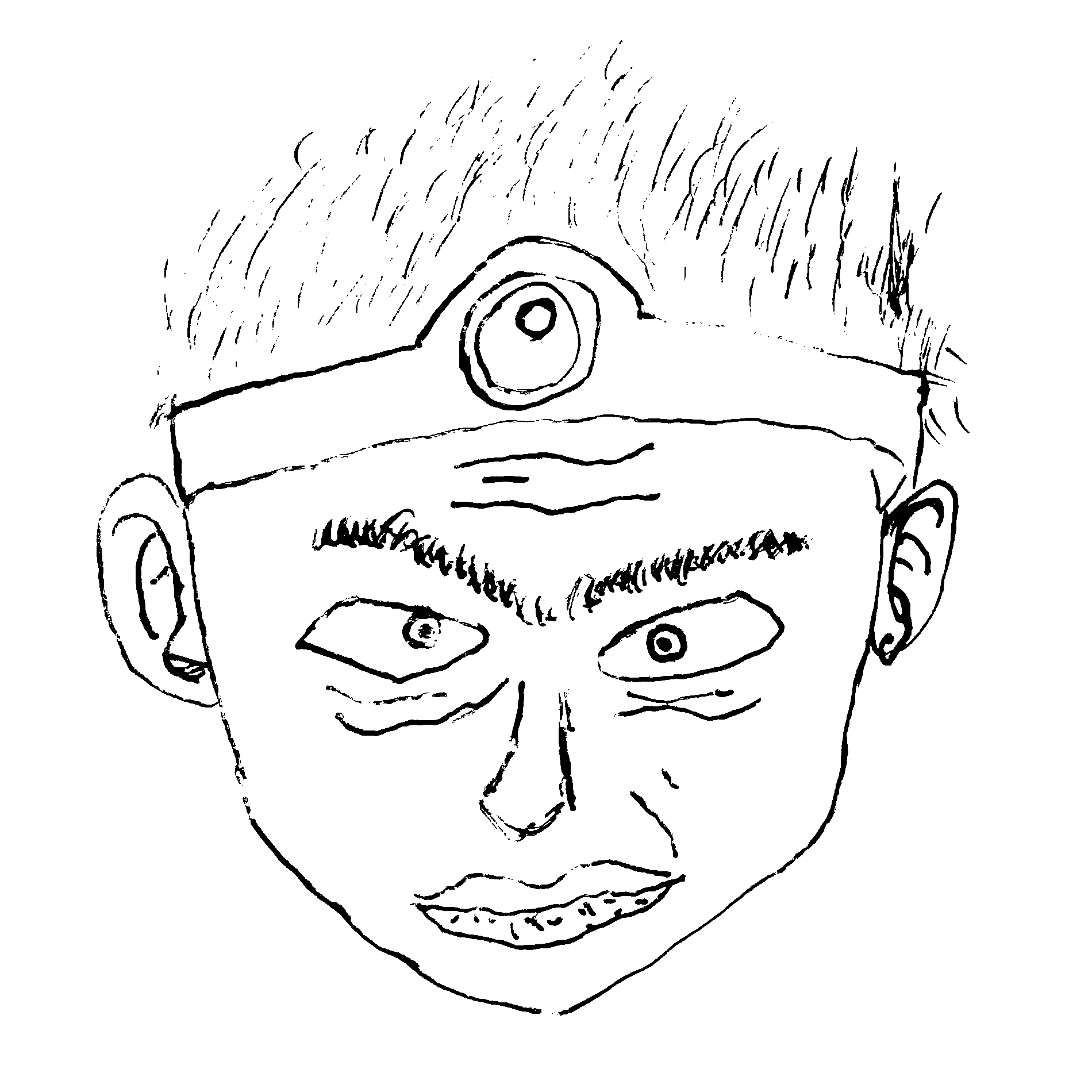
「まだ名人になりたい」 第4回
そして現実へ
~私はまだ人から褒められたいのです!

柳家 さん花
2025/08/01

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回
言霊のブーメラン
~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎
2025/09/25

「テーマをもらえば考えます」 第2回
名月
~世の中で最強なのは団子だよね!!

三遊亭 天どん
2025/09/30
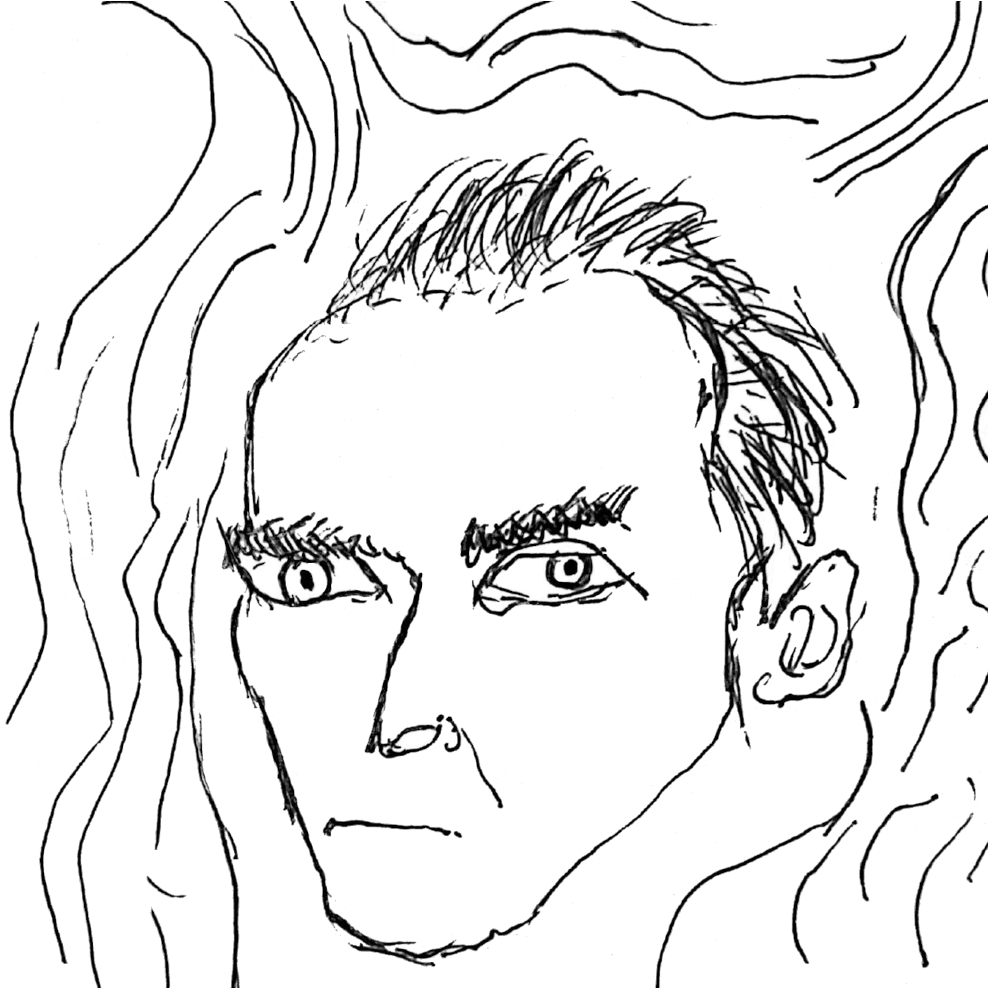
「まだ名人になりたい」 第3回
泣きっ面にう○○
~私はゴッホだ! あなたもゴッホだ!

柳家 さん花
2025/07/02

三遊亭朝橘の「朝橘目線」 第1回
ここもカフェ?と思って見ると美容院
~私なりのコーヒー愛

三遊亭 朝橘
2025/05/08

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第13回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(後編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/29
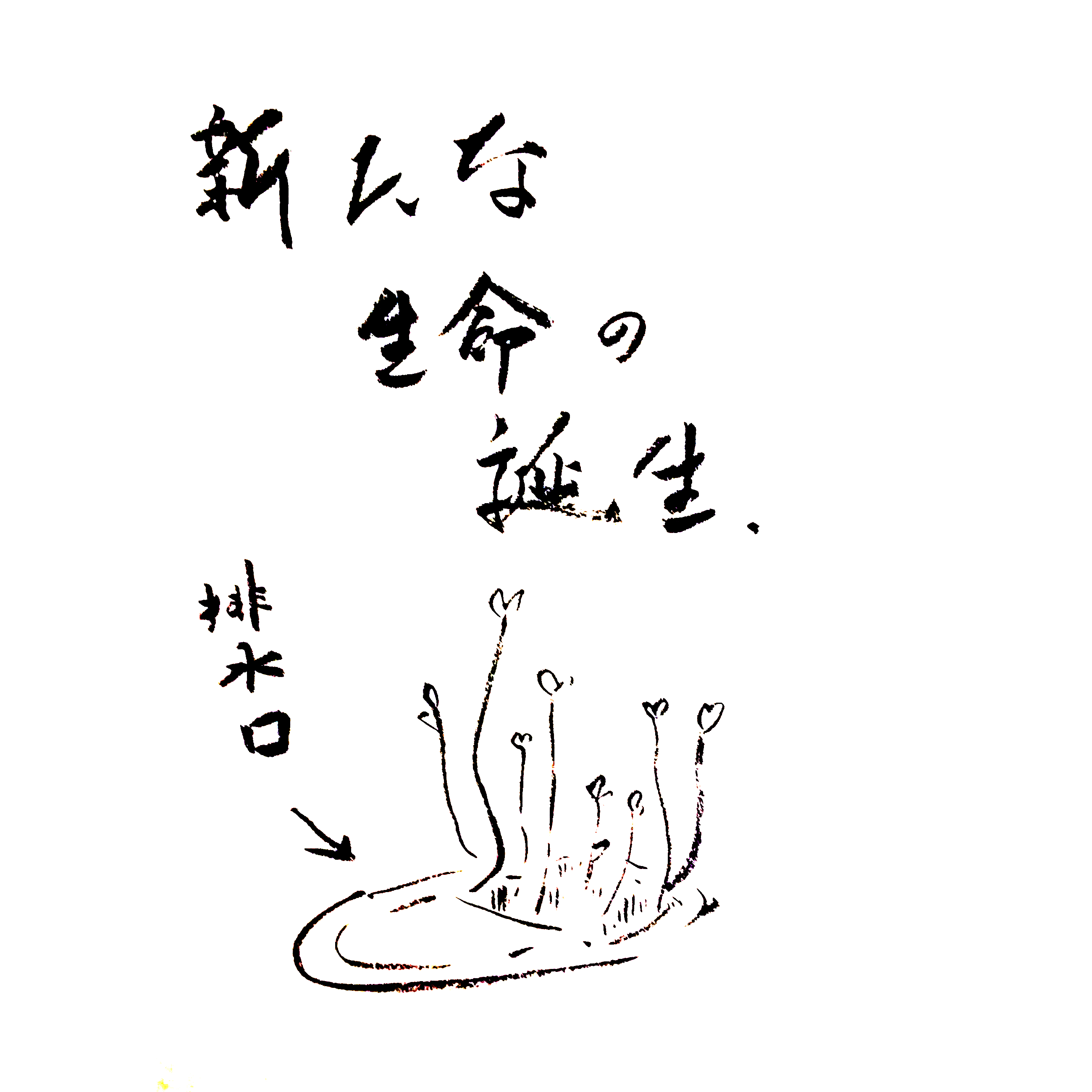
「エッセイ的な何か」 第3回
8/31は、野菜の日 →ミョウガ21本を食べた男の記憶
~落語『茗荷宿』のウソとホント

三笑亭 夢丸
2025/08/19
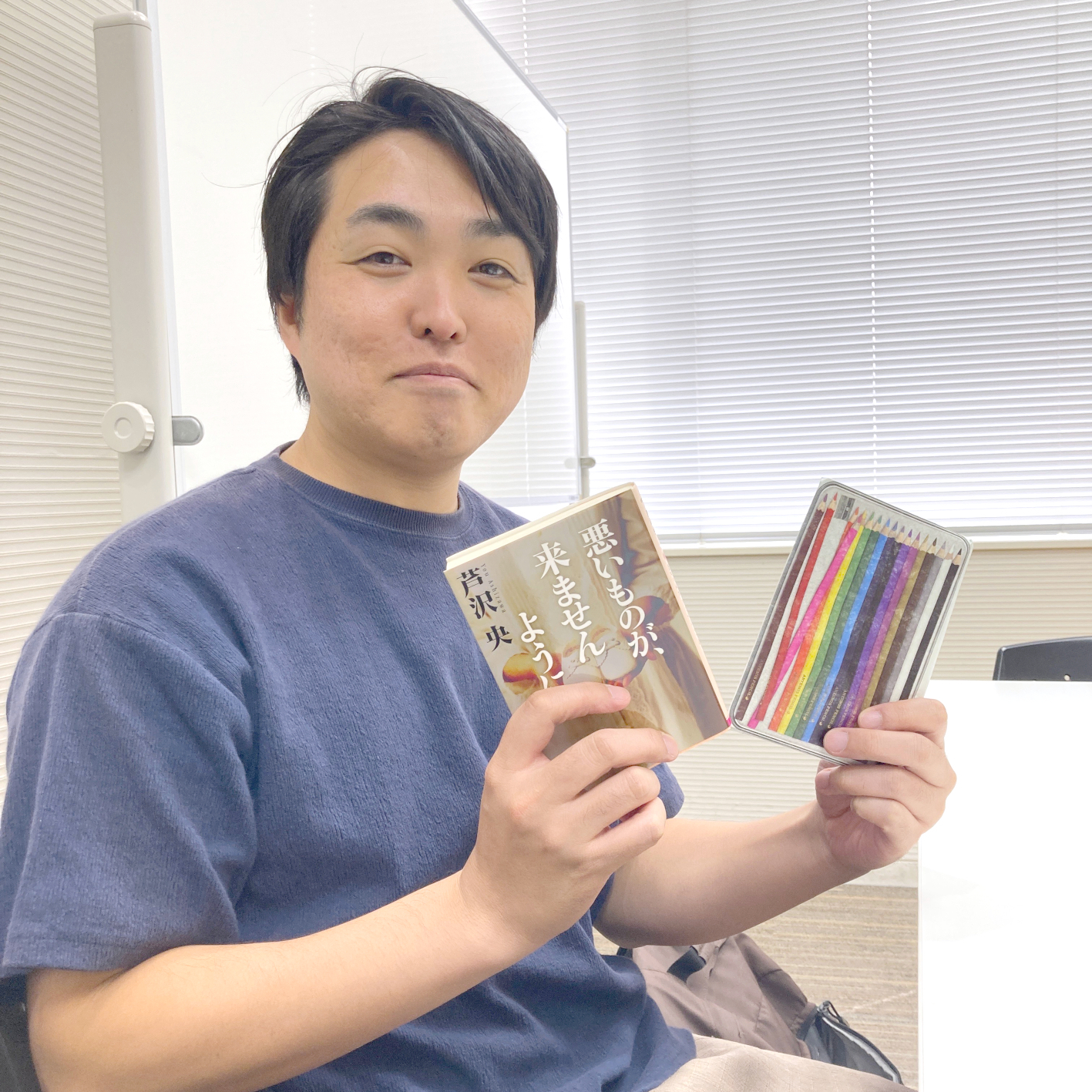
「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回
〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)
~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光
2025/09/30

「テーマをもらえば考えます」 第2回
名月
~世の中で最強なのは団子だよね!!

三遊亭 天どん
2025/09/30

「酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~」 第3回
三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉
~幕末ロマンと伏見の名酒を楽しむ、幸せな旅

松林 伯知
2025/10/01

「二藍の文箱」 第5回
異国の路地、迷子の入口
~誰もしらない自分に出会う旅

三遊亭 司
2025/10/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回
言霊のブーメラン
~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎
2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第13回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(後編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/29

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第12回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(中編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/28

「二藍の文箱」 第4回
かたばみ日記 令和7年 夏
~暑い夏もまた愉しい

三遊亭 司
2025/09/02
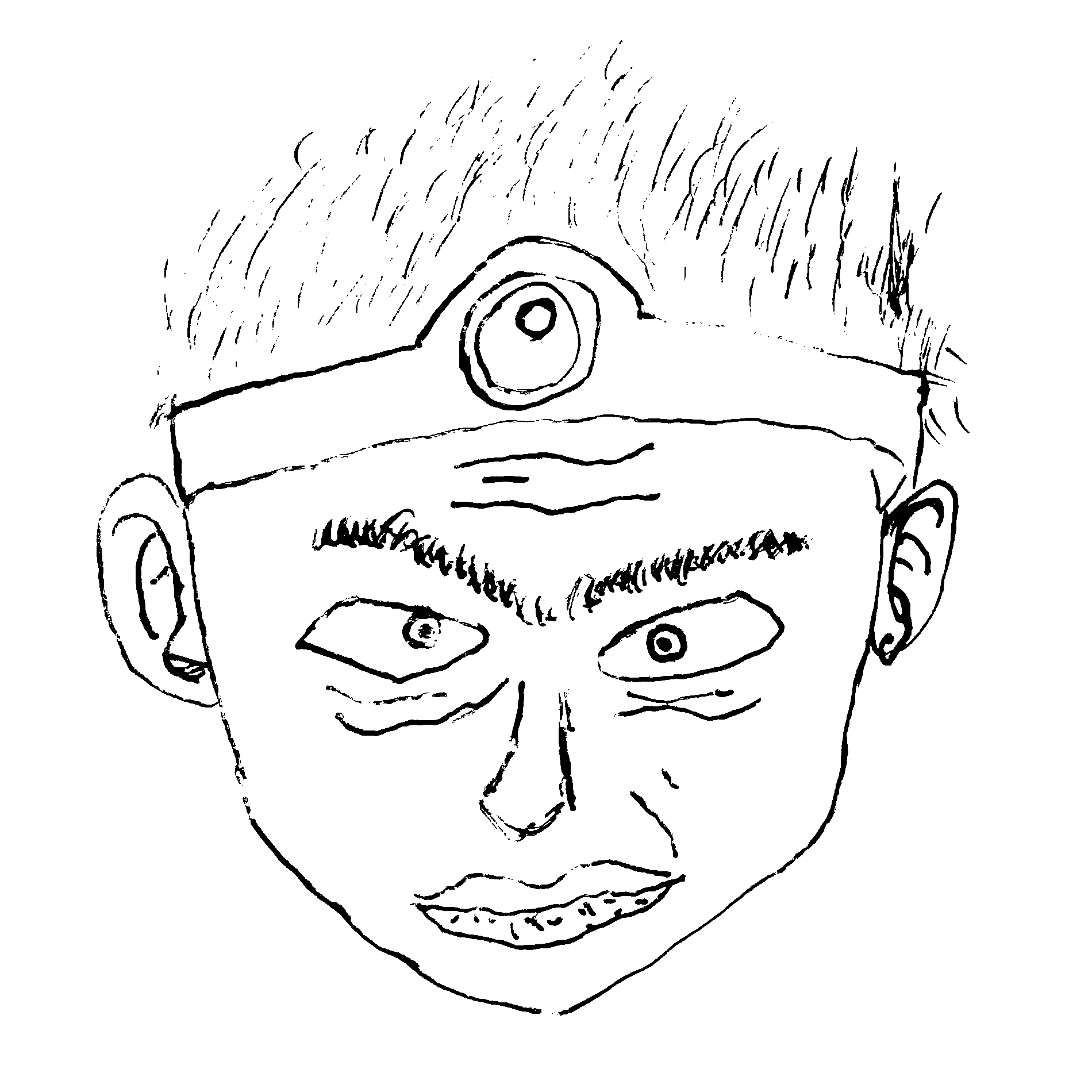
「まだ名人になりたい」 第4回
そして現実へ
~私はまだ人から褒められたいのです!

柳家 さん花
2025/08/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/27
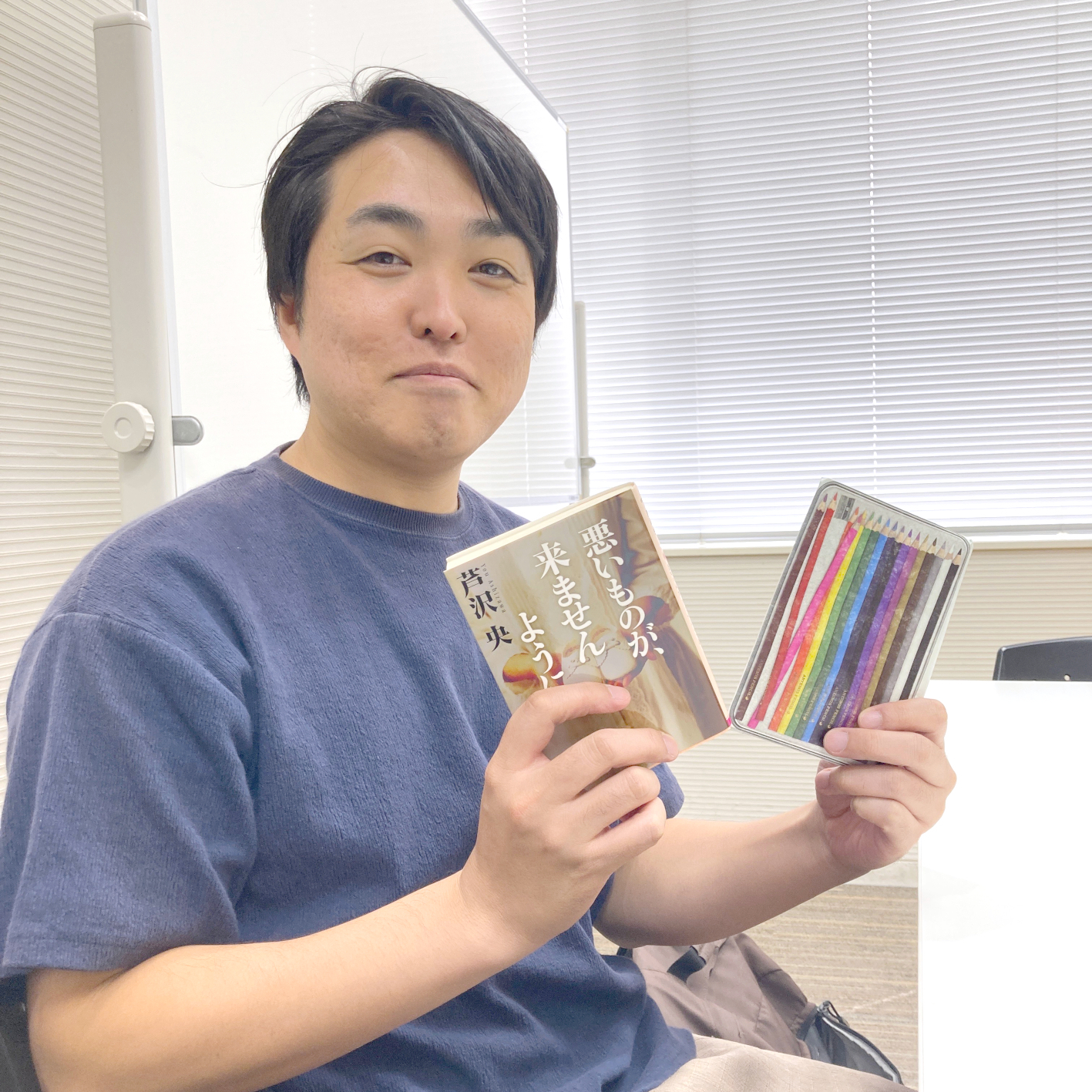
「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回
〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)
~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光
2025/09/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第12回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(中編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/28

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第13回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(後編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/29
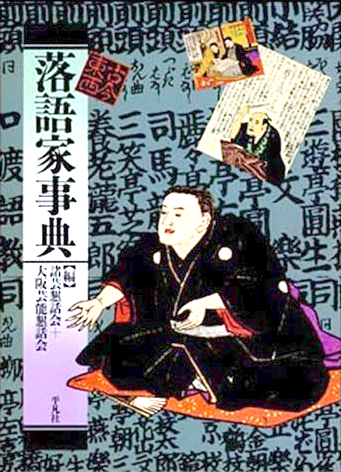
「芸人本書く派列伝 クラシック」 第5回
〈書評〉 古今東西落語家事典 / 東都噺家系図
~落語界の不思議を紐解く、名著二冊

杉江 松恋
2025/09/29

「すずめのさえずり」 第三回
恩人について
~佐竹雅昭さんが教えてくれた本当の強さ

古今亭 志ん雀
2025/09/26

「テーマをもらえば考えます」 第2回
名月
~世の中で最強なのは団子だよね!!

三遊亭 天どん
2025/09/30

「ずいひつかつどお」 第4回
まんまるおつきさま
~月の美しさと伝えられない想い

立川 談吉
2025/09/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回
言霊のブーメラン
~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎
2025/09/25

「マクラになるかも知れない話」 第二回
栗と私
~栗から考える人生の機微

三遊亭 萬都
2025/09/24

鈴々舎馬風一門 入門物語 第15回
捨て犬のブルース (前編)
~16歳の高校生、噺家の弟子になる!

柳家 平和
2025/09/04

「令和らくご改造計画」
第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」
~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/09/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第5回
落語愛を、次世代へ ~あの日の感動を、息子も知った
~はじまりは、いつもあの時の「新鮮な気持ち」

シン・道楽亭
2025/09/10

鈴々舎馬風一門 入門物語 第16回
捨て犬のブルース (後編)
~『タイガー&ドラゴン』の世界へ!

柳家 平和
2025/09/05
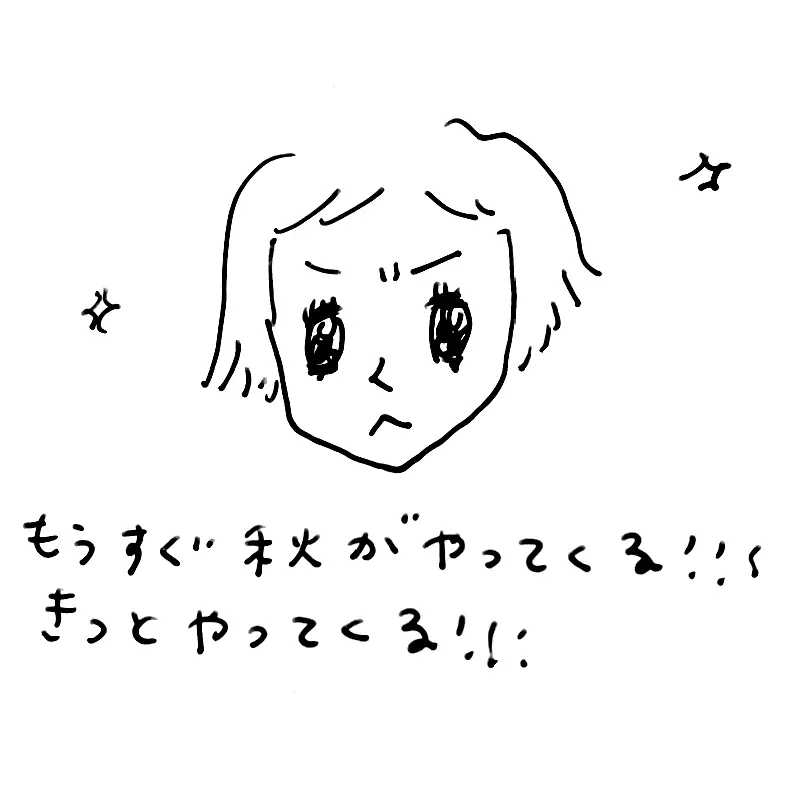
「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回
夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい
~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春
2025/09/03
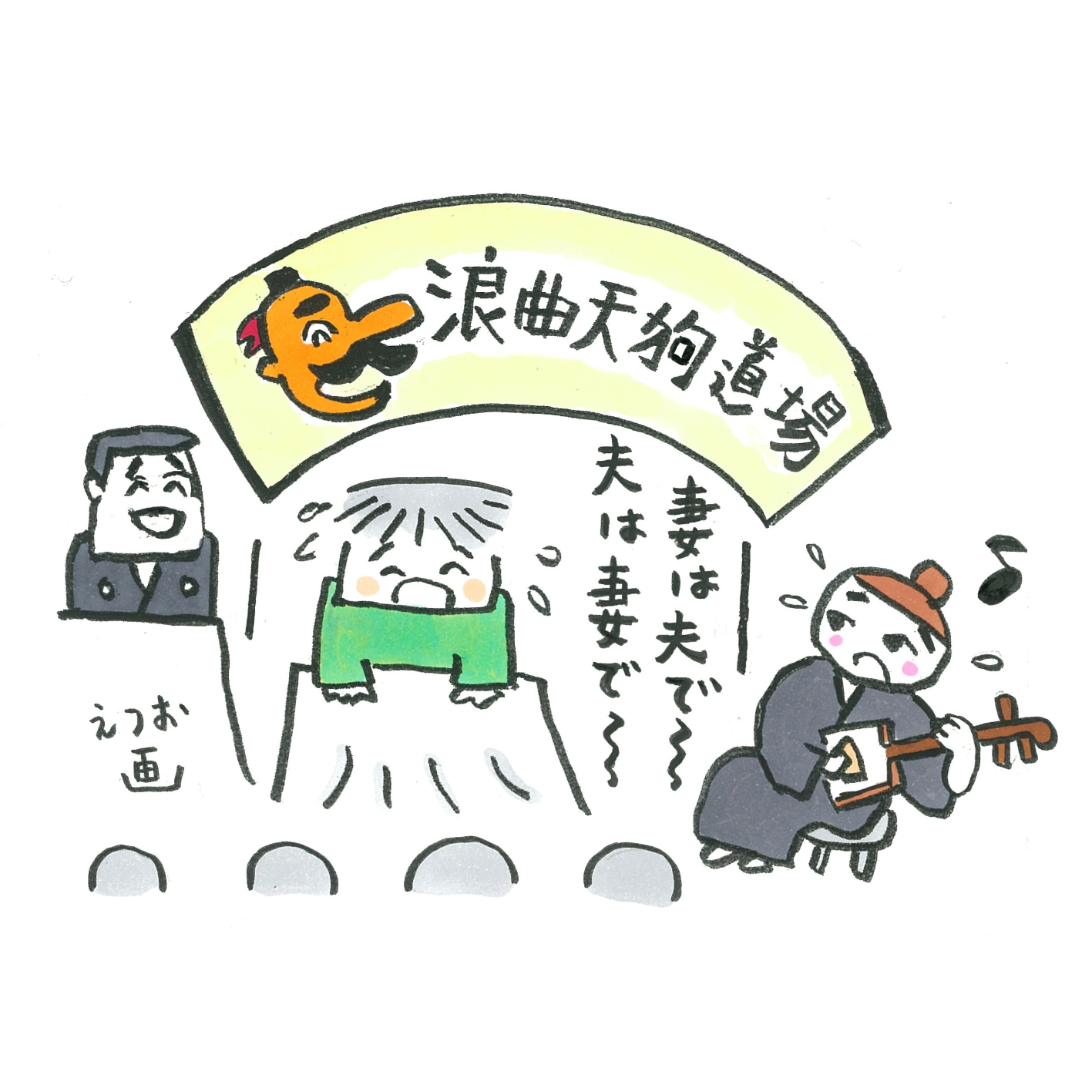
「浪曲案内 連続読み」 第5回
君は『浪曲天狗道場』を知っているか
~浪曲の「素人のど自慢番組」がラジオを席巻した時代

東家 一太郎
2025/09/15

月刊「浪曲つれづれ」 第5回
2025年9月のつれづれ(富士実子、広沢美舟、国本はる乃、玉川奈々福、それぞれの躍動)
~銀座の地下で響く浪曲の魂

杉江 松恋
2025/09/09

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回
言霊のブーメラン
~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎
2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/27

「令和らくご改造計画」
第一話 「危機感をあなたに」
~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/08/12
編集部のオススメ

「酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~」 第3回
三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉
~幕末ロマンと伏見の名酒を楽しむ、幸せな旅

松林 伯知
2025/10/01
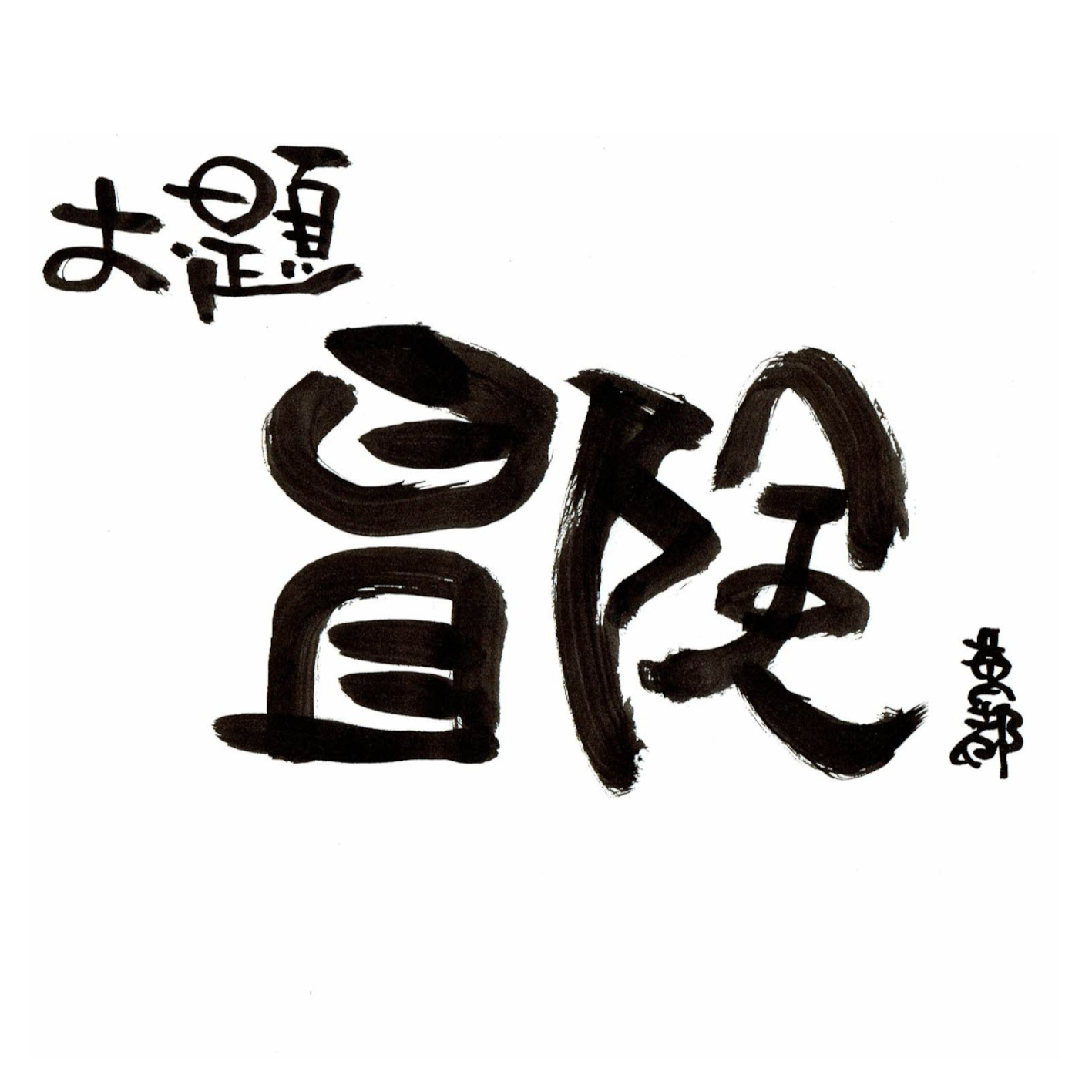
「マクラになるかも知れない話」 第一回
夏の日の少年
~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都
2025/08/24

シリーズ「思い出の味」 第11回
食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶
~焼肉は落語

桂 笑金
2025/08/17

「令和らくご改造計画」
第一話 「危機感をあなたに」
~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/08/12
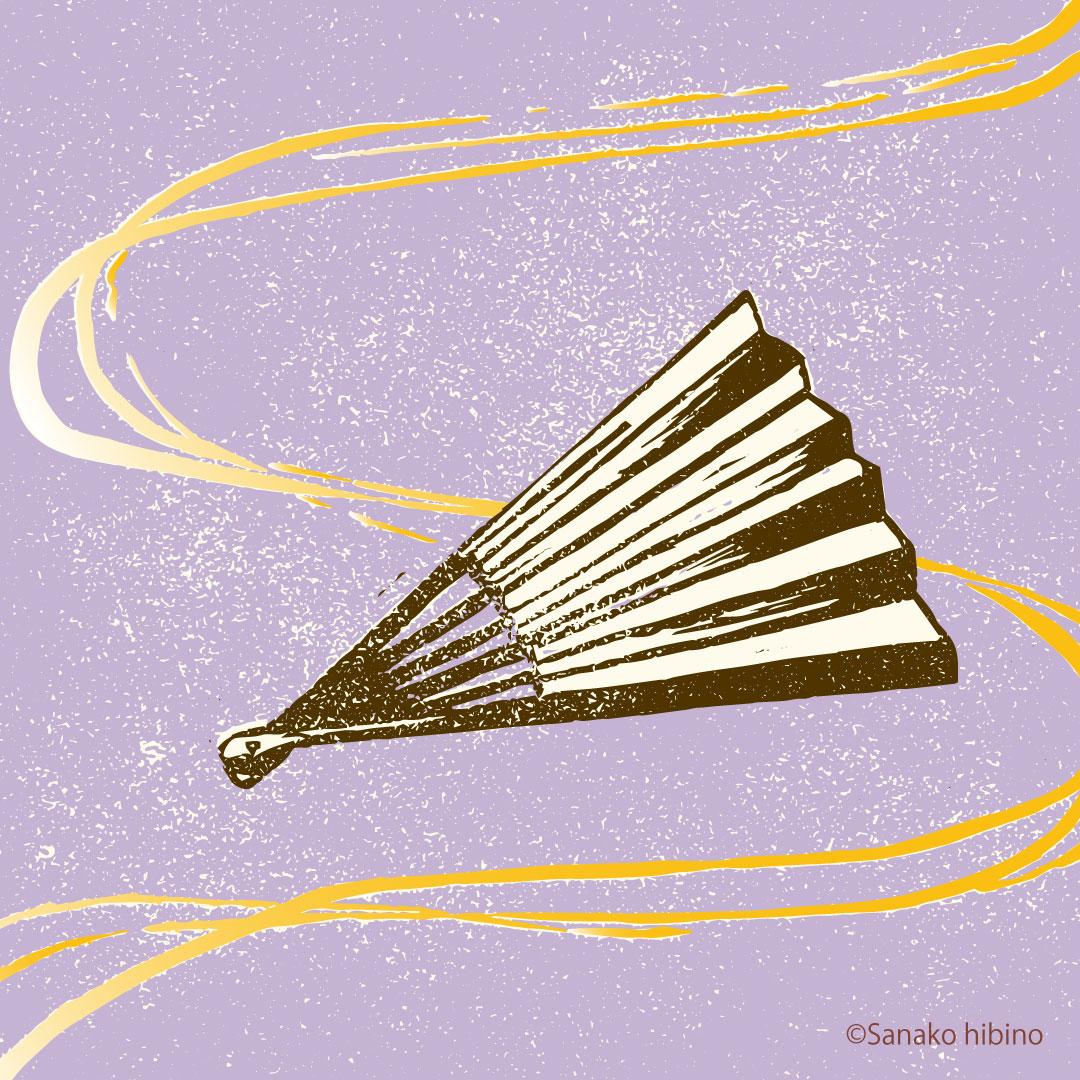
「二藍の文箱」 第3回
前座見習に師匠見習
~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司
2025/08/02

「くだらな観音菩薩」 第2回
阿修羅
~私は良い人なので、お気軽に話しかけてくださいね!

林家 きく麿
2025/06/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第2回
席亭への道 ~服部、落語に沼る人生
~還暦過ぎからが人生

シン・道楽亭
2025/06/10

