21900のいただきます
シリーズ「思い出の味」 第1回
- 落語

三遊亭 司
2025/05/13

今も思い出す、懐かしい味と、かけがえのない時間の記憶
24年前の朝
オヤジさん。いつのころからか、師匠三遊亭歌司のことをそう呼ぶようになった。
盆暮れの挨拶やお中元、お歳暮に限らず、お礼やお詫びにわたしたち落語家は身体を運ぶ。礼状を送ることはあっても、盆暮れの挨拶は師匠や先輩方、客先に「お世話になりました」と、心ばかりの進物を持参する。わたしの家に出入りする後輩たちも例外ではなく、みなそうだ。
その年の暮れの挨拶も、そういうわけで師匠が在宅であろう日時を見計らい訪問すると、案の定師匠は家にいて、めずらしく台所に立っていた。
「お前は間がいいなぁ、いまちょうど牡蠣鍋ができるとこ。見てたみてぇだな」
と、缶ビールを渡される。これでも飲んで待っていろということなので、プシュっとやって「いただきます」と。
そう時間がかからず出された牡蠣鍋は、味噌仕立てだった。「喰え」に、「いただきます」と箸を伸ばして、はふはふといただく。
「旨いですね。しかし、20年以上いてオヤジさんの手料理ははじめてじゃないですか」
「なに言ってンだよ。俺んとこきて寄席の初日の翌朝、トースト焼いてやったじゃねぇか」
そうだった、確かに24年前にそんな朝があった。出戻り前座として寄席に入った初日。一門の三遊亭若圓歌師がトリの興行だったため、師匠歌司も顔付されており、打ち上げから、二軒目は師匠宅近所の行きつけの焼鳥屋へ。そう遅い時間ではなかったが「泊まれ」となり、翌朝顔をあたって居間に行くと、出してくれたのが、師匠手ずから焼いた食パンのトースト。
そのころはオヤジさんだなんてとんでもない、師匠と呼ぶことすらぎこちなかった。いま思えば、あの「泊まれ」と翌朝のトーストは、師匠なりに距離を詰めようとしてくれたのだと、想像するに難くない。あれから四半世紀近く経ち、ひとつ鍋のものを遠慮せず、他愛もないはなしをしながらつつくぐらいの間柄、オヤジさんと弟子になっていた。
いま読まれています!
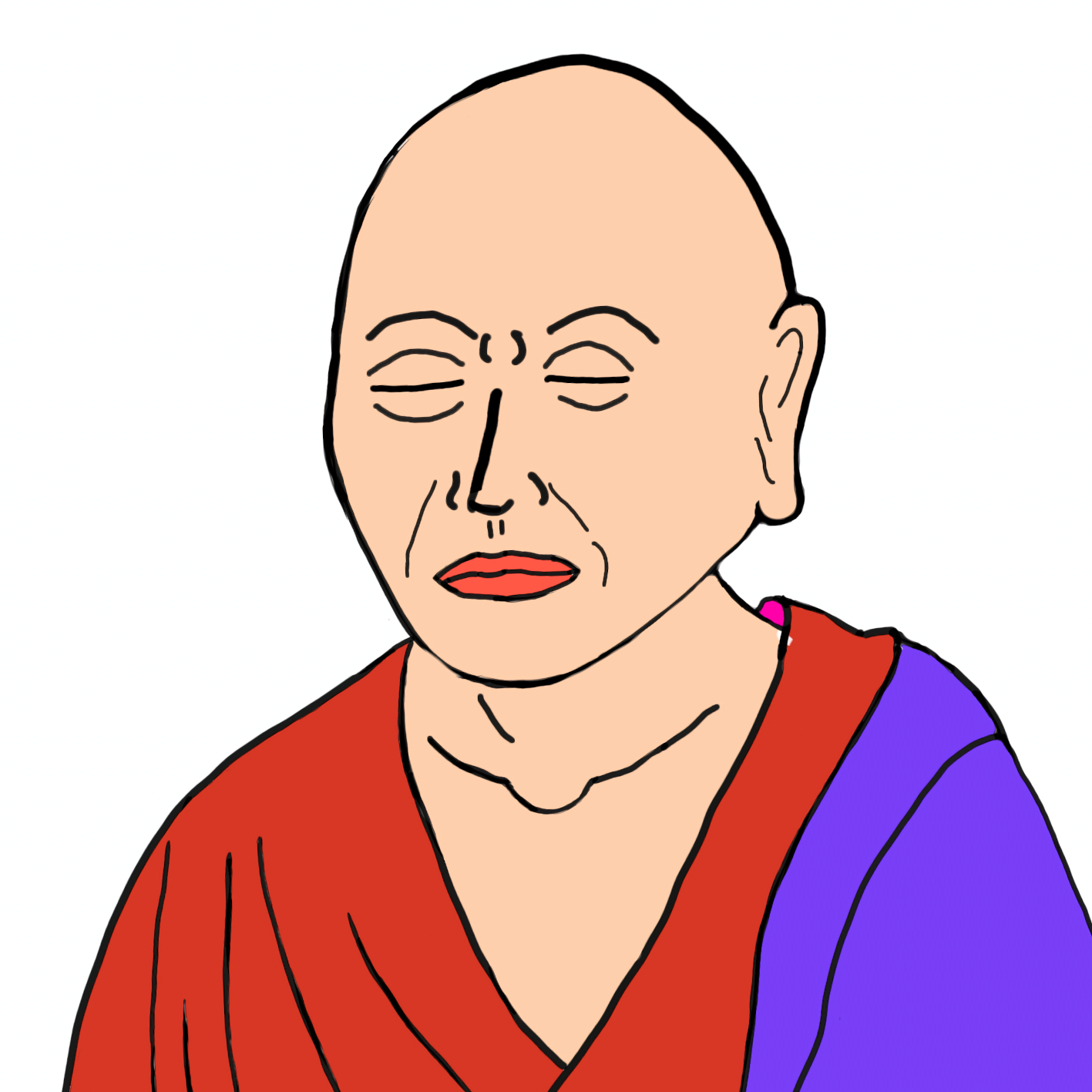
「くだらな観音菩薩」 第6回
鑑真和上
~そう、諦めちゃあいけないんだ

林家 きく麿
2025/10/16
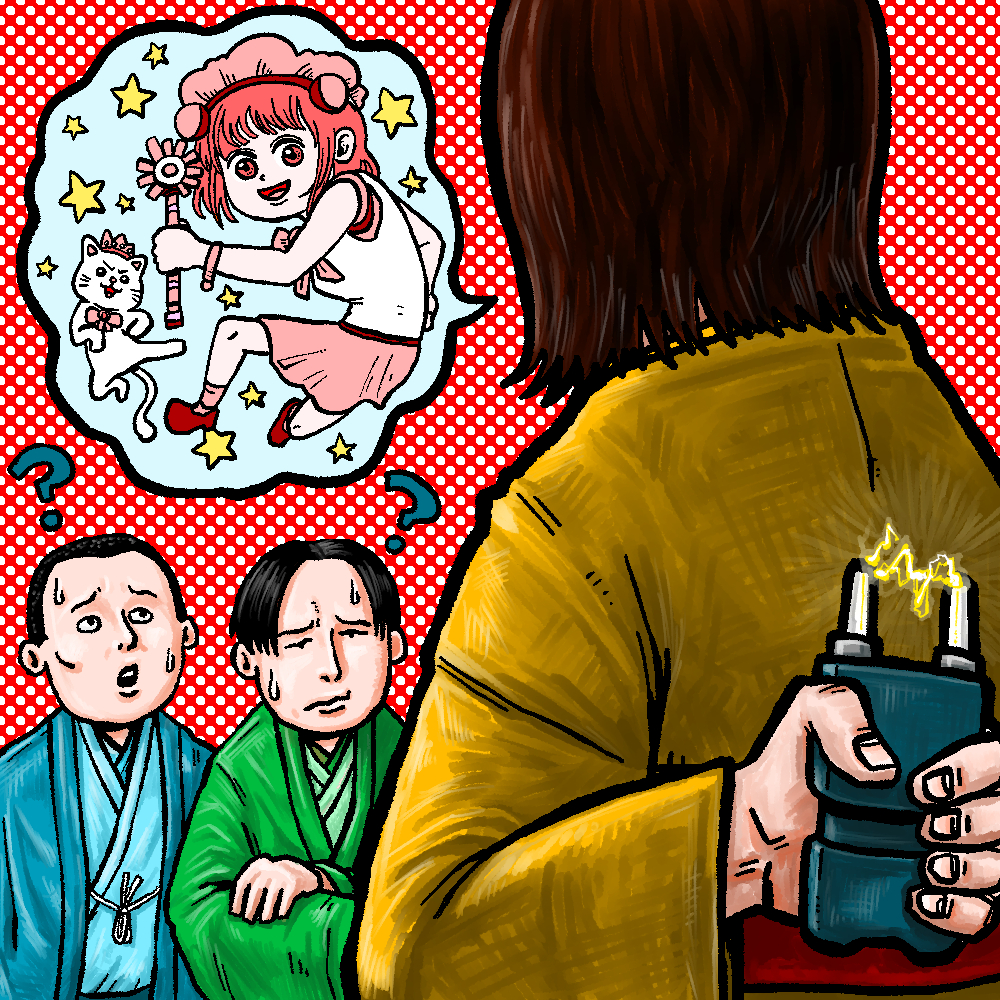
「令和らくご改造計画」
第三話 「内輪ノリ」
~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/10/12

シリーズ「思い出の味」 第13回
二つの乳に育てられし
~木綿豆腐、絹ごし豆腐、豆乳、絹揚げ、おからの炊いたん!

月亭 天使
2025/10/15

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回
言霊のブーメラン
~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎
2025/09/25

鈴々舎馬風一門 入門物語 第12回
青春の終わりに入門。青春の始まりの入門 (後編)
~楽屋で学んだ人生のLUCK GO!

柳家 獅堂
2025/06/05

「まだ名人になりたい」 第5回
秋白し
~私は秋の名物に「発情期の鹿」を加えたい!

柳家 さん花
2025/10/13
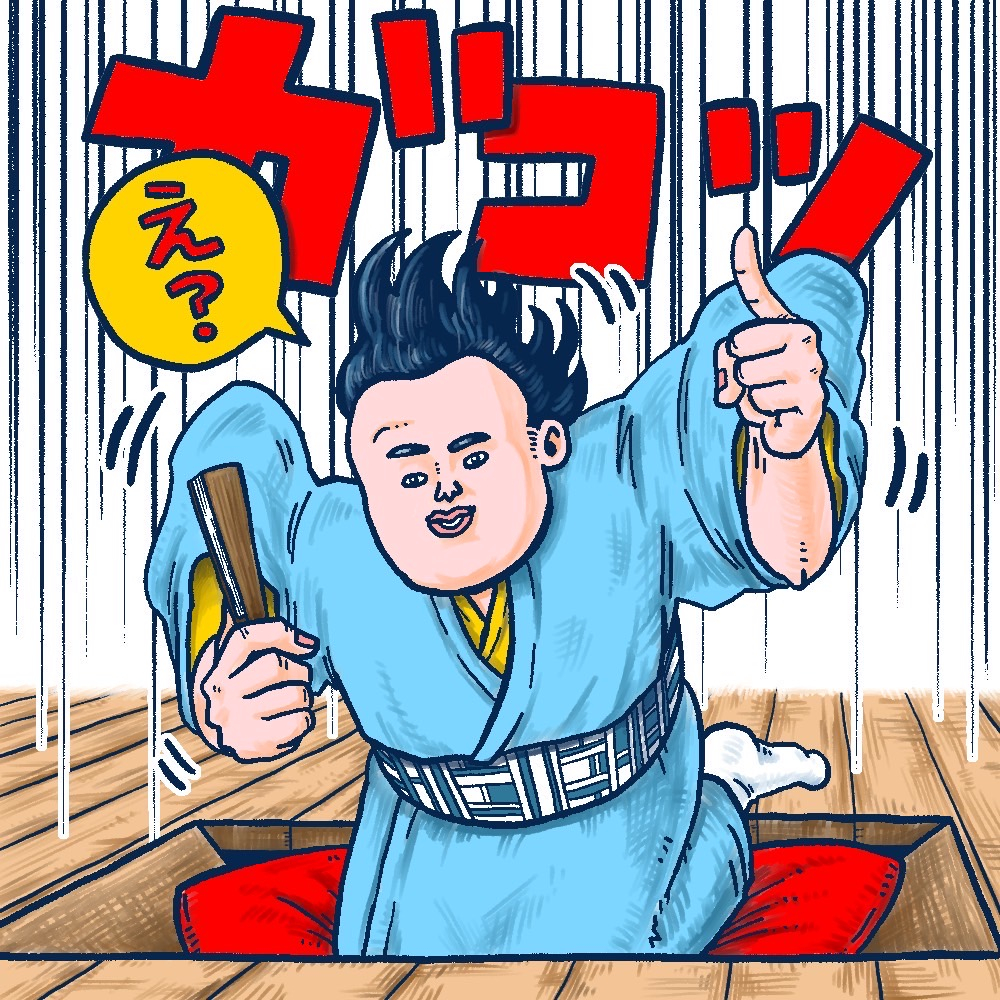
「令和らくご改造計画」
第一話 「危機感をあなたに」
~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/08/12

鈴々舎馬風一門 入門物語 第1回
ドンといけ美馬 (前編)
~運命のいたずらで落研に

鈴々舎 美馬
2025/05/01

シリーズ「思い出の味」 第11回
食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶
~焼肉は落語

桂 笑金
2025/08/17
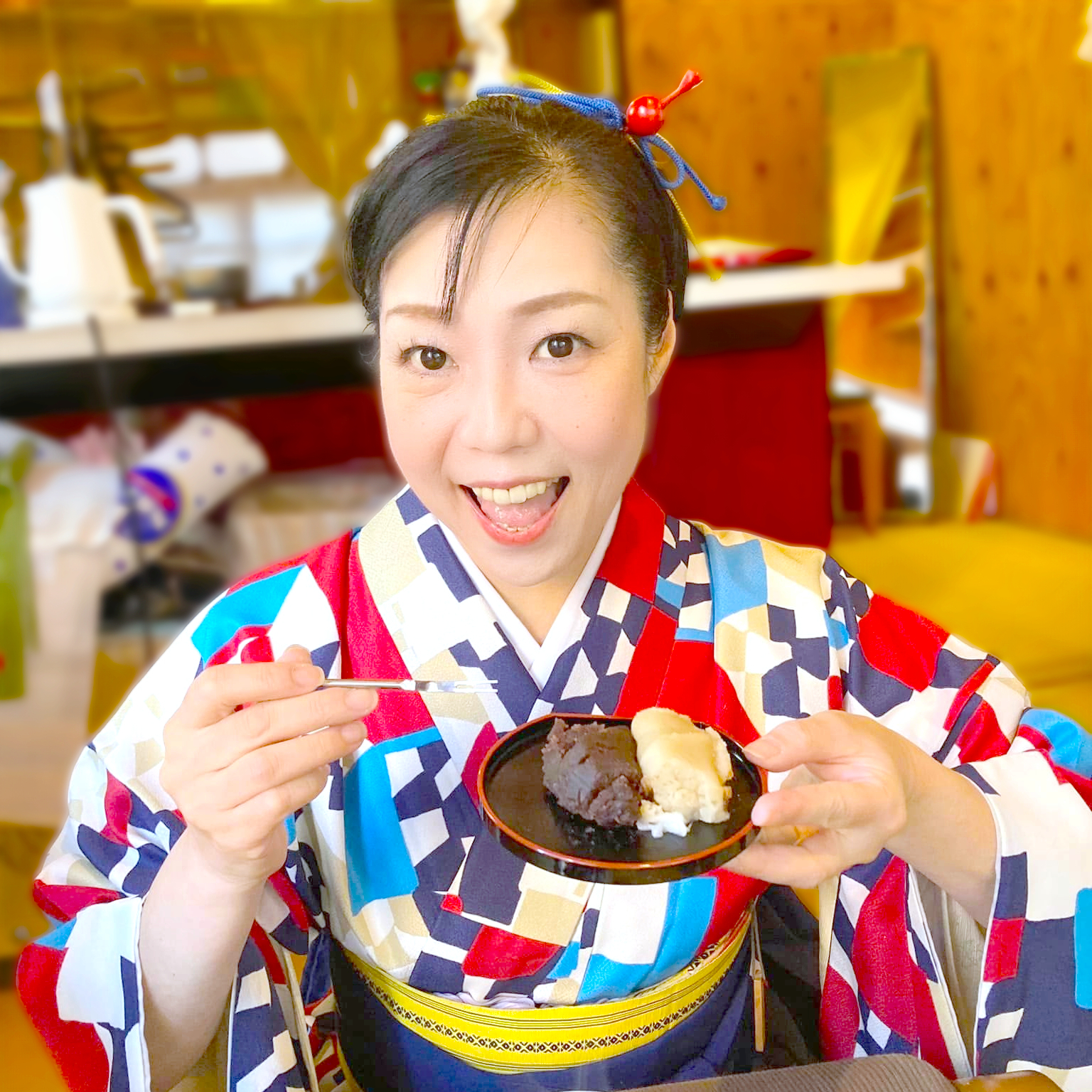
「講談最前線」 第8回
2025年10月の最前線 【前編】 (神田紅佳インタビュー)
~一年の集大成! 木馬亭での独演会に注目

瀧口 雅仁
2025/10/04
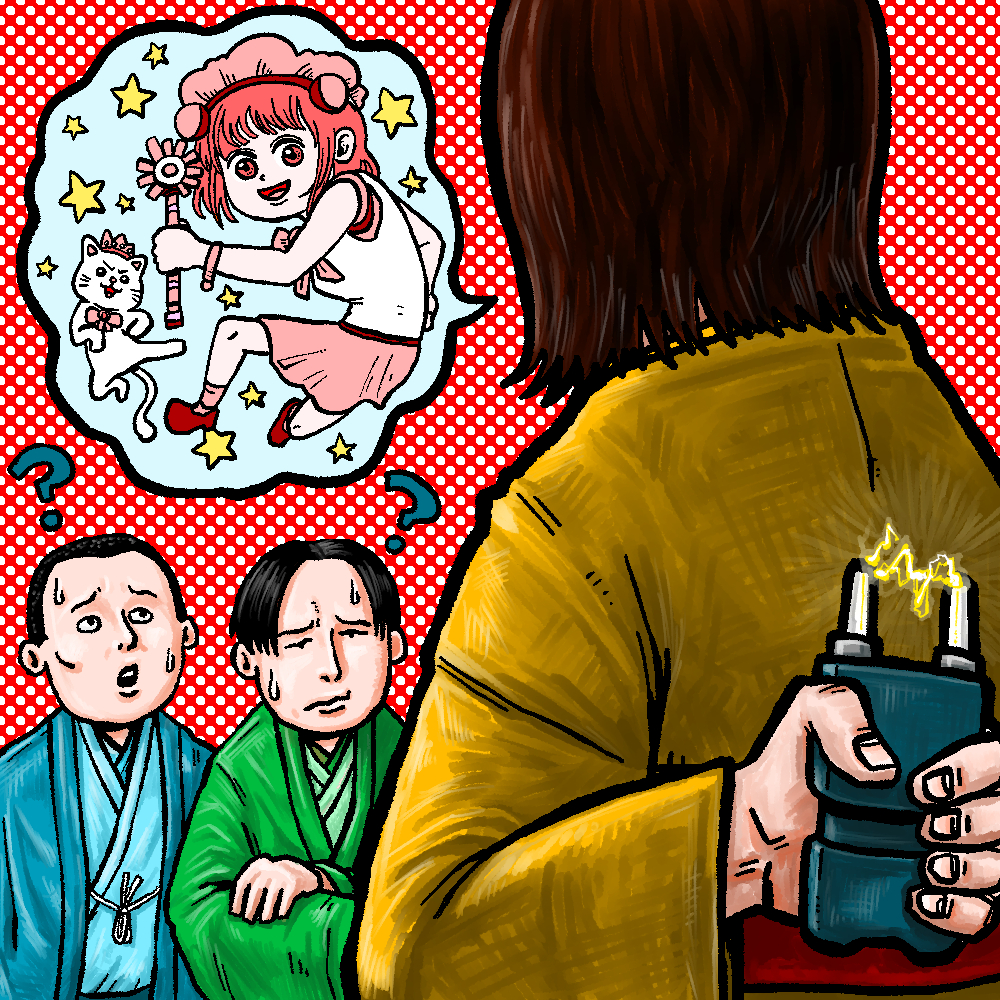
「令和らくご改造計画」
第三話 「内輪ノリ」
~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/10/12

シリーズ「思い出の味」 第13回
二つの乳に育てられし
~木綿豆腐、絹ごし豆腐、豆乳、絹揚げ、おからの炊いたん!

月亭 天使
2025/10/15
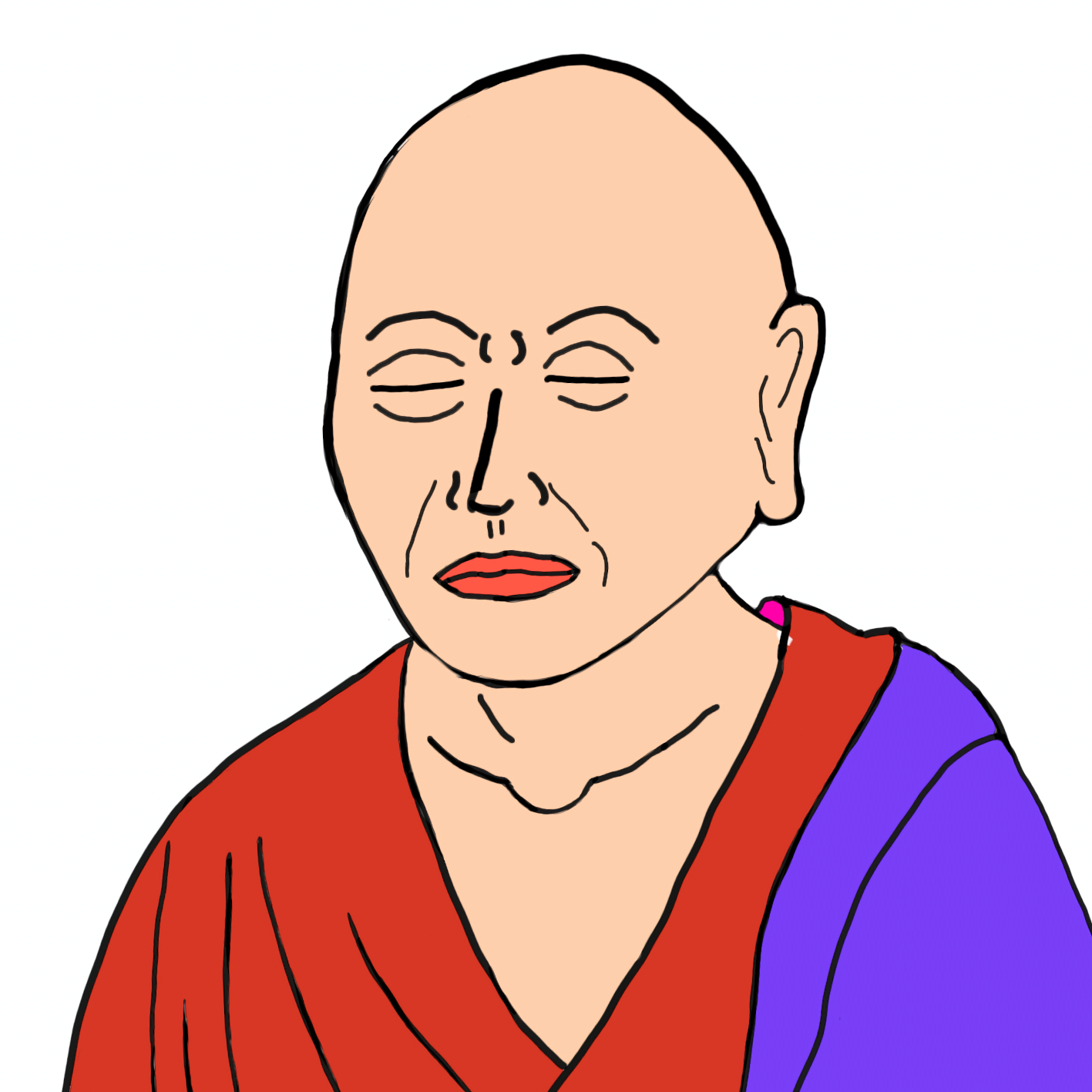
「くだらな観音菩薩」 第6回
鑑真和上
~そう、諦めちゃあいけないんだ

林家 きく麿
2025/10/16
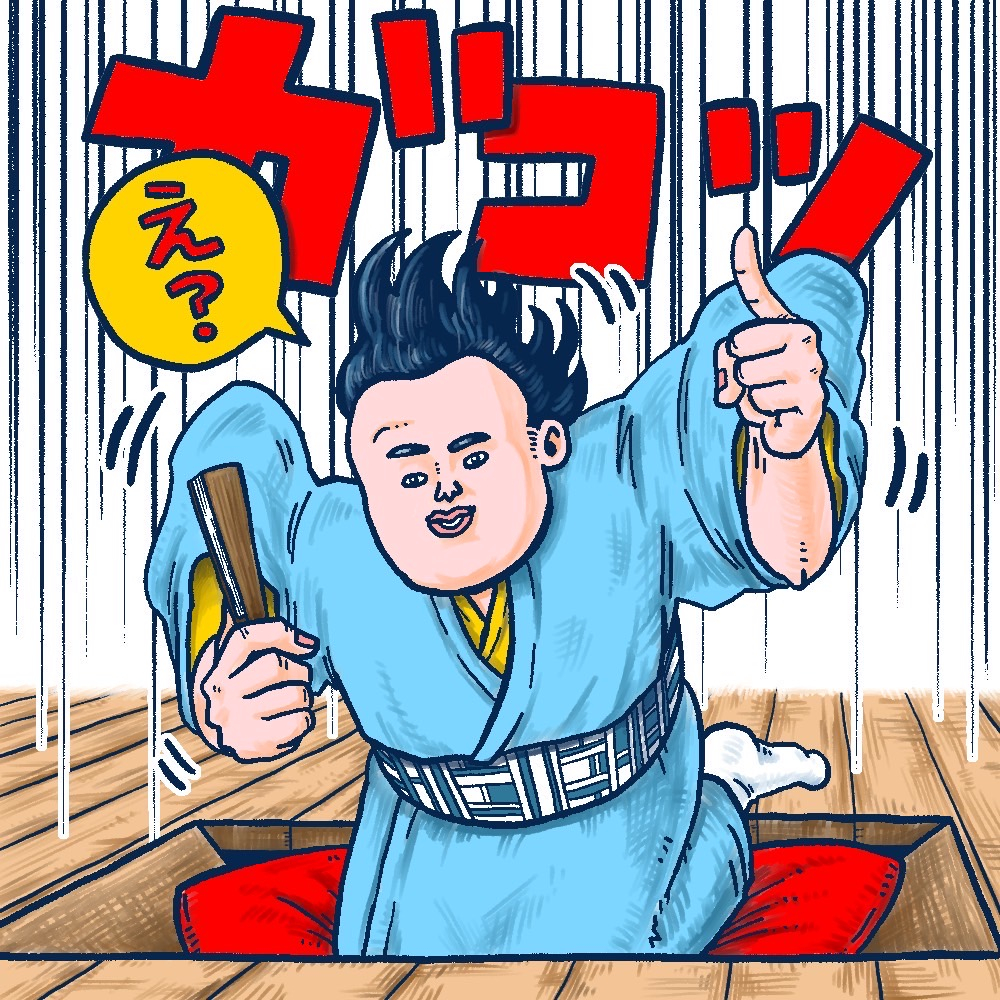
「令和らくご改造計画」
第一話 「危機感をあなたに」
~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/08/12

「令和らくご改造計画」
第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」
~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/09/12

「噺家渡世の余生な噺」 第6回
“施設長X”の献身
~架空の介護施設を舞台にした超短編小説

柳家 小志ん
2025/10/14

「まだ名人になりたい」 第5回
秋白し
~私は秋の名物に「発情期の鹿」を加えたい!

柳家 さん花
2025/10/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回
言霊のブーメラン
~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎
2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/27
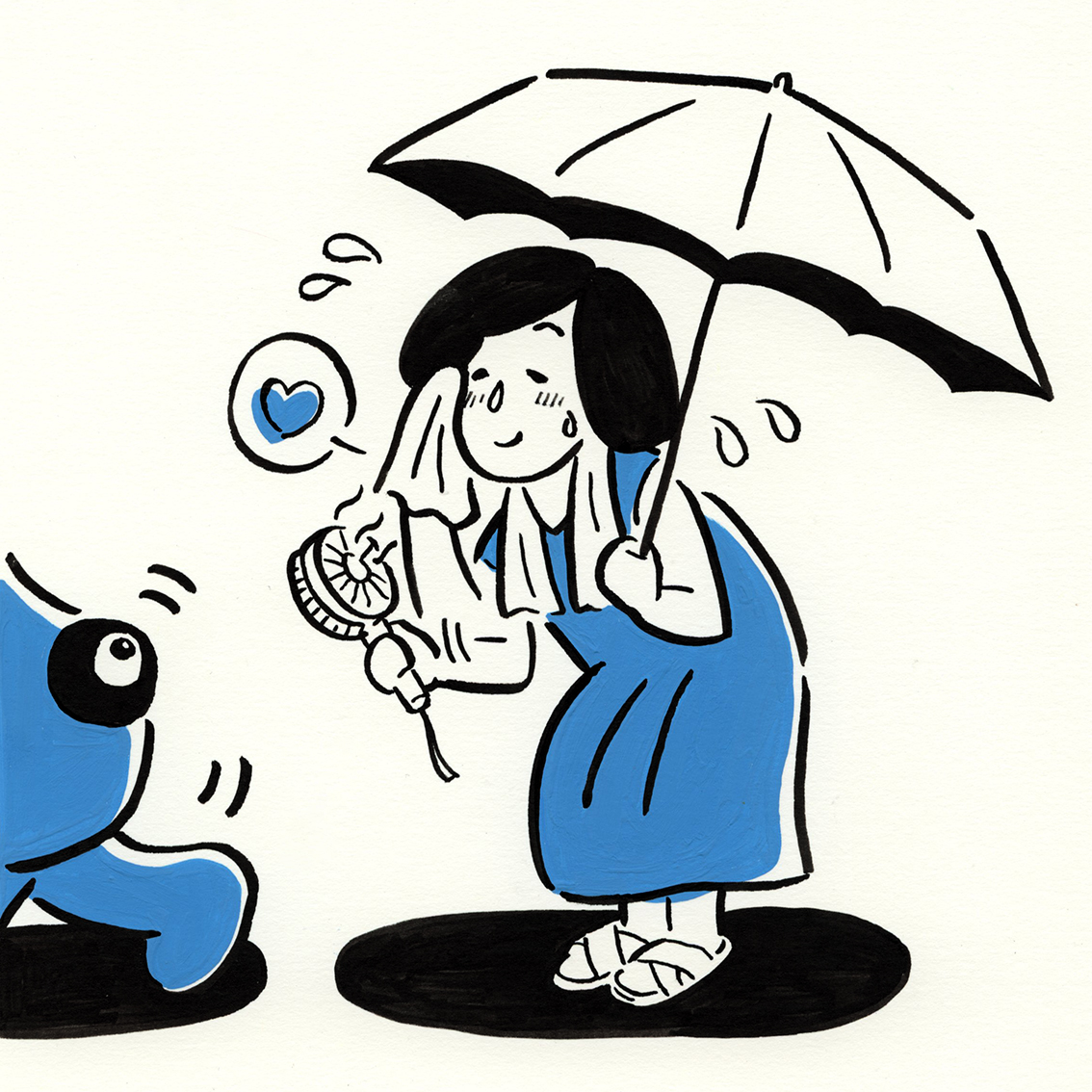
「ラルテの、てんてこ舞い」 第4回
ミャクミャクに翻弄される日々
~果てしない行列の、その先にあったもの

ラルテ
2025/10/11
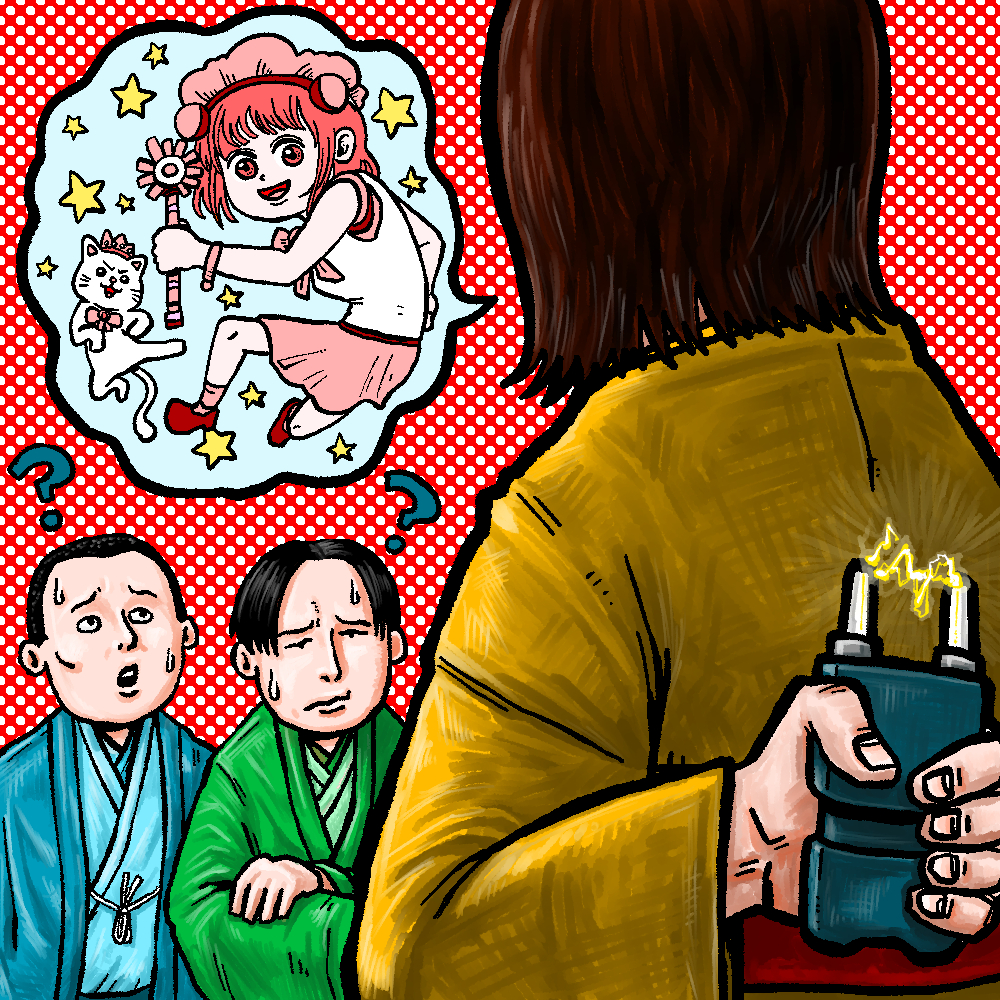
「令和らくご改造計画」
第三話 「内輪ノリ」
~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/10/12

「まだ名人になりたい」 第5回
秋白し
~私は秋の名物に「発情期の鹿」を加えたい!

柳家 さん花
2025/10/13

月刊「シン・道楽亭コラム」 第6回
上方落語を聴く旅 ~服部の大阪旅行記
~動楽亭、百年長屋、猫も杓子も、ハルカス寄席、ツギハギ荘、そして天満天神繁昌亭!

シン・道楽亭
2025/10/10

「令和らくご改造計画」
第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」
~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/09/12
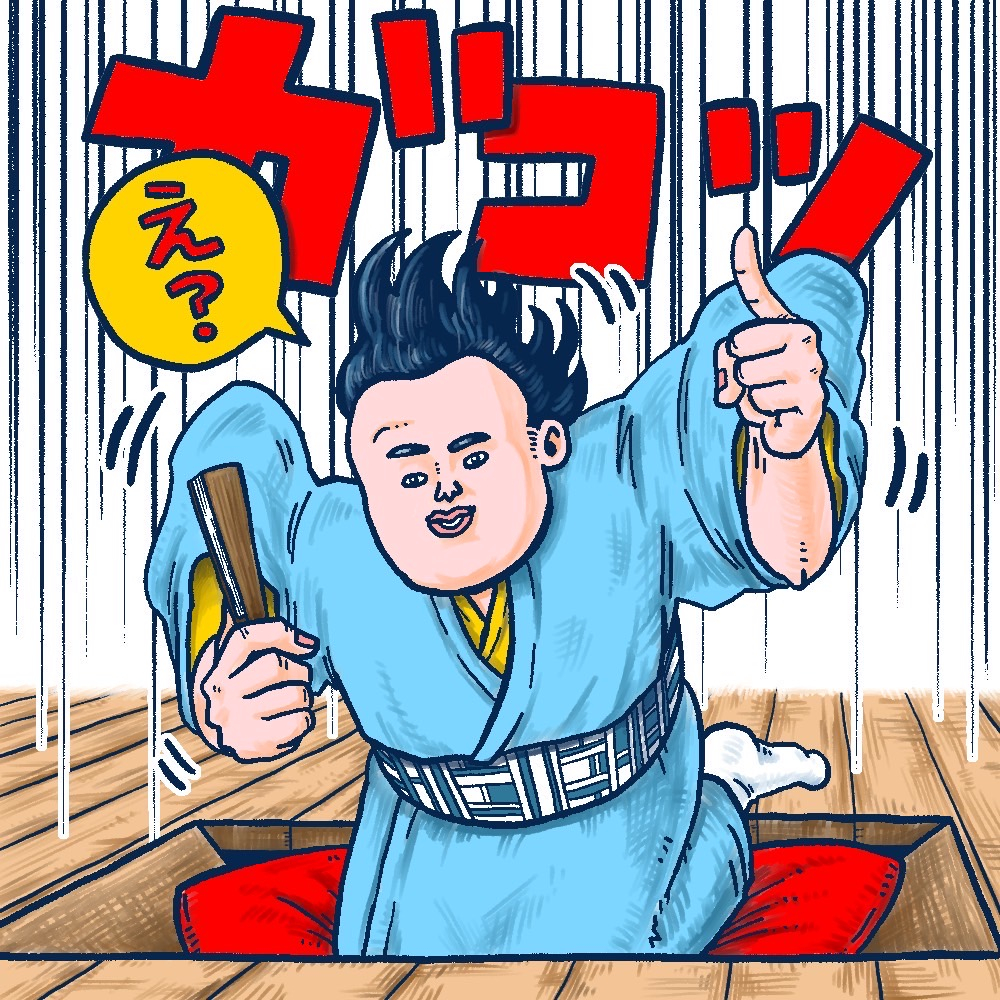
「令和らくご改造計画」
第一話 「危機感をあなたに」
~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/08/12
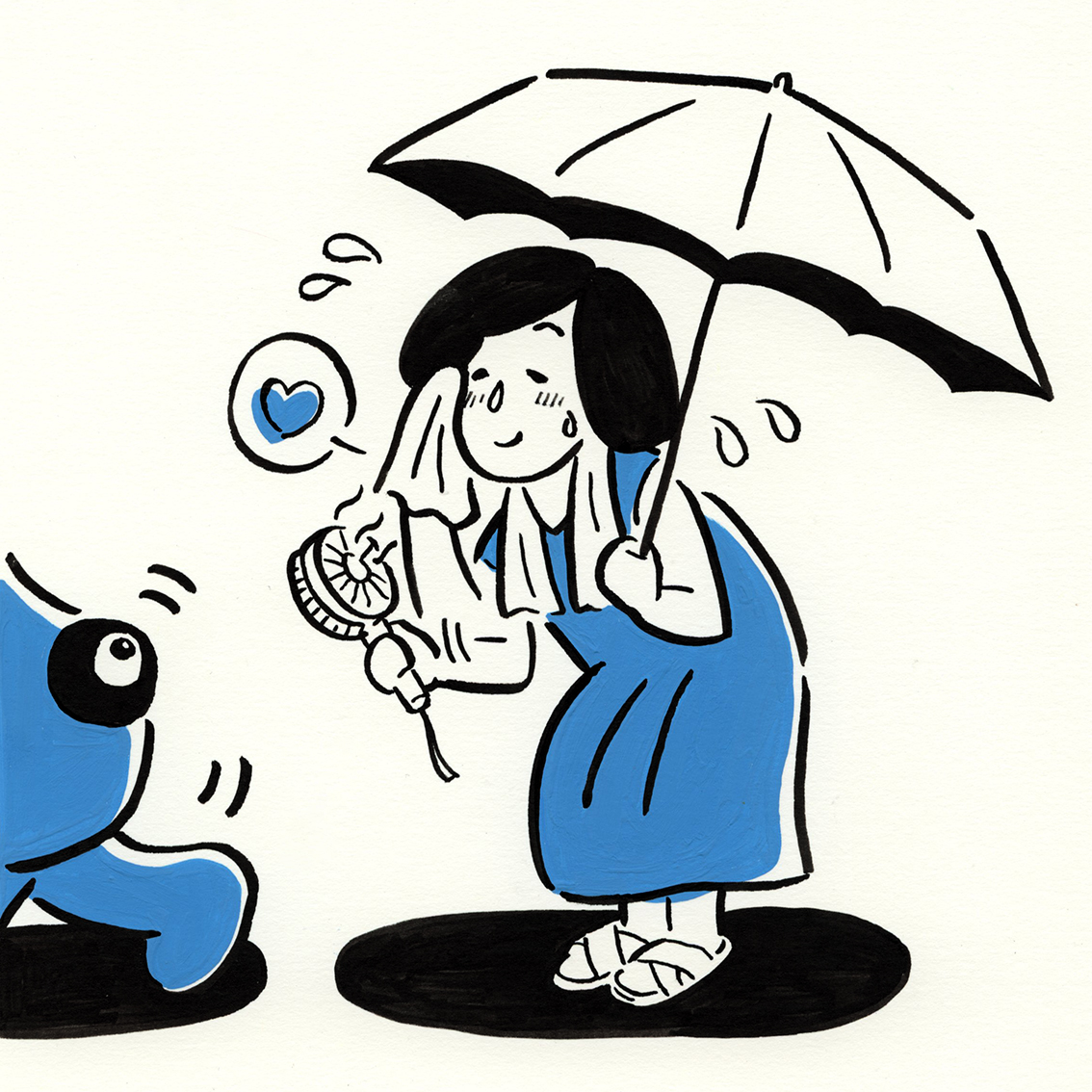
「ラルテの、てんてこ舞い」 第4回
ミャクミャクに翻弄される日々
~果てしない行列の、その先にあったもの

ラルテ
2025/10/11

「噺家渡世の余生な噺」 第6回
“施設長X”の献身
~架空の介護施設を舞台にした超短編小説

柳家 小志ん
2025/10/14

シリーズ「思い出の味」 第13回
二つの乳に育てられし
~木綿豆腐、絹ごし豆腐、豆乳、絹揚げ、おからの炊いたん!

月亭 天使
2025/10/15

「朝橘目線」 第6回
サイゼリヤ ガストジョナサン バーミヤン くら寿司あとは鳥貴族など
~この国に生まれて良かった

三遊亭 朝橘
2025/10/08

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第6回
ビール飲み干し、そしてわたしに秋が来る
~時にヒリヒリ、時に爆笑の舞台裏

東家 千春
2025/10/03
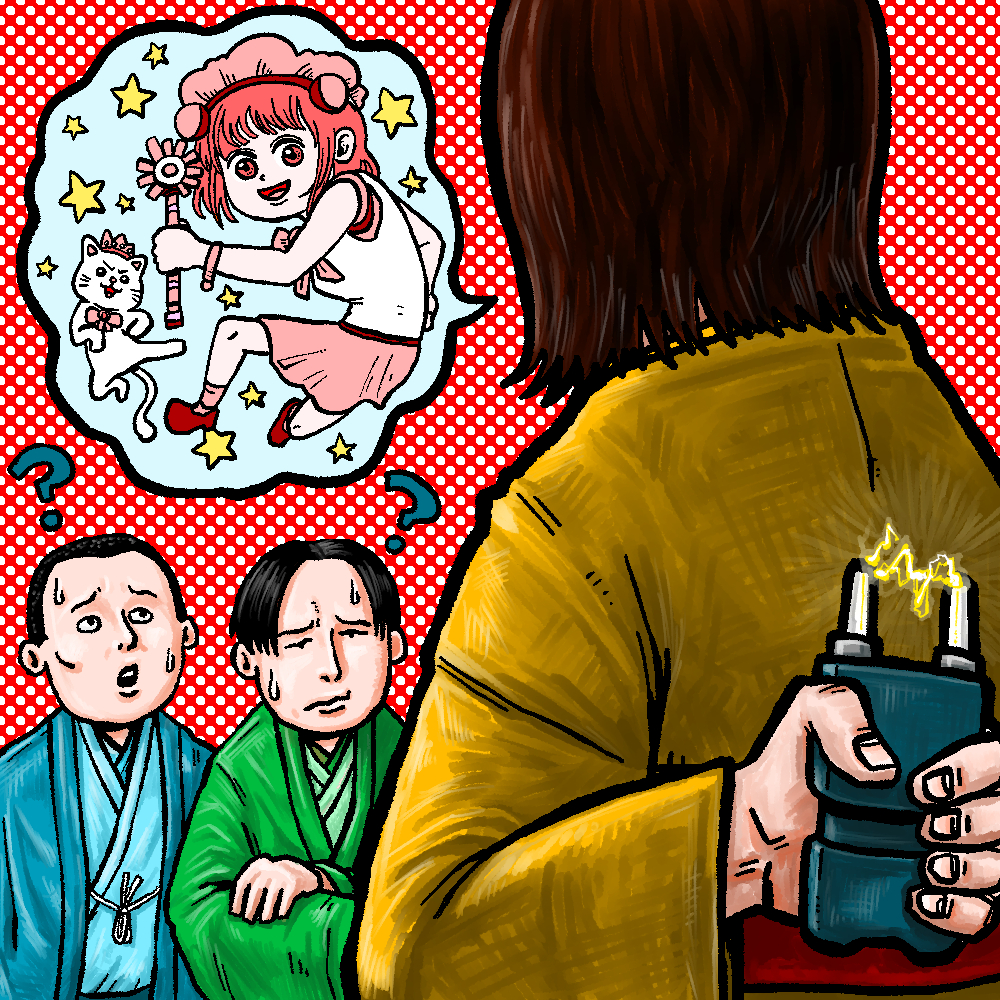
「令和らくご改造計画」
第三話 「内輪ノリ」
~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/10/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回
言霊のブーメラン
~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎
2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/27

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第6回
ビール飲み干し、そしてわたしに秋が来る
~時にヒリヒリ、時に爆笑の舞台裏

東家 千春
2025/10/03
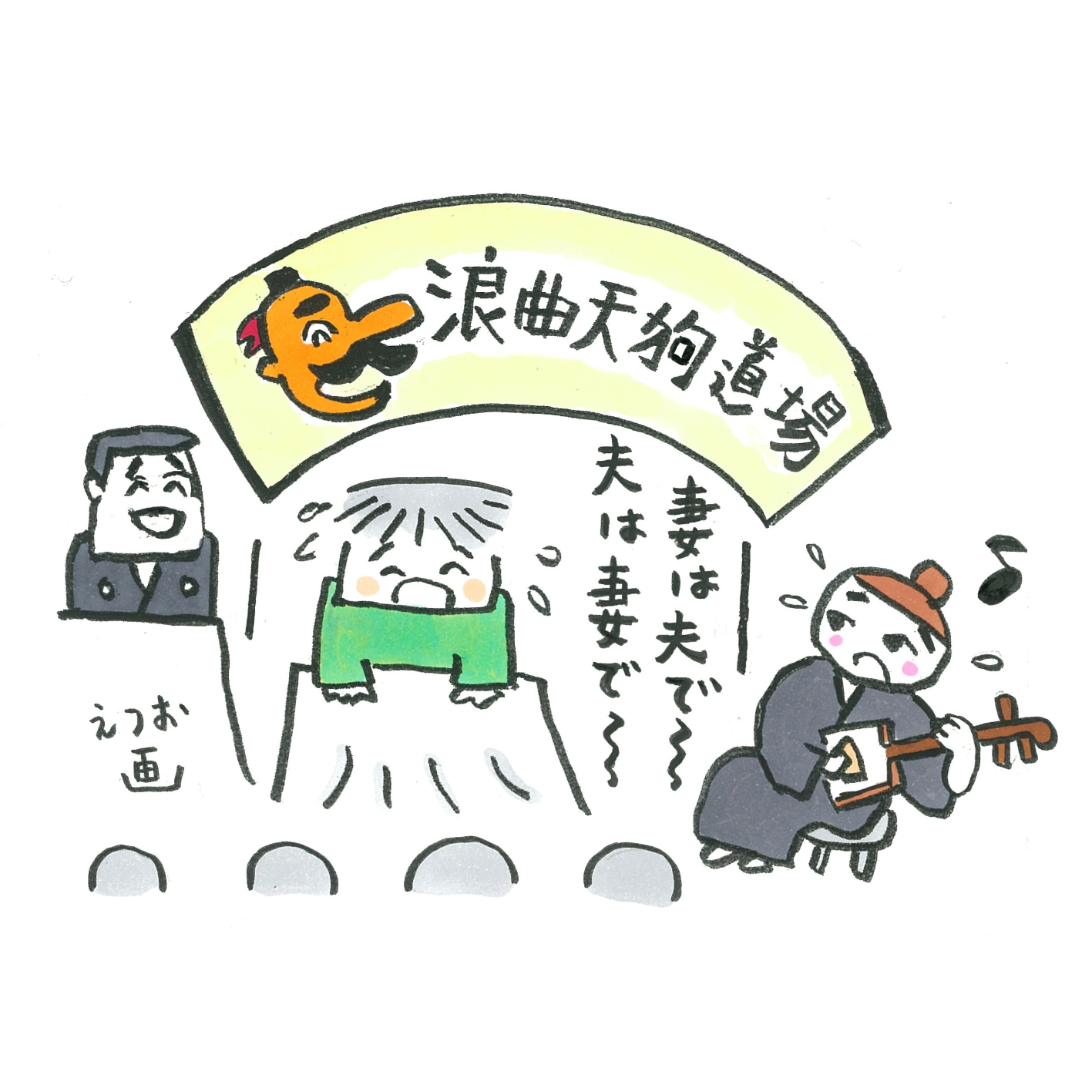
「浪曲案内 連続読み」 第5回
君は『浪曲天狗道場』を知っているか
~浪曲の「素人のど自慢番組」がラジオを席巻した時代

東家 一太郎
2025/09/15
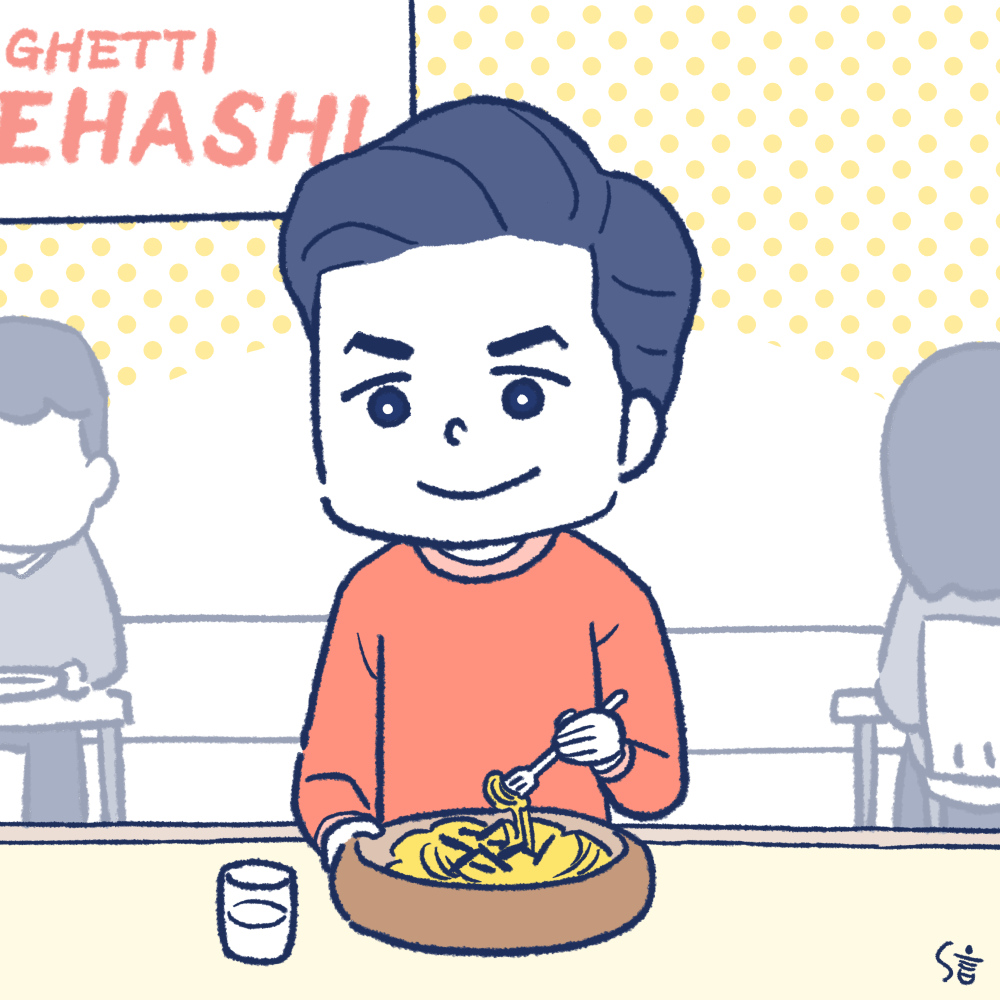
「かけはしのしゅんのはなし」 第4回
「カケハシ」に行ってきた! ~名前にまつわる小さな冒険
~新宿の絶品スパゲッティ

春風亭 かけ橋
2025/09/18
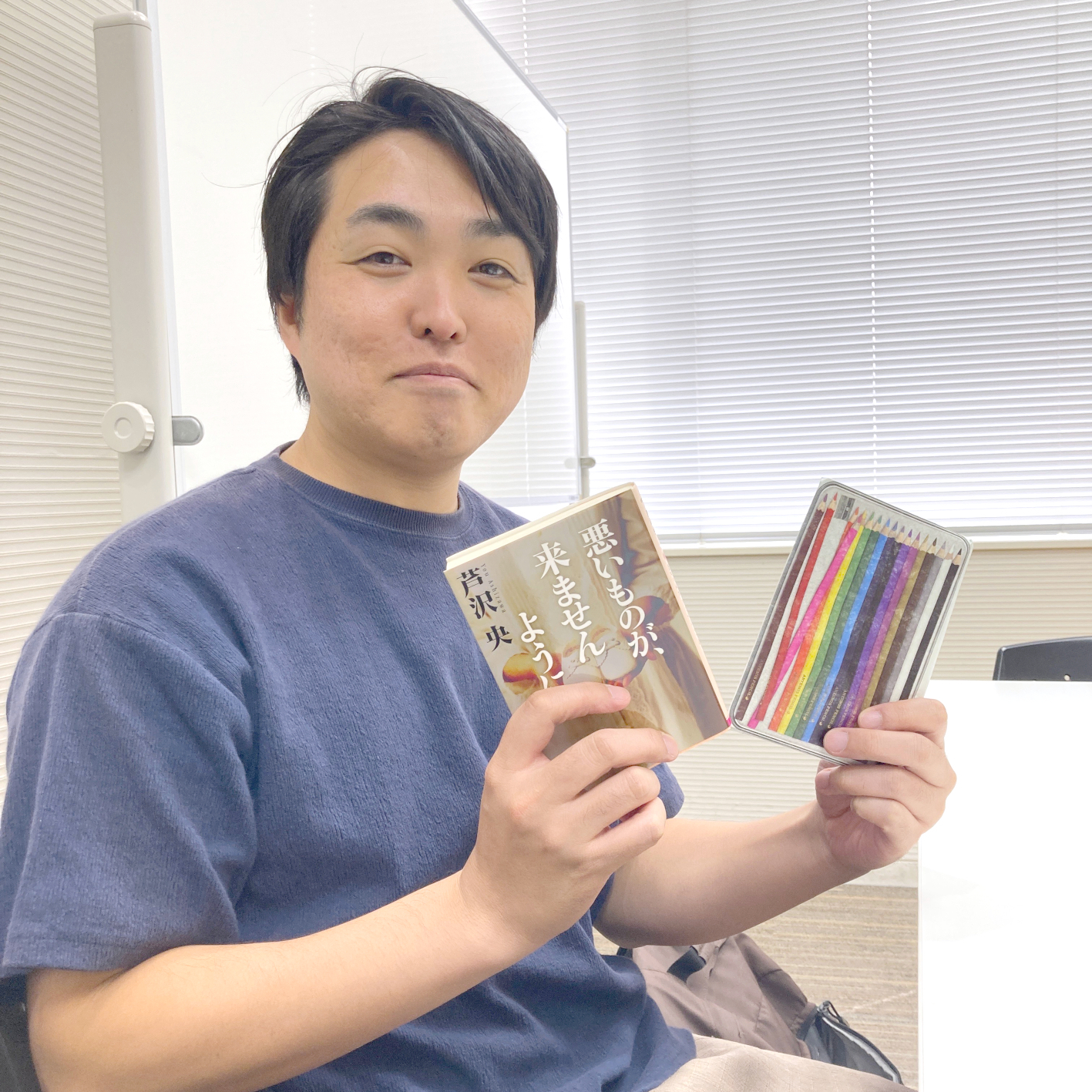
「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回
〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)
~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光
2025/09/30

「エッセイ的な何か」 第4回
9/3は、睡眠の日 →電車で寝過ごしてしまった男の恥辱
~ジーンズ一枚、上半身裸のまま楽屋入り!?

三笑亭 夢丸
2025/09/23

「マクラになるかも知れない話」 第二回
栗と私
~栗から考える人生の機微

三遊亭 萬都
2025/09/24

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第12回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(中編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/28
編集部のオススメ

「伯知の日本酒漫遊記 ~酒は“釈”薬の長」 第3回
三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉
~幕末ロマンと伏見の名酒

松林 伯知
2025/10/01

「マクラになるかも知れない話」 第一回
夏の日の少年
~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都
2025/08/24

シリーズ「思い出の味」 第11回
食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶
~焼肉は落語

桂 笑金
2025/08/17
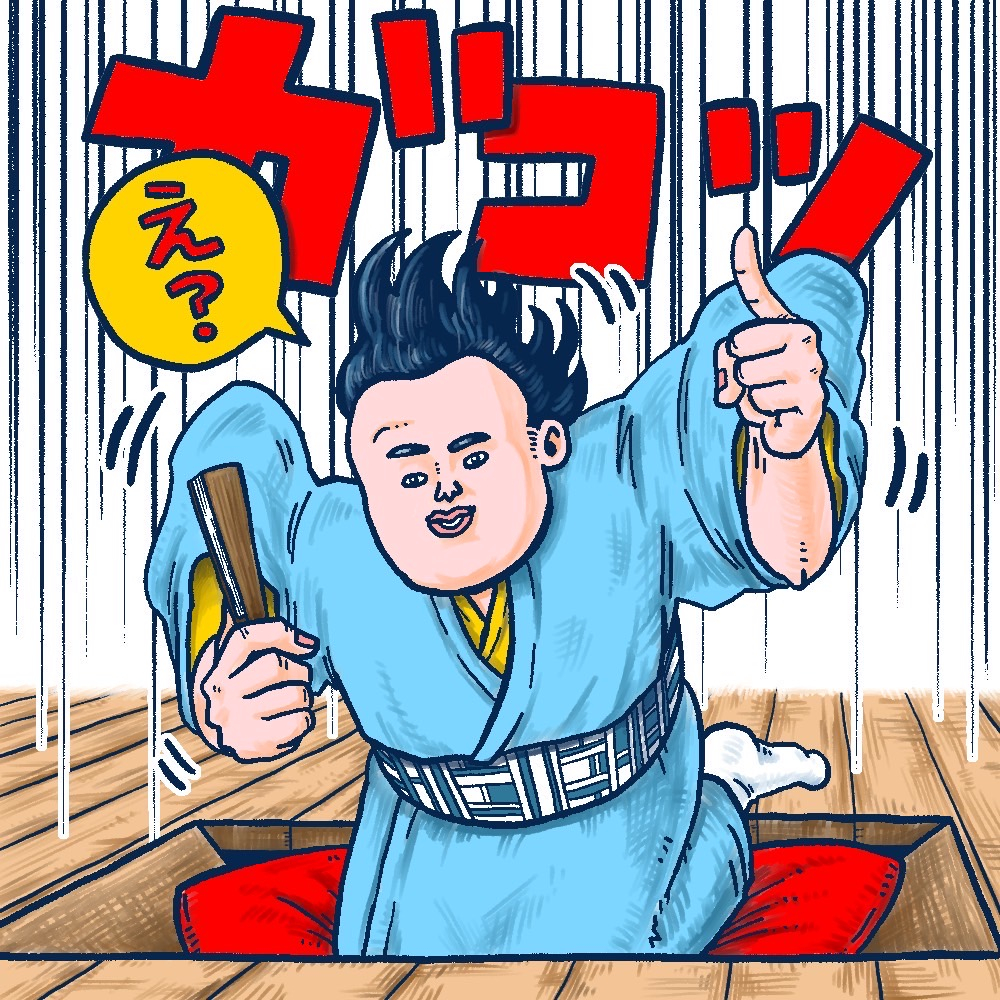
「令和らくご改造計画」
第一話 「危機感をあなたに」
~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/08/12

「二藍の文箱」 第3回
前座見習に師匠見習
~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司
2025/08/02

「くだらな観音菩薩」 第2回
阿修羅
~私は良い人なので、お気軽に話しかけてくださいね!

林家 きく麿
2025/06/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第2回
席亭への道 ~服部、落語に沼る人生
~還暦過ぎからが人生

シン・道楽亭
2025/06/10

