こしらGPT師匠に、「落語の展開・構成」を聞いてみた
「教えて! こしらGPT師匠」 第2回
- 落語

立川こしらGPT
2025/08/09
山場はこう作る! 本編の展開術
――本編(噺)の展開・構成についても教えてください。
よっしゃ、じゃあ今度は「本編の展開・構成」にググッと踏み込んでいきましょうか。
マクラはもう済んだ。ここからがいよいよ本ネタ、つまり落語の本編。これはね、ちゃんとした骨組みがあるんですよ。演目によって差はあるけど、だいたい共通してる流れがある。ここ、しっかり押さえると、落語を聴くのが100倍面白くなるし、自分で作ることだってできるようになる!
多くの落語の本編は、こんな風に展開していくよ。
① 導入(起)
まずは世界観と登場人物を紹介するところ。
・舞台はどこか(江戸? 町内? 山奥?)
・誰が出てくるか(熊さん、八っつぁん、ご隠居さん、旦那、与太郎)
・今どんな状況か(ケンカした? 借金した? ヒマしてる?)
ここで客に「この話はこういう世界観なんだな?」とすんなり入ってもらう。言い換えると、地図を渡して「この道を一緒に歩きますよ」と知らせる部分。
② 発展(承)
事が起こる。何かがズレる。話が広がっていく。
・勘違いが始まる
・登場人物がどんどん増えていく
・うっかり約束しちゃう
・「なんでそうなる!?」みたいな行動が出てくる
例えば、『時そば』なら、そばを食べながら勘定をごまかす男が登場。『目黒のさんま』なら、殿様が初めて庶民の味を知って感動。この部分が面白くなると、サゲなんてなくても成立するぐらい盛り上がるんだ。
③ 転換・山場(転)
物語のクライマックス。ズレが大きくなり、笑いも加速。
・勘違いがピークに
・トンデモ展開(ありえない行動)
・間(ま)を使って笑わせる
・聴き手が「どうなるんだ?」と身を乗り出す
ここでネタによってはテンポを落としたり、逆に畳みかけたりと、演者のセンスが光る!
④ サゲへ向けた落とし(結)
いよいよ終わり。オチに向けて「流れを整える」。
・一言で全部をひっくり返す伏線回収
・勘違いが明らかになる
・とぼけた一言でバッサリ切る
そして…
⑤サゲ(落ち)
決まったー!!という瞬間。演目によっては、客席が笑いでブワッとなったり、逆に「ふっ」と静かに笑うこともある。この余韻も落語の醍醐味。
また、演目によっては、以下のような特徴もあるよ。
Ⓐ二段構成
「前半に一つ話、後半で同じパターンの別バージョン」みたいな。例えば、『時そば』『芝浜』。
Ⓑ反復構造
同じパターンのギャグを繰り返して積み重ねる。例えば、『寿限無』『饅頭こわい』。
Ⓒオチ先行型
オチの一言ありきで全部が組まれる。例えば、『出来心』『長短』。
さ、これを知ってから『時そば』とか『死神』とか聴き直すとね、「あっ今、承に入った!」「おお、そこが転か!?」って実況しながら楽しめるよ(笑)
いま読まれています!

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「お恐れながら申し上げます」 第5回
新年のご挨拶
~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太
2026/01/11

月刊「浪曲つれづれ」 第9回
2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)
~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋
2026/01/09

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回
昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!
~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭
2026/01/10

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

「令和らくご改造計画」
第一話 「危機感をあなたに」
~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/08/12

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回
〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)
~「見えない序列」の正体

杉江 松恋
2025/12/24

「座布団の片隅から」 第9回
大河
~『べらぼう』が残していった、噺家への置き土産

三遊亭 好二郎
2026/01/07

「令和らくご改造計画」
第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」
~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ
2025/09/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第9回
不動坊、抜け雀、七段目
~「てっぺんから落ちたな」「いいえ、七段目」

林家 はな平
2026/01/06

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回
昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!
~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭
2026/01/10

「お恐れながら申し上げます」 第5回
新年のご挨拶
~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太
2026/01/11

月刊「浪曲つれづれ」 第9回
2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)
~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋
2026/01/09

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「座布団の片隅から」 第9回
大河
~『べらぼう』が残していった、噺家への置き土産

三遊亭 好二郎
2026/01/07

「二藍の文箱」 第8回
麹町の雑煮、目白のおせち
~噺家の正月風景

三遊亭 司
2026/01/02
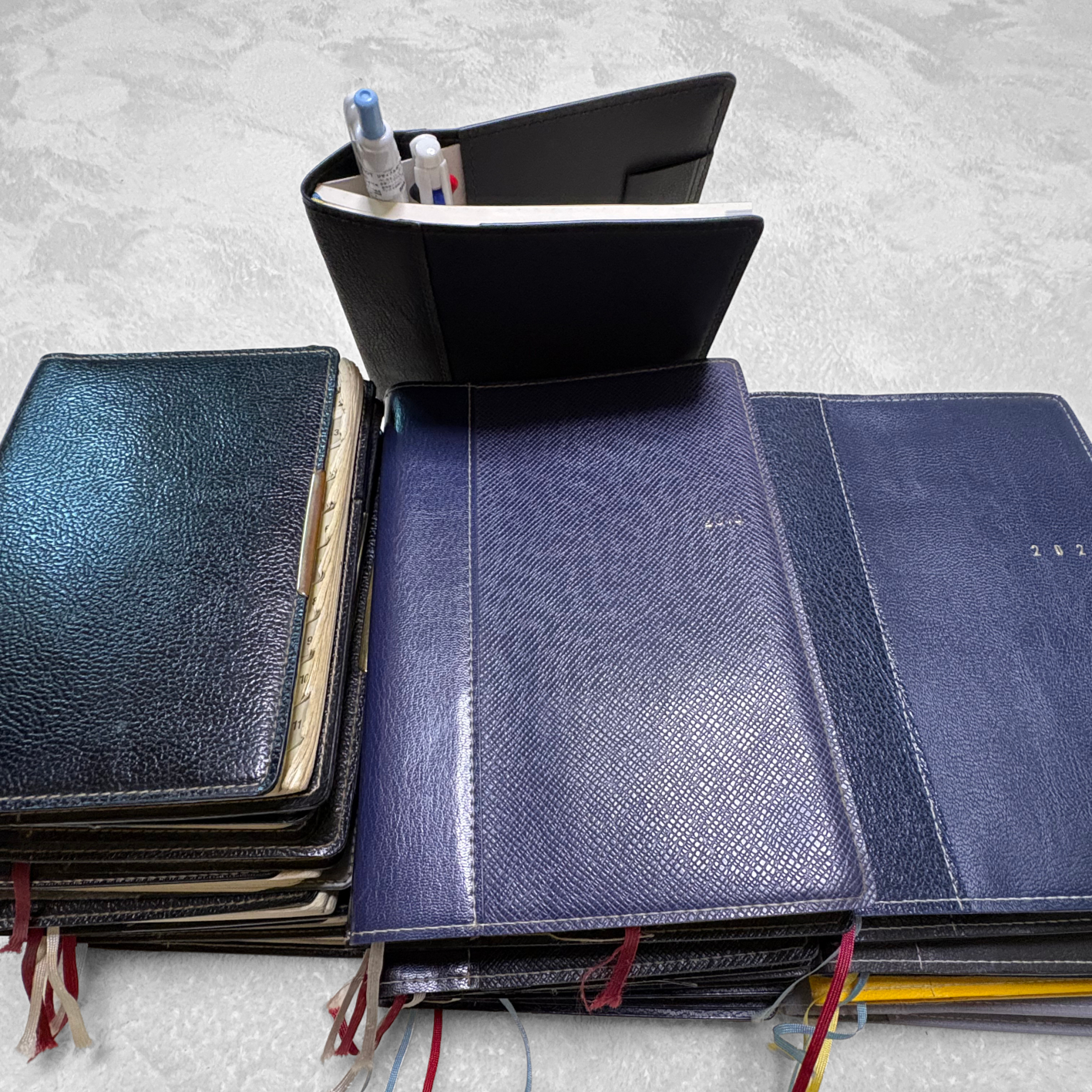
「朝橘目線」 第9回
来る春や 妻啼き我の 目は涙
~年男について調べてはいけない理由(妻が正解を知っている)

三遊亭 朝橘
2026/01/08

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第9回
不動坊、抜け雀、七段目
~「てっぺんから落ちたな」「いいえ、七段目」

林家 はな平
2026/01/06

古今亭佑輔とメタバースの世界 第7回
VR落語を始めて1年経った今
~余白を埋めるVR、余白に委ねる寄席

古今亭 佑輔
2026/01/05

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回
〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)
~「見えない序列」の正体

杉江 松恋
2025/12/24

「講談最前線」 第12回
2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2025/12/15

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/29

「二藍の文箱」 第8回
麹町の雑煮、目白のおせち
~噺家の正月風景

三遊亭 司
2026/01/02

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第22回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(中編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/30

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第23回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(後編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/31

「講談最前線」 第13回
2025年12月の最前線【後編】 (2025年の講談界ニュース)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2025/12/17

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回
〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)
~「見えない序列」の正体

杉江 松恋
2025/12/24

「浪曲案内 連続読み」 第8回
浪曲ほど素敵な商売はない
~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎
2025/12/22

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回
昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!
~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭
2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回
落語家の夢
~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎
2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第15回
水茄子とジンジャーエール
~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三
2025/11/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回
上方落語大会議「なんぼでなんぼ」
~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎
2025/10/24

「令和らくご改造計画」
第四話 「初心者よ永遠なれ」
~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回
シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト
~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭
2025/11/13

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回
ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋
~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春
2025/11/03

「マクラになるかも知れない話」 第三回
となりは鼻うがいをする人ぞ
~ねぇママ、パパは何をしているの?

三遊亭 萬都
2025/10/22
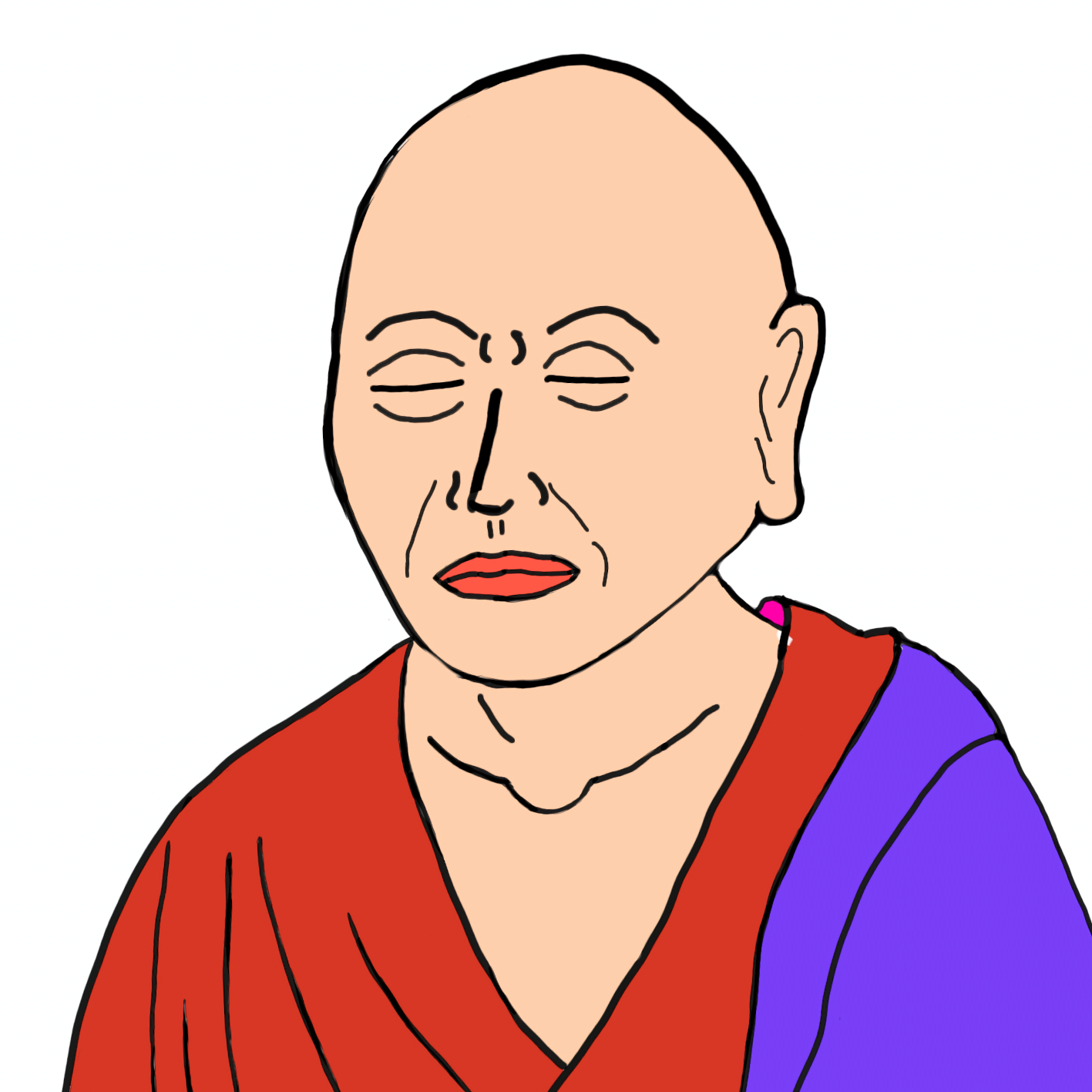
「くだらな観音菩薩」 第6回
鑑真和上
~そう、諦めちゃあいけないんだ

林家 きく麿
2025/10/16
編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回
浪曲ほど素敵な商売はない
~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎
2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回
弥勒菩薩(半跏思惟像)
~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿
2025/12/16

「講談最前線」 第12回
2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2025/12/15

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回
にらみ返し、大工調べ、短命
~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平
2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回
今日は宇宙一の美が誕生した日
~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春
2025/12/03


