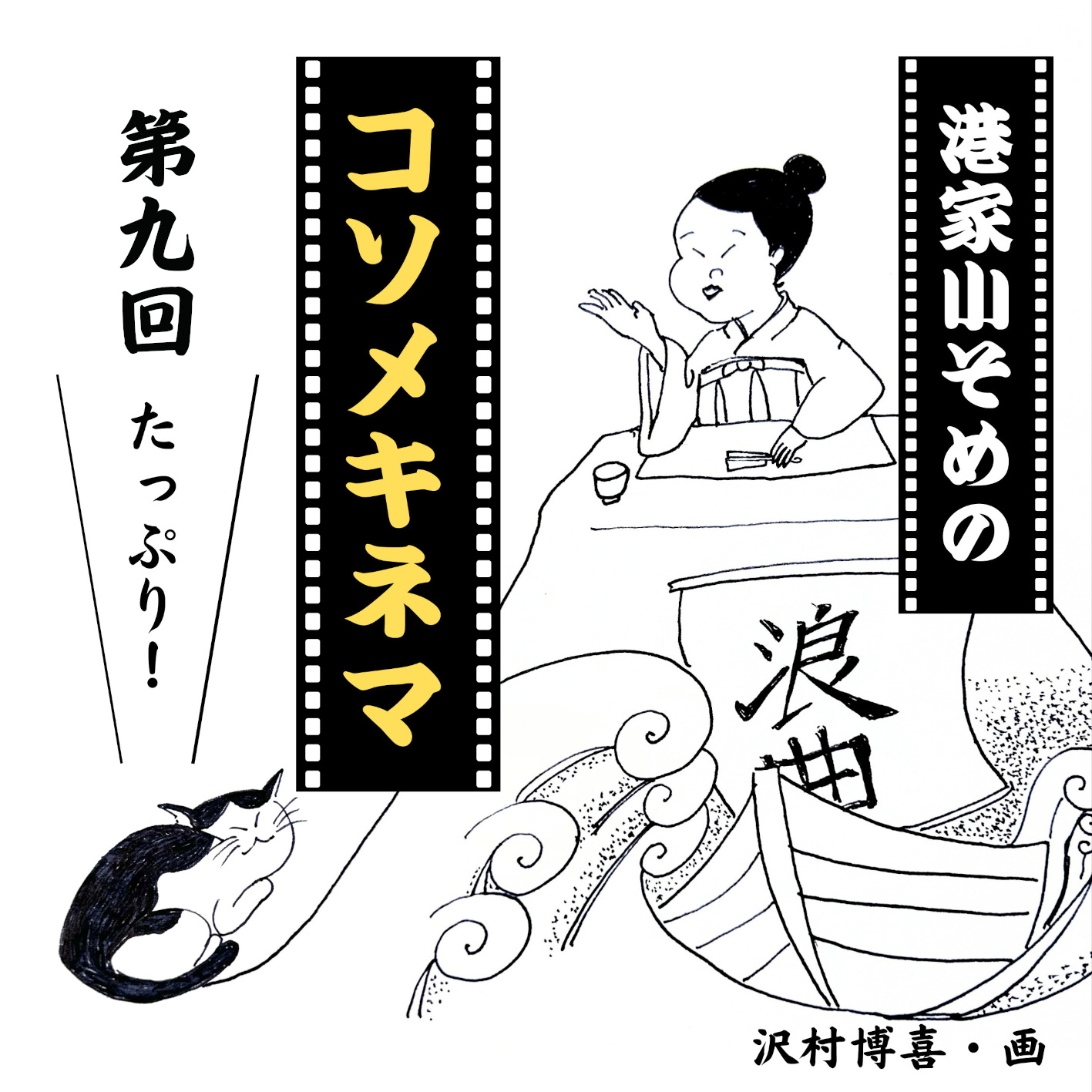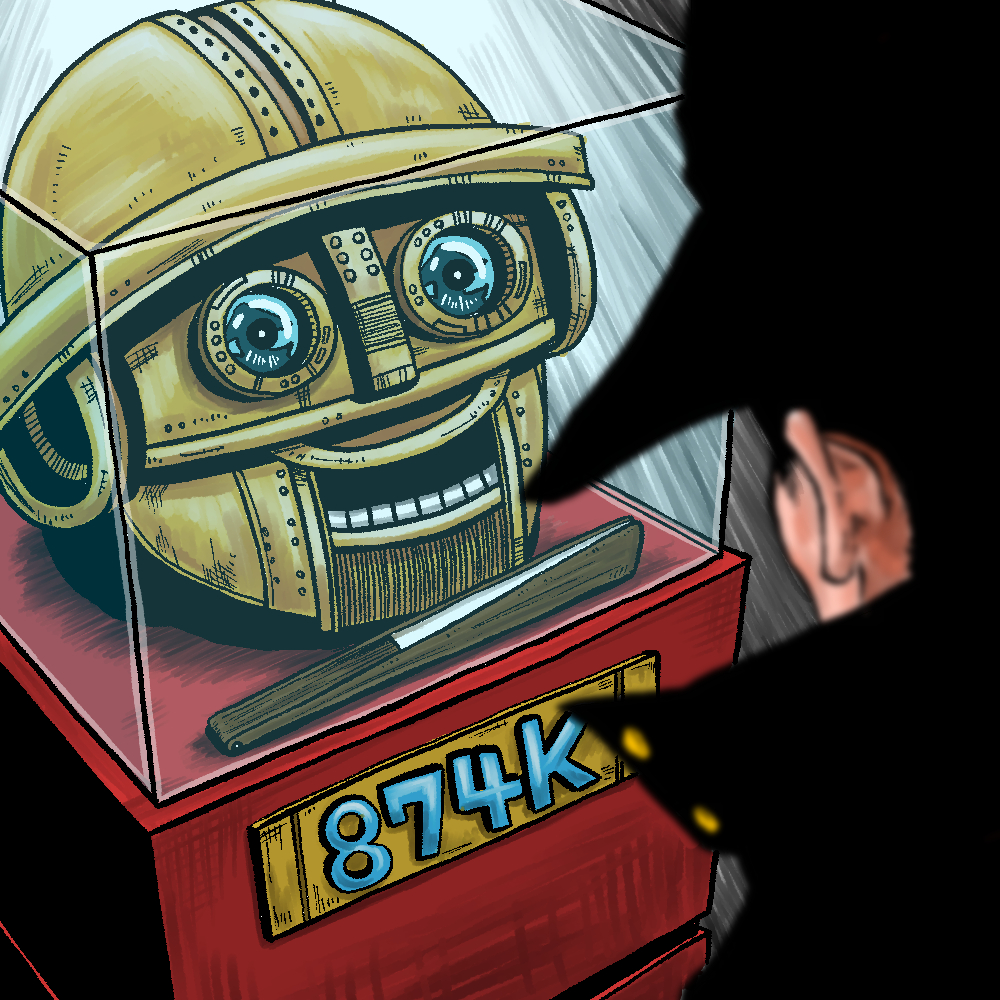NEW
〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】
掲載記事300本記念
- 落語

2023年5月20日、有楽町朝日ホールにて(撮影・武藤奈緒美)
名人文楽や圓生らが芸を磨き、寄席の楽屋でにらみを利かせていた1960年代後半。柳家さん喬師匠は、柳家小稲として前座修業で気働きをしつつ、師匠・五代目柳家小さんの呼吸、視座を身体の中に染み込ませようとしていました。
「(コンプライアンスは)これっぽっちもない」という時代。掲載記事300本記念のインタビューの2回目は、そのあたりのお話からうかがっていきます。(前編/中編/後編のうちの中編)
前編はこちら
取材:文=渡邉 寧久(演芸評論家・エンタメライター)
撮影:話楽生Web編集部
名人の着物を着せた誇り
さん喬師匠は苦笑気味に、時の移ろいを語る。
「そんな古い話をしていると思わないんだけど、聞いている方、後輩なんかが『えー、そんなことがあったんですか』って。『いや、ついこないだなんだよ』って感じなんですけどね。
若い人に『こういうことがあったんだよ』と話をすると、『勉強になりました!』って。勉強になるような話はしてないんだけどな……と思うんです(笑)」
さん喬師匠が入門した1967年(昭和42年)当時の落語協会会長は、六代目三遊亭圓生師匠。志ん生師匠、文楽師匠、八代目林家正蔵師匠らが協会幹部としてかじ取りをしていた。
当時のコンプライアイスについて尋ねると、
「ないない、これっぽっちもない」
さん喬師匠が即座に首を横に振る。その10年ほど前まで、浅草では吉原が廓として営業を続けていた(昭和33年、1958年3月31日に廃止)。江戸時代が落語の世界と地続きだった。
「文楽師匠が楽屋にお入りになると、シーン……ですよ。凍てつくような空気感、緊張感。しゃべらないってわけじゃないんですよ。
先輩方が『こんなバカなことをやっちゃった~』としくじり話をすると、文楽師匠が『そうかい~』なんて笑ってくださる。話した方も『あぁ、文楽師匠が聞いてくれた』って大喜び。そんな時代ですもんね」
その一方で……
「今なんて、前座といわゆる私らの世代がため口でしゃべってますからね(笑)。楽屋の緊張感が違うことを痛感します」

名人文楽から見れば、さん喬師匠は孫弟子にあたる。18歳の前座・小稲と最晩年の名人は、短い時間ながら、楽屋で同じ時を過ごし、空間を共有することができた。
「文楽師匠に名前を憶えていただいて、うれしかったですね。『小稲~』って呼んでくださるから、『はい!』って。お茶をお出ししたり、袴の着せつけのお手伝いをさせていただいたりしました。
自分の噺家人生の中で、『あの文楽の着物を着せつけた』っていうのは、ある意味誇りというか、思い出してもうれしい時間ですね」
一時代を築いた名人たち、スター落語家が晩年を迎え、師匠である五代目小さんらの若手が自然に台頭する世代交代の中で、さん喬師匠がぼんやりと目指した落語家像は「影の落語家」だった。
「私が噺家になった時は、どちらかというと落語のことをよく知らないで入門しましたが、師匠方や先輩の噺を楽屋で聞くうちに、『落語って、なんてすてきな芸能なんだろう』って思うようになりました。
いろいろと触発されることはありましたけど、そんな中で自分が思ったのは、もし自分が将来、噺家として食って行けたならば、10人とすれ違って3人が『あれ、柳家さん喬じゃない?』って言ってくれるような噺家になりたいなと思ったんです」