流れもの日記 (前編)
鈴々舎馬風一門 入門物語 第5回
- 落語

柳家 あお馬
2025/05/17

前座の頃、柳家権之助兄に撮ってもらった一枚
キリギリスの生活
2011年、秋の夜。
大学四年の僕は着物を着て、大学の落研部員として横浜野毛にある、とあるバーで落語をやっていた。落語会というようないわゆる寄席ではない。バーのイベントの一種で漫才、唄、漫談。何でもありのライブだ。
僕は、そこに落語枠としてイッチョ前にもYouTubeで覚えた噺を目の前のお客さんに向かって口角泡を飛ばしながら、必死にしゃべっていた。開口一番。前座、落語。聞こえてくるのは、お客さんの笑い声ではない。マスターが「カシャカシャ」と氷をピッグで砕く音がこだます。まるで相槌を打つかのように。
落語を一席しゃべり終える頃には、氷がミラーボールのような光沢を放ち、グラスの中に納まっていた。この氷が溶ける頃には、僕が落語をやったこともお客さんの記憶の中には残っていない。それでもいい。今日はうまくしゃべれたことよりも、正座をして一席、無事に完走できた自分を褒めようではないか。
バーなんて、そもそも高座台があるような環境ではない。この日の高座は即席のものだ。丸い小さなカウンター席の椅子に座布団を強引に敷き、ほぼ脛骨(スネ)しか接着面がない今日の現場は、落ちずに済んだだけでも良いではないか。噺の最後は、もう少しオチても良かったが……。
この場にいることが楽しくて仕方がなかった。ちなみにこの日のトリは、国籍を変えてロンドン五輪を目指していた頃の猫ひろしさんだった。国籍どころか就職先もろくに決まっていなかった僕は、自分の出番が終わると後方の席に移動してコロナビールを飲みながら、『芸能人のひとだあ』というような心境でその日のショーを楽しんでいた。
ずっとこういうような日常を送っていたいと思った。落語家になったら、こんな生活ができるのだろう。今日みたいな日を多く消費して、生きていきたいと思った。アリとキリギリスで言えば、絵に書いたようなキリギリス。でも食えるならいいじゃあないか、と思った。
いま読まれています!

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第28回
古今東西を自在に読む講釈師 松林伯知(中編①)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2026/03/13

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第27回
古今東西を自在に読む講釈師 松林伯知(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2026/03/12
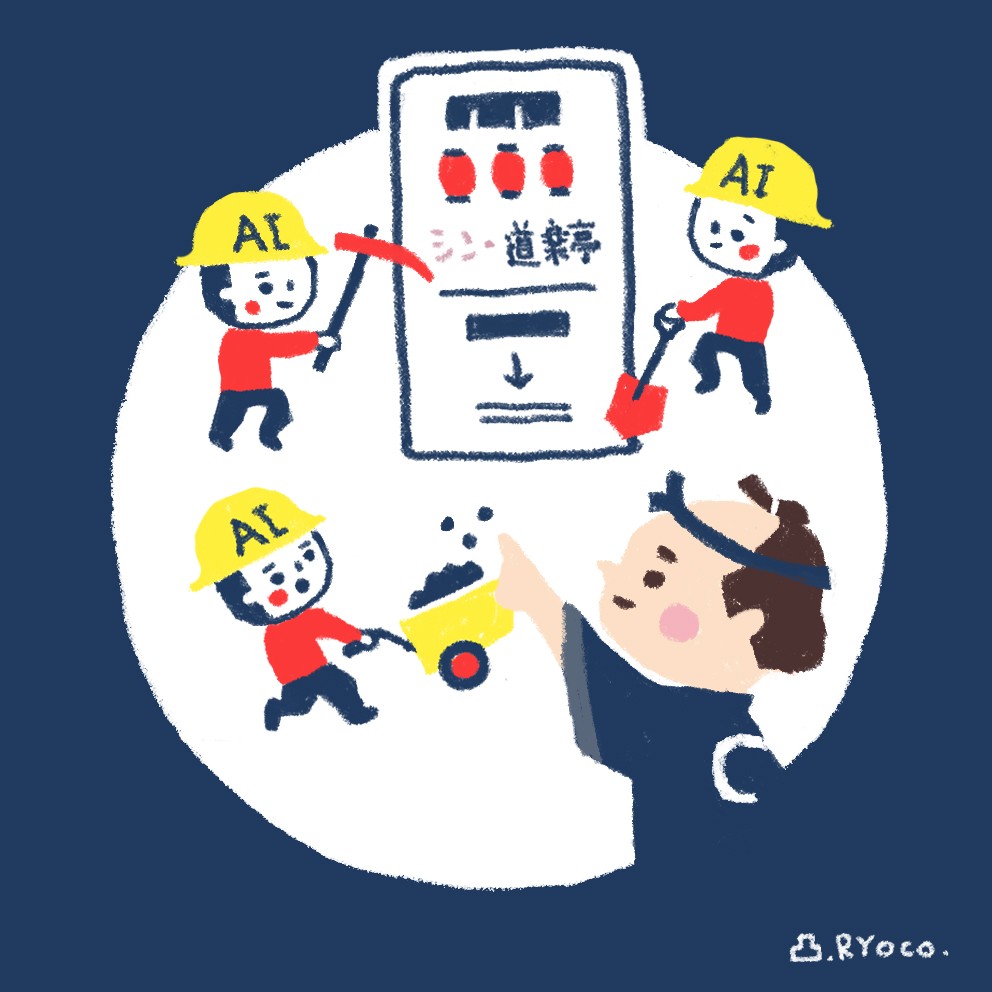
月刊「シン・道楽亭コラム」 第11回
シン・道楽亭Webサイトリニューアル! ほぼほぼAIで作ってみた話
~どんな思いで運営しているのか、どんな場所として受け入れられたいのかをお伝えしたい

シン・道楽亭
2026/03/10

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第29回
古今東西を自在に読む講釈師 松林伯知(中編②)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2026/03/14

月刊「浪曲つれづれ」 第11回
2026年3月のつれづれ(玉川太福の受賞、玉川奈々福の徹底天保水滸伝、『深夜食堂』&『陰陽師』の浪曲化)
~スターの活躍と新しい挑戦が交差する、いまの浪曲界をご紹介

杉江 松恋
2026/03/09
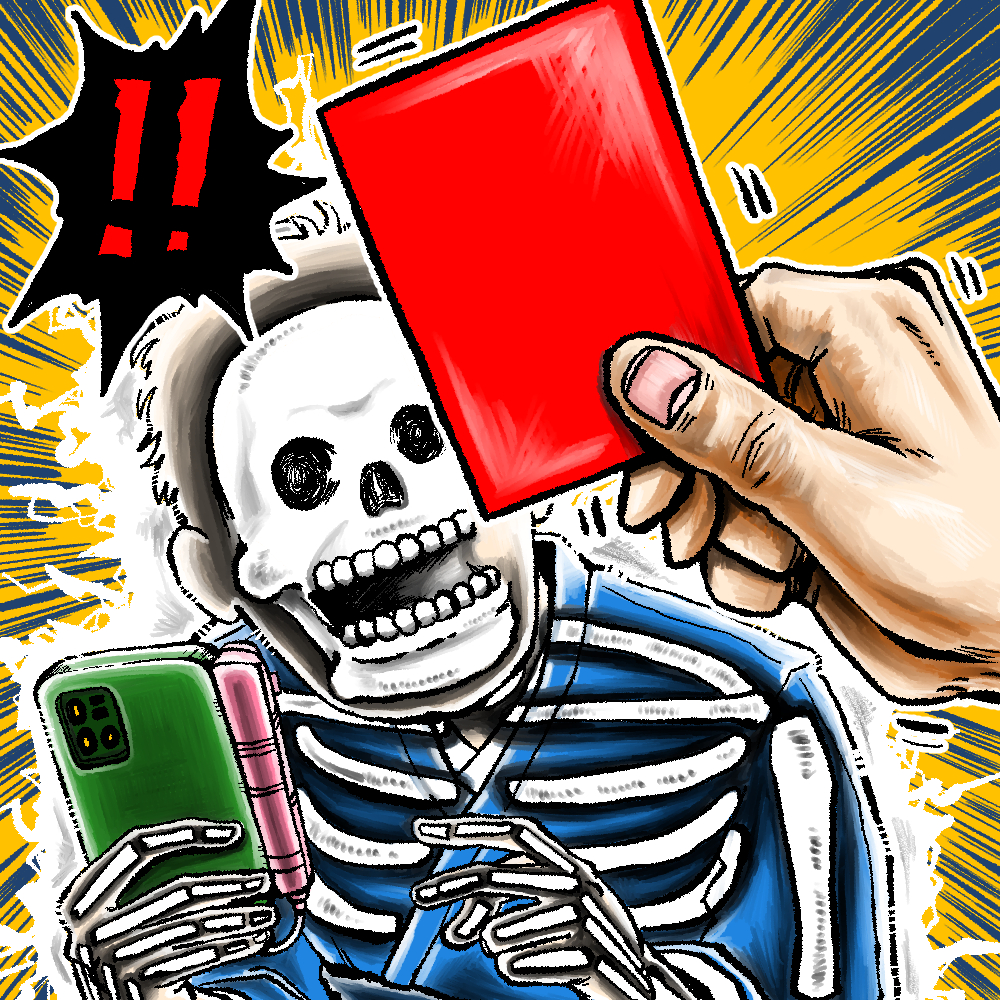
「令和らくご改造計画」
第八話 「酔っ払いにSNSを」
~芸人のSNSは、なぜ自由すぎるのか?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/03/12

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第11回
病んでる間に千春の春到来
~体調不良で“声”を失っても、“笑い”は失わない宇宙一の美人浪曲師の事件簿!

東家 千春
2026/03/03

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第12回
伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/09/27
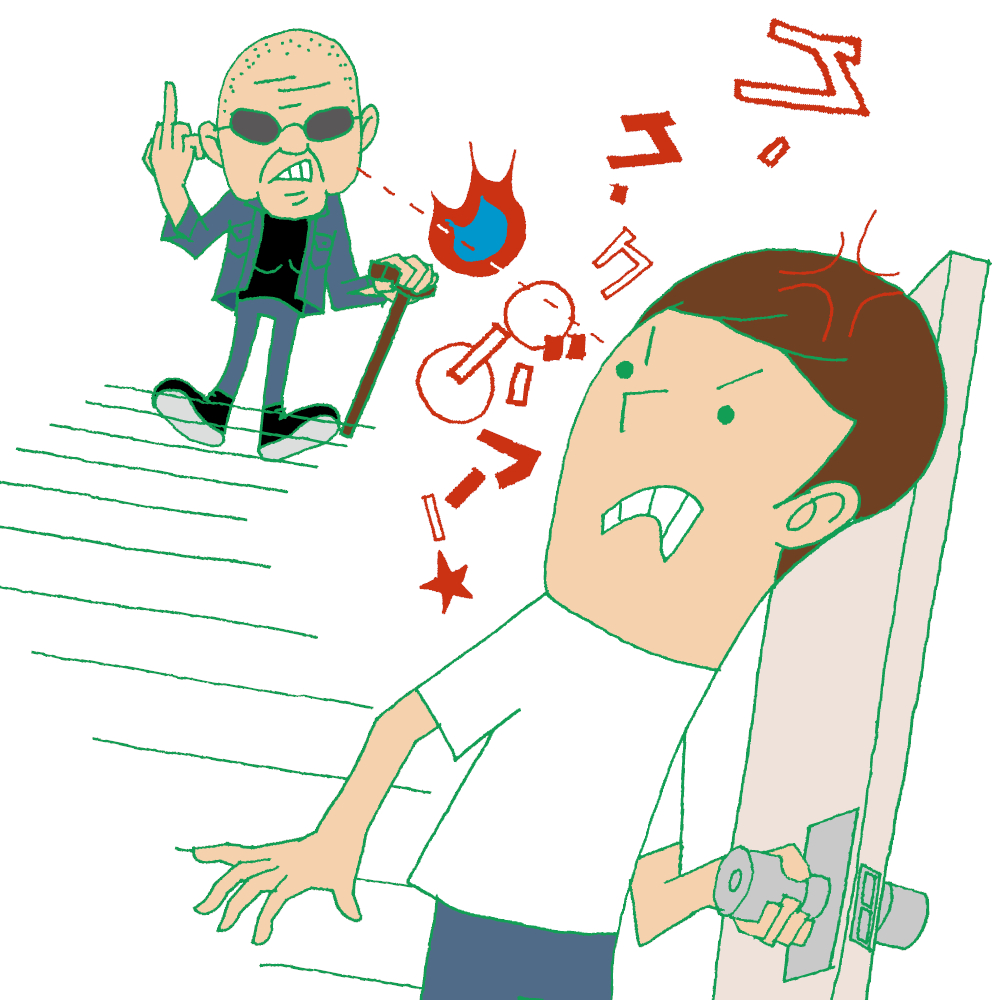
「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回
微笑みながら中指を
~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎
2026/02/25

「噺家渡世の余生な噺」 第11回
手紙 ~拝啓 四十八の君へ~
~自分に送る手紙

柳家 小志ん
2026/03/14

月刊「浪曲つれづれ」 第11回
2026年3月のつれづれ(玉川太福の受賞、玉川奈々福の徹底天保水滸伝、『深夜食堂』&『陰陽師』の浪曲化)
~スターの活躍と新しい挑戦が交差する、いまの浪曲界をご紹介

杉江 松恋
2026/03/09
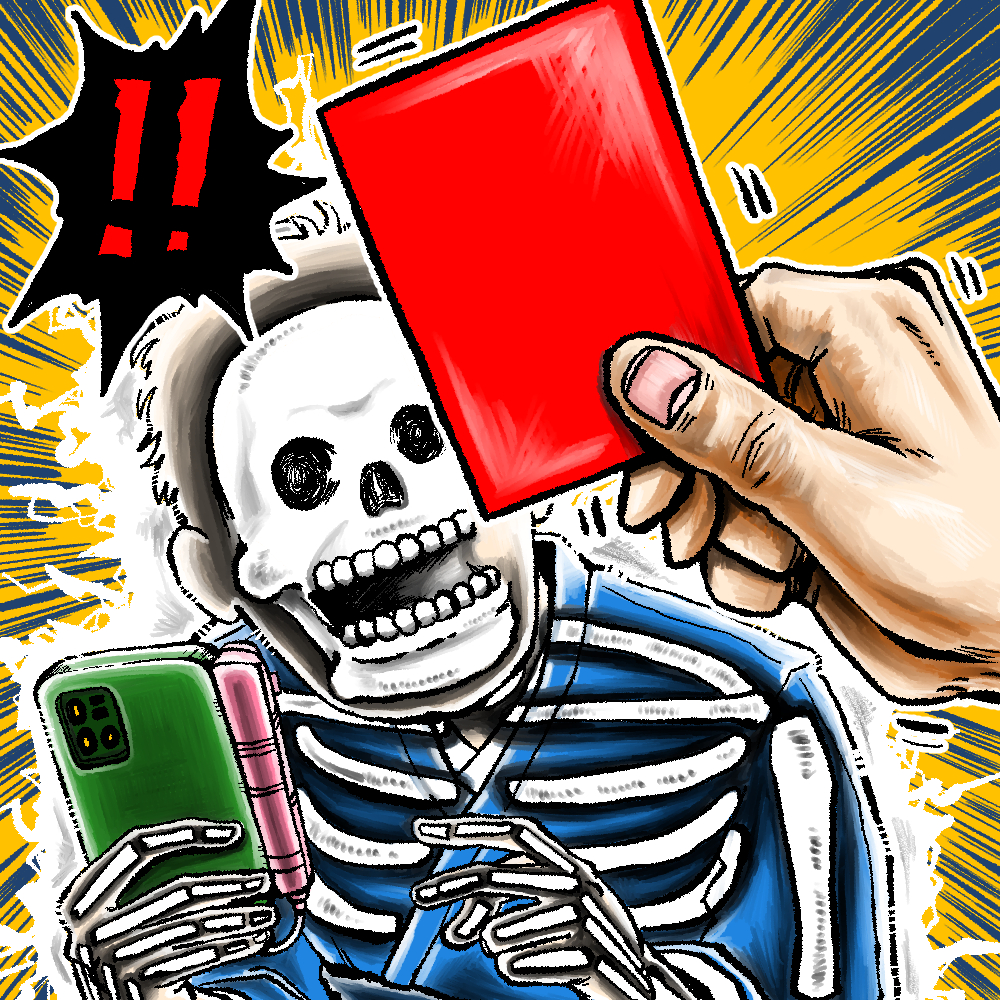
「令和らくご改造計画」
第八話 「酔っ払いにSNSを」
~芸人のSNSは、なぜ自由すぎるのか?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/03/12
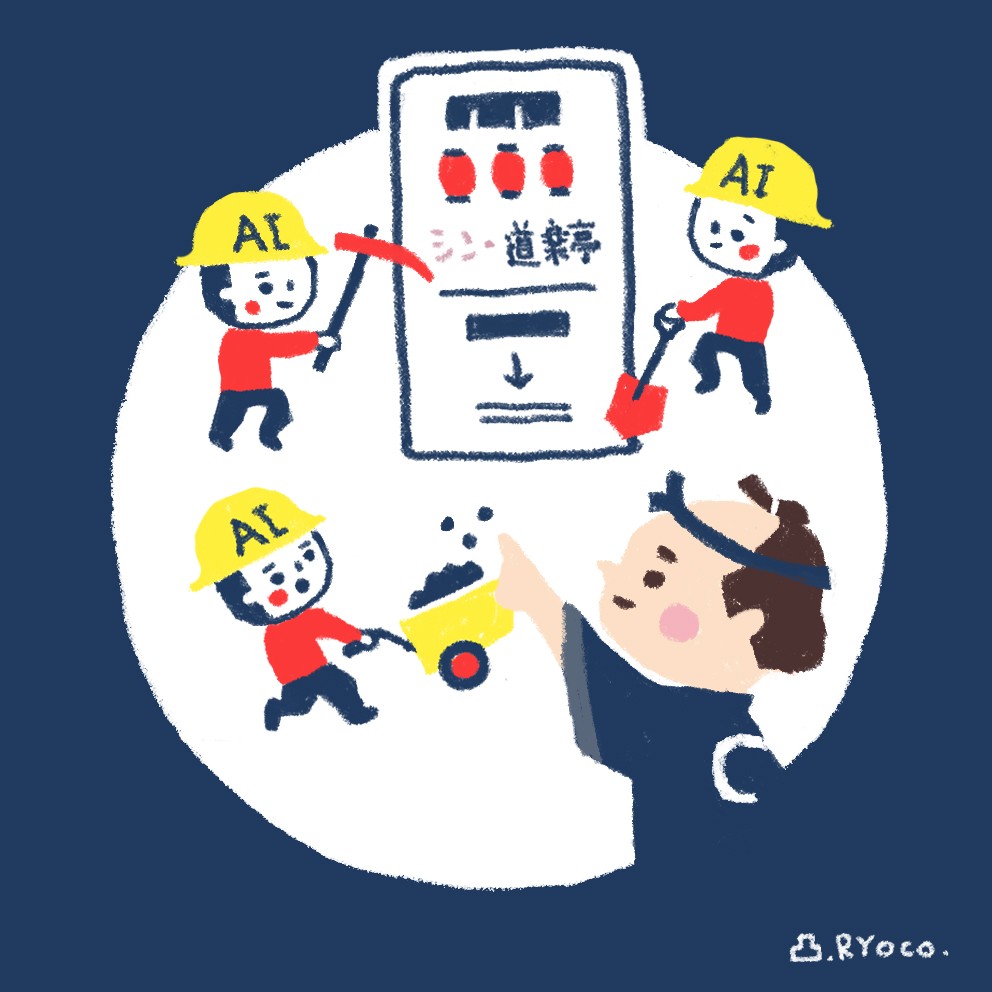
月刊「シン・道楽亭コラム」 第11回
シン・道楽亭Webサイトリニューアル! ほぼほぼAIで作ってみた話
~どんな思いで運営しているのか、どんな場所として受け入れられたいのかをお伝えしたい

シン・道楽亭
2026/03/10

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第27回
古今東西を自在に読む講釈師 松林伯知(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2026/03/12

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第28回
古今東西を自在に読む講釈師 松林伯知(中編①)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2026/03/13
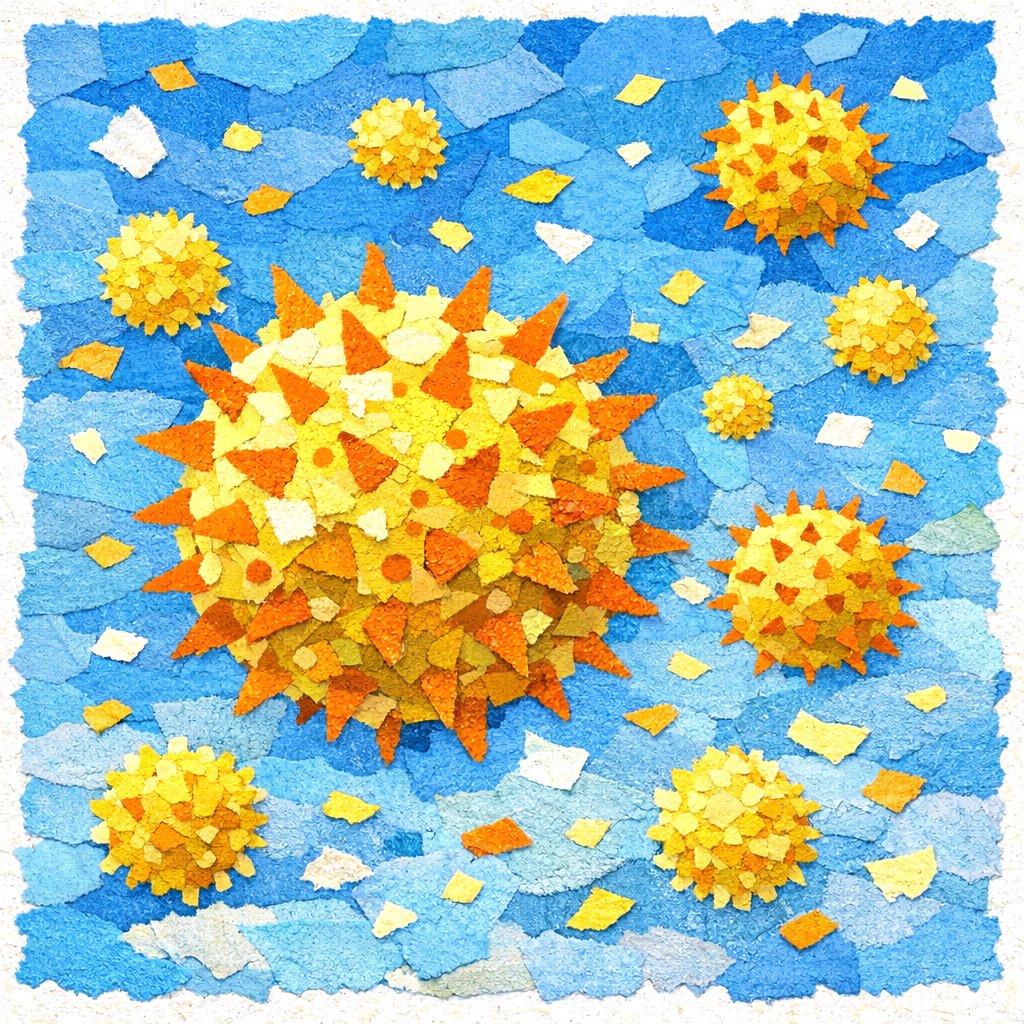
「お恐れながら申し上げます」 第7回
花粉の話
~鼻が教えてくれる季節の便り。春を楽しみましょう!

入船亭 扇太
2026/03/11

「朝橘目線」 第11回
からかさに 隠れて見たる 娘かな
~いつまでこうして一緒に歩けるのか

三遊亭 朝橘
2026/03/08

「二藍の文箱」 第10回
かたばみ日記 ~初主任の十日間
~高座と人生が交差する、濃密で温かい日々の舞台裏

三遊亭 司
2026/03/02
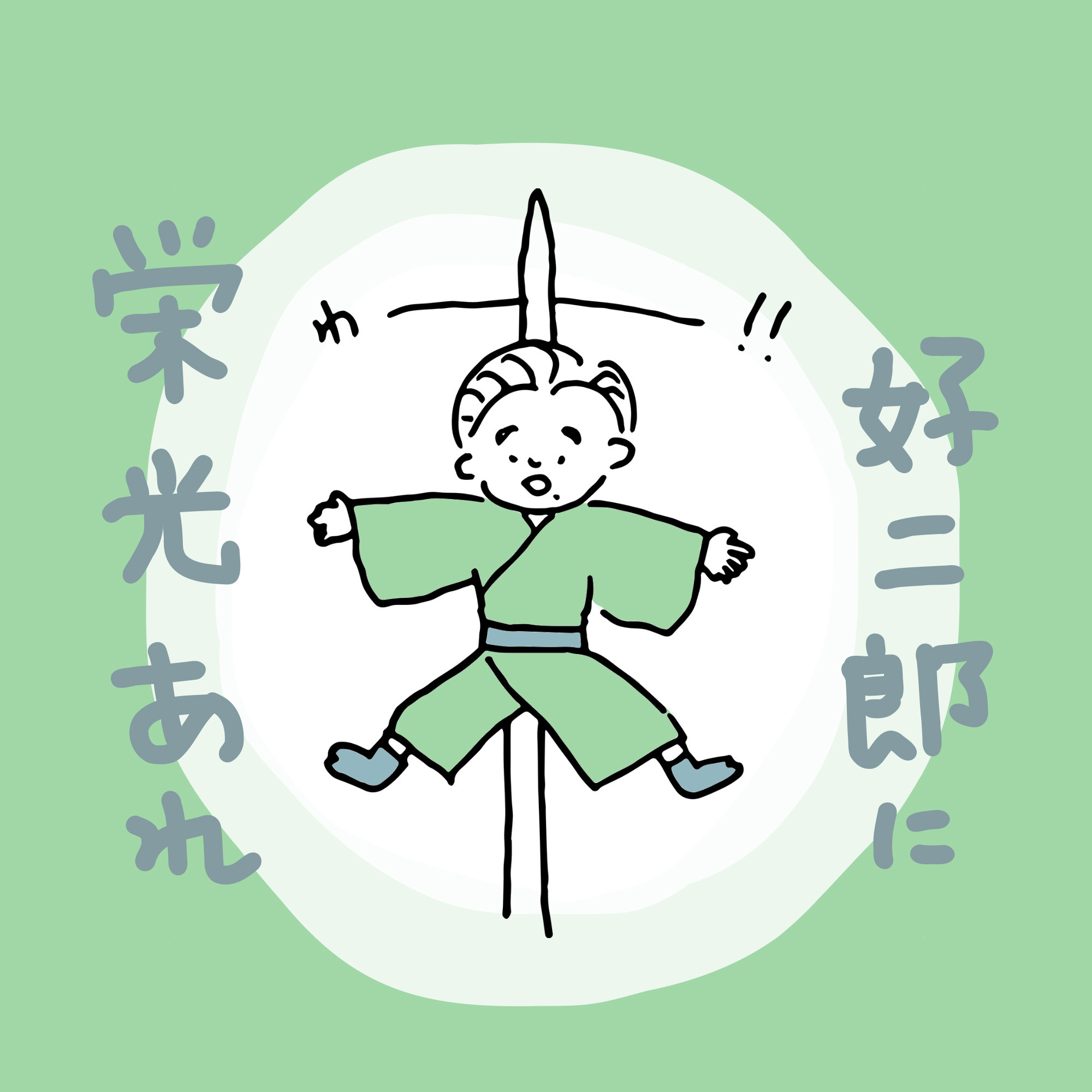
「座布団の片隅から」 第11回
SF
~暗黒SFを観に行きました!!

三遊亭 好二郎
2026/03/07

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第11回
病んでる間に千春の春到来
~体調不良で“声”を失っても、“笑い”は失わない宇宙一の美人浪曲師の事件簿!

東家 千春
2026/03/03

「二藍の文箱」 第10回
かたばみ日記 ~初主任の十日間
~高座と人生が交差する、濃密で温かい日々の舞台裏

三遊亭 司
2026/03/02

月刊「浪曲つれづれ」 第11回
2026年3月のつれづれ(玉川太福の受賞、玉川奈々福の徹底天保水滸伝、『深夜食堂』&『陰陽師』の浪曲化)
~スターの活躍と新しい挑戦が交差する、いまの浪曲界をご紹介

杉江 松恋
2026/03/09

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第11回
病んでる間に千春の春到来
~体調不良で“声”を失っても、“笑い”は失わない宇宙一の美人浪曲師の事件簿!

東家 千春
2026/03/03

「令和らくご改造計画」
第七話 「若手人気落語家殺人事件 【解決編】」
~寛容な落語の世界、非寛容な現実の世界

三遊亭 ごはんつぶ
2026/02/13
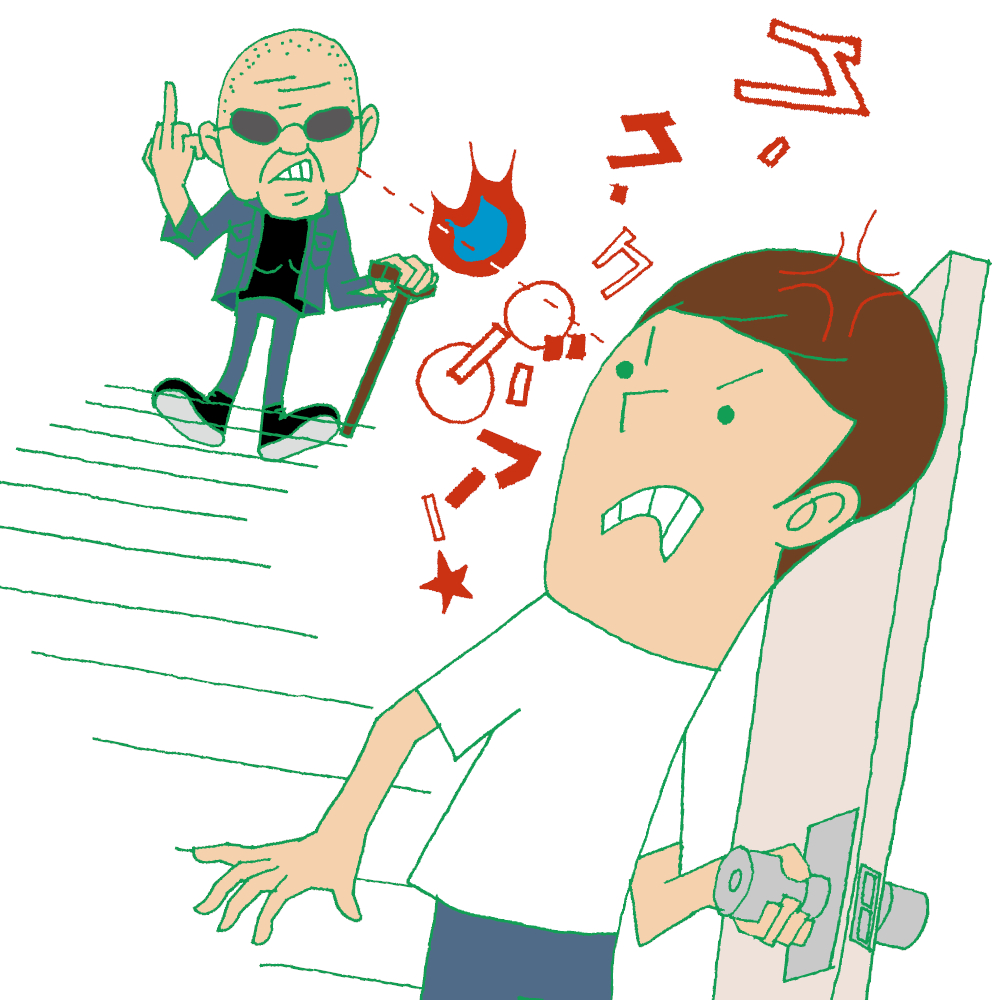
「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回
微笑みながら中指を
~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎
2026/02/25

「二藍の文箱」 第9回
寄席、そちらとこちら
~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司
2026/02/02
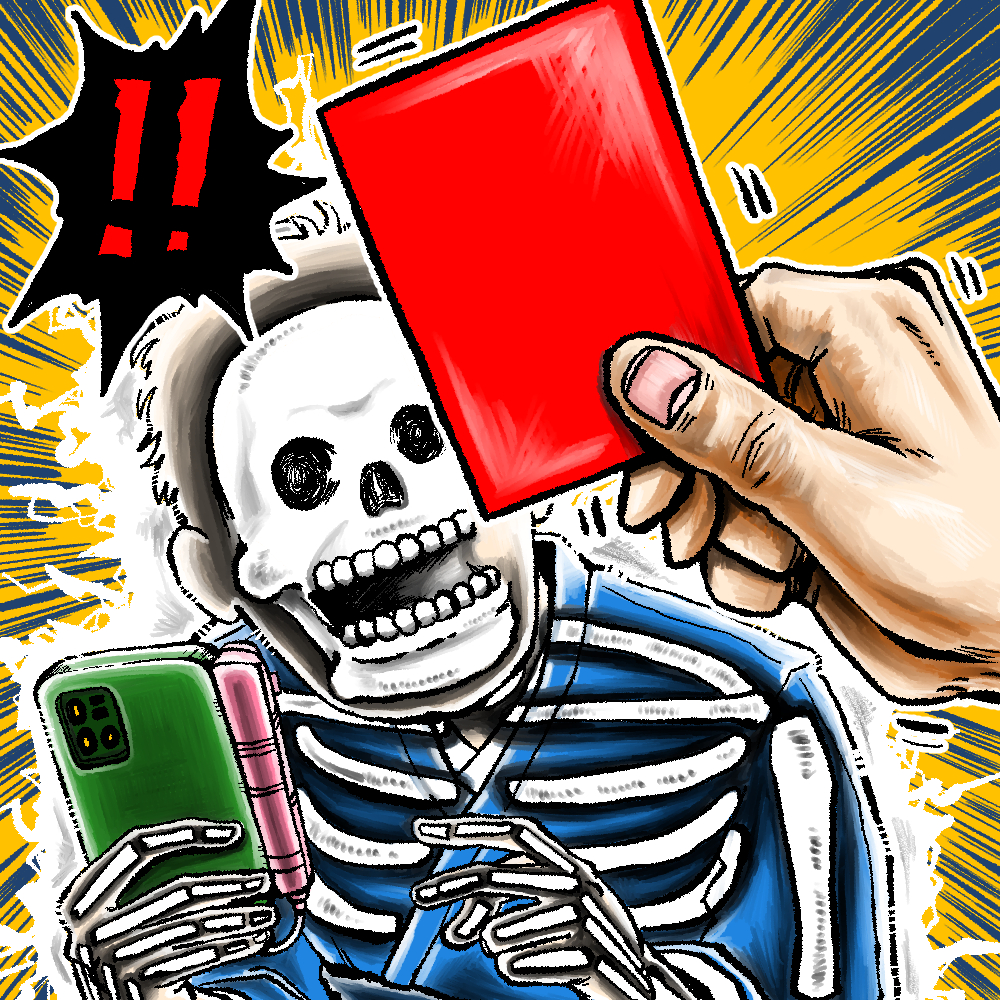
「令和らくご改造計画」
第八話 「酔っ払いにSNSを」
~芸人のSNSは、なぜ自由すぎるのか?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/03/12

「艶やかな不安の光沢」 第1回
謂れなきものたちの飛躍
~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三
2026/02/12
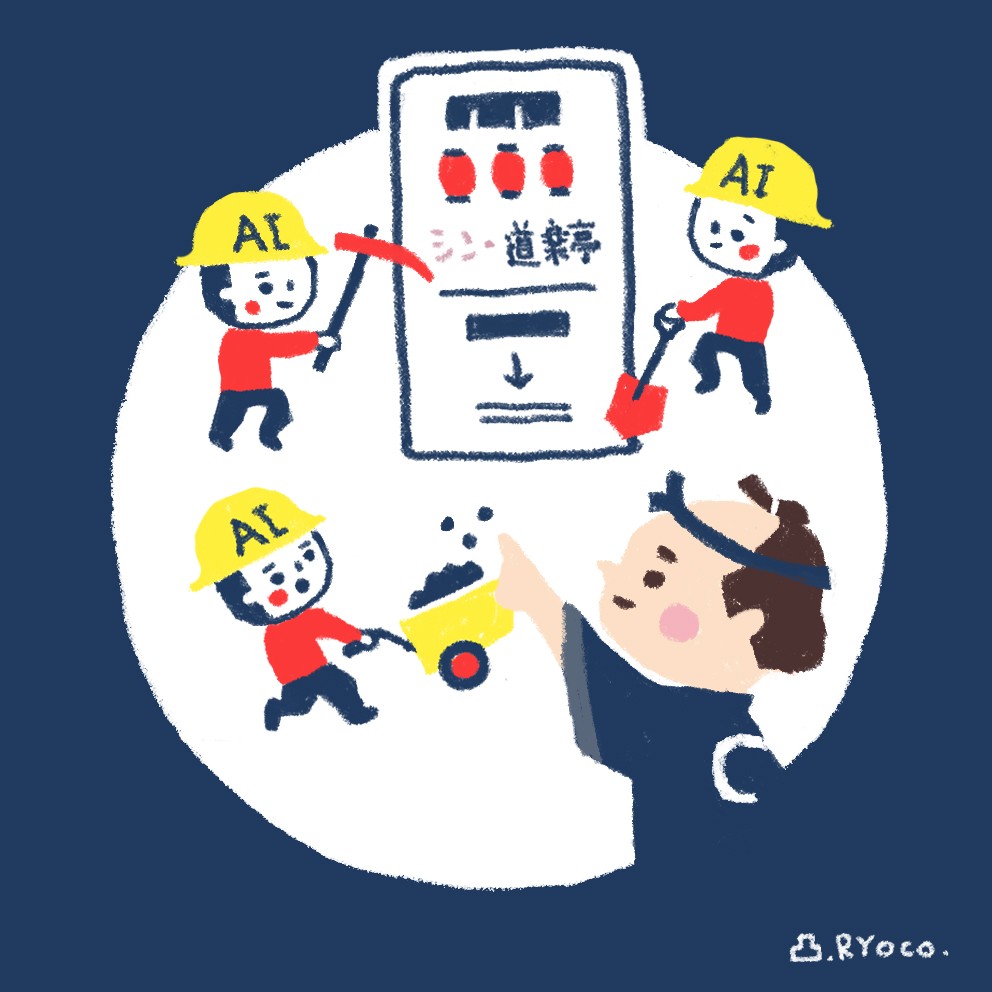
月刊「シン・道楽亭コラム」 第11回
シン・道楽亭Webサイトリニューアル! ほぼほぼAIで作ってみた話
~どんな思いで運営しているのか、どんな場所として受け入れられたいのかをお伝えしたい

シン・道楽亭
2026/03/10
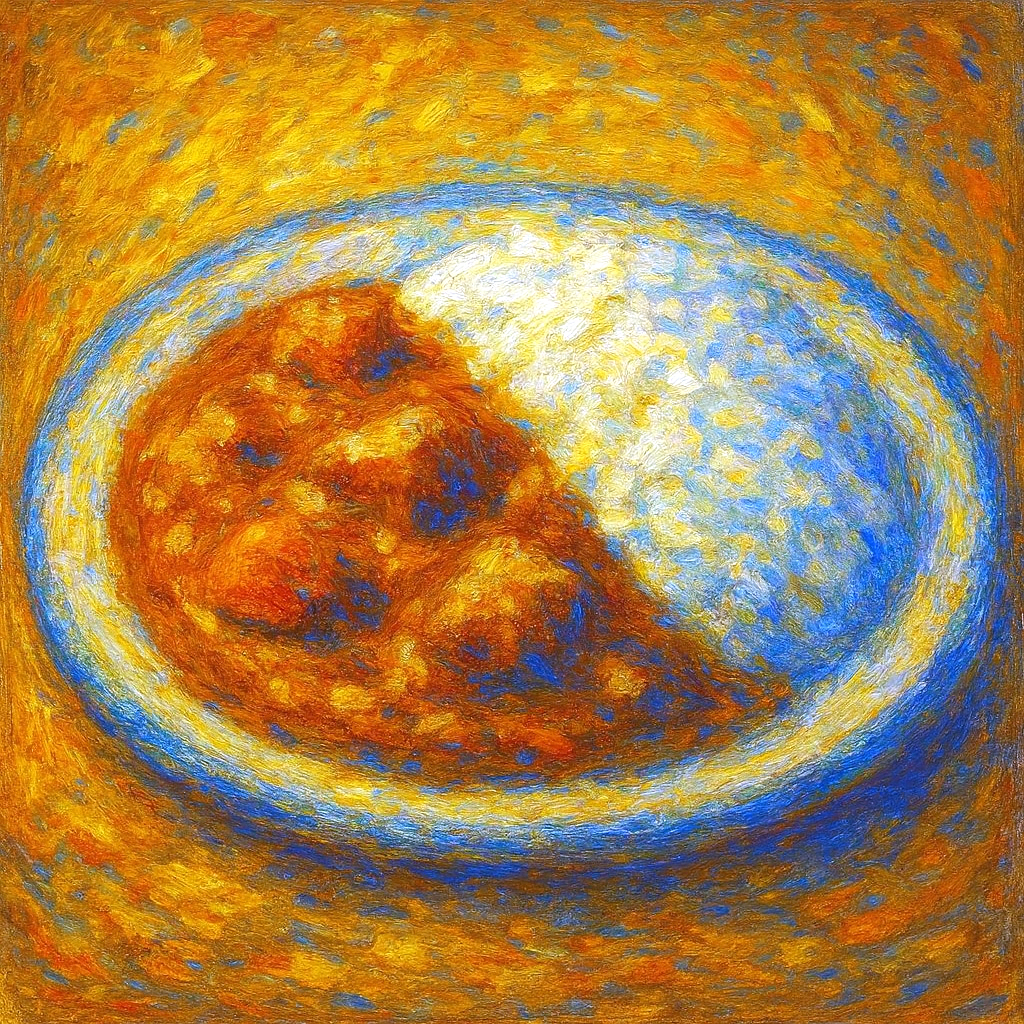
「テーマをもらえば考えます」 第7回
愛と青春のカレー断ち
~うん、世の中よく分からないことだらけだわ……

三遊亭 天どん
2026/02/28

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回
落語家の夢
~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎
2025/11/27

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

「艶やかな不安の光沢」 第1回
謂れなきものたちの飛躍
~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三
2026/02/12
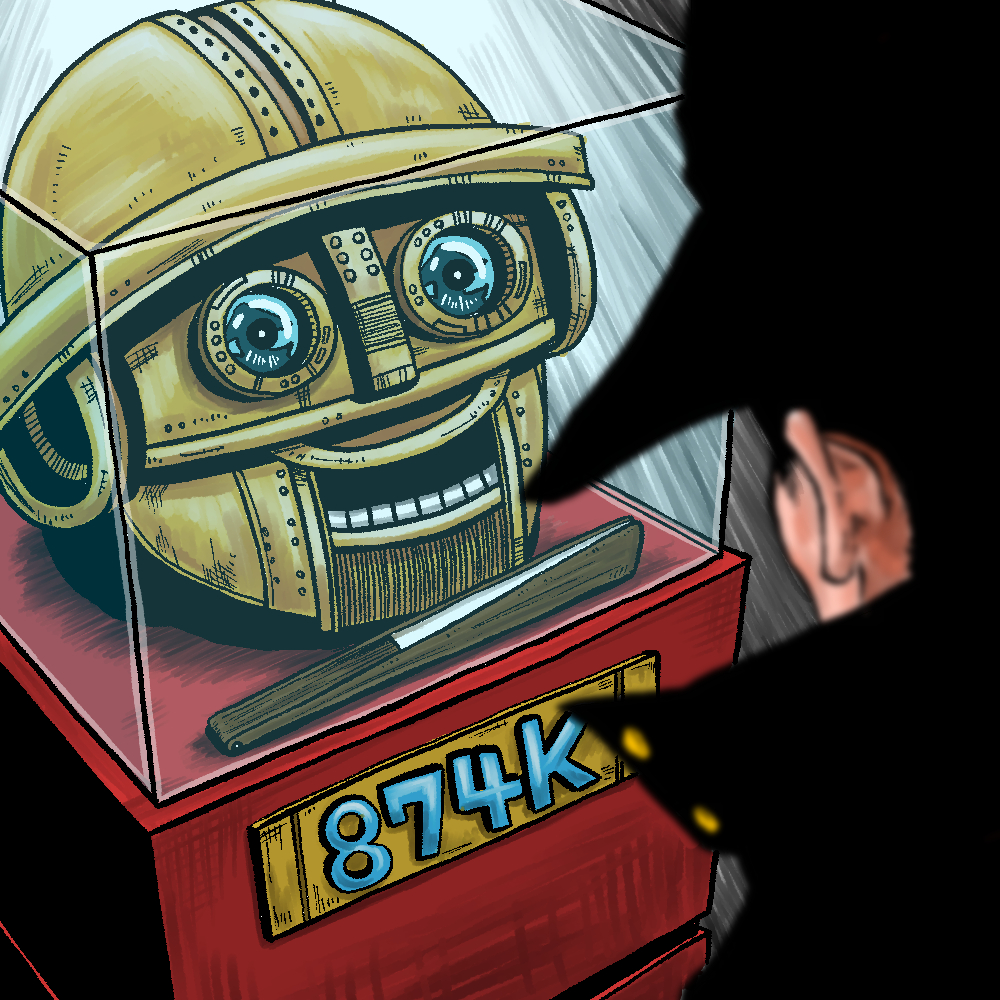
「令和らくご改造計画」
第四話 「初心者よ永遠なれ」
~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/11/12

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回
世間せまないか?
~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎
2026/02/01

シリーズ「思い出の味」 第15回
水茄子とジンジャーエール
~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三
2025/11/25

掲載記事300本記念
〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】
~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部
2026/01/25
編集部のオススメ
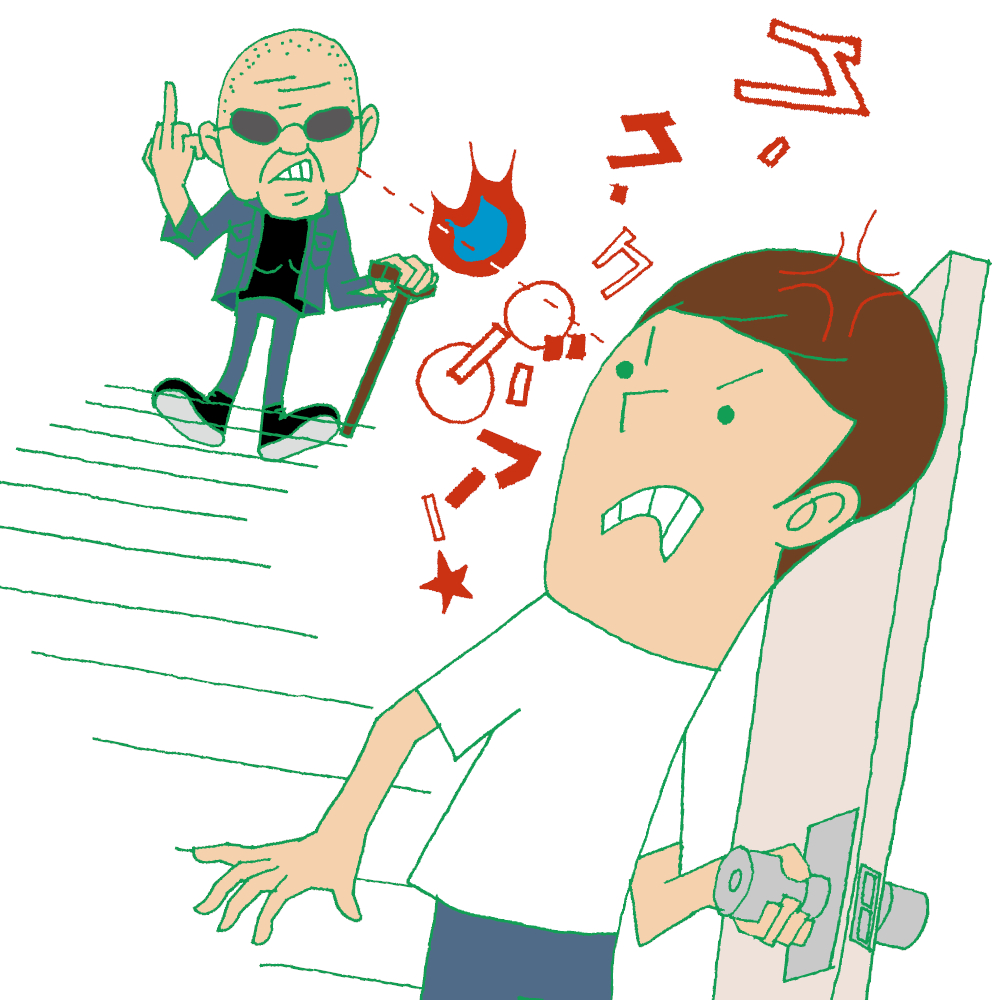
「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回
微笑みながら中指を
~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎
2026/02/25

「令和らくご改造計画」
第七話 「若手人気落語家殺人事件 【解決編】」
~寛容な落語の世界、非寛容な現実の世界

三遊亭 ごはんつぶ
2026/02/13

「艶やかな不安の光沢」 第1回
謂れなきものたちの飛躍
~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三
2026/02/12

「お恐れながら申し上げます」 第6回
早朝寄席のこと
~精一杯やりますので、ご来場をお待ちしております

入船亭 扇太
2026/02/11
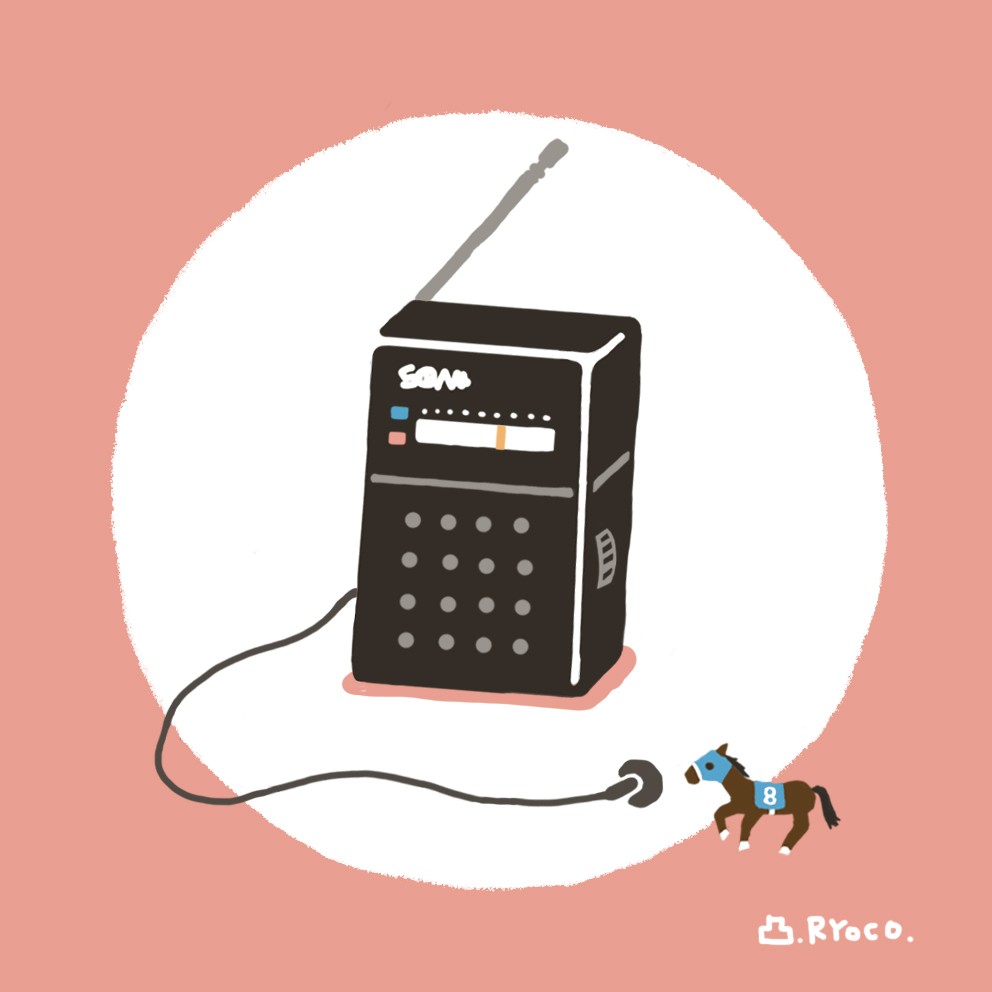
月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回
シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2
~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭
2026/02/10

月刊「浪曲つれづれ」 第10回
2026年2月のつれづれ(沢村豊子を偲ぶ会、玉川奈々福の徹底天保水滸伝、帯広浪曲学校)
~世界に一つだけの宝

杉江 松恋
2026/02/09

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第24回
講談界を駆ける一鶴イズムの継承者 田辺銀冶(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2026/02/03

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第10回
宇宙一の美人も風邪には勝てない
~たっぷりの愛情を込めて演芸界という濃密な世界を描く芸人日記

東家 千春
2026/02/03

「二藍の文箱」 第9回
寄席、そちらとこちら
~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司
2026/02/02

掲載記事300本記念
〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】
~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部
2026/01/25


