“施設長X”の献身
「噺家渡世の余生な噺」 第6回
- 落語

柳家 小志ん
2025/10/14

今回は、ある介護施設を舞台にした、架空の掌編です
決して忘れてはならない、現実。それは、この物語はフィクションであり、架空の“施設長X”の献身を俯瞰的に描いた超短編小説であること……
一、献身の顔をした土地活用
とある介護施設、Z荘。
のどかな地方の田畑に建てられたその施設は、一見すれば「地域福祉に尽くす立派な社会福祉法人」と見えた。だが実態は、地主一族の土地活用である。
施設長Xは、この土地の生まれの者だった。祖父が会長、祖母が理事長、本人は施設長、配偶者は副施設長、相談員は親戚筋。そして「修業」と称して現場に放り込まれたご子息は、現場の監視役にすぎなかった。
法人の土地も建物も、もとは一族の所有。補助金を使って再開発したそれを世間では「地域福祉」と呼ぶ。
アパートなら埋まらない。だが老人ホームなら、入居希望者は尽きない。
Xにとって、介護職員は「お手伝いさんの延長」であり、入所者は「お客様」だった。自分はその頂点に立ち、現場に降りることはない。施設は補助金で建てられ、税金で運営される。これほど割のいい商売は他にない。
二、栄誉は虚像にあり
慢性的な人手不足。
腰を壊し、心をすり減らす職員たち。それでも、Xは会議で決まり文句を繰り返した。
「近頃、施設に対する、いい噂を聞きません」
Xにとって、入所者や外部から「素晴らしい施設長」と称賛されることこそが、何よりの栄誉だった。
現場経験のないXにとって、介護とは食事・入浴・排泄・レクリエーション、それにナースコールの対応程度でしかない。
だから「ナースコールはルームサービスのように押してください」と入所者に奨励し、感謝される。結果として廃用性症候群を生み、寝たきりを増やす要因であることに気づきもしなかった。そして何より、それが業務を圧迫していることに気づく由もない。
職員は「コスト」と考えるXにとって、職員が談笑する姿を見ただけで苛立ちを覚える。税金や保険料で成り立つ現場で、その働く人間もまた同じ納税者であることなど、思いも及ばない。
三、監査という儀式
監査の日は、さらに滑稽だった。
都道府県や区市町村の職員が書類を広げ、帳簿の数字を確認し、「問題なし」と頷く。現場の「疲弊」という数字に表れない現象は、目に入らない。
年間に10人が退職し、8人が入職している。数字上では特段問題はない。しかし、そもそも全職員を合わせても30人程度の職場で、年間10人が辞めるということは――組織としてどこかに闇があるに違いない。
そこへ2人の欠員も加わる。元々人手不足の現場で、2人の欠員は致命的である。だが、そんな事実は監査では問題にならない。
監査員の多くは、異動でたまたま回ってきただけの人間だ。既に異動の決まっている前任者から教わりながら帳簿を追い、その数年後には別の部署に去る。
だから最後には、施設長Xに向かって「今後とも地域福祉にご尽力を」と頭を下げ、帰っていくのだ。
いま読まれています!

「くだらな観音菩薩」 第9回
伎芸天
~髪の生え際から、呼ばれて飛び出た仏様

林家 きく麿
2026/01/16

「講談最前線」 第14回
2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2026/01/15

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「噺家渡世の余生な噺」 第9回
今年も、自分を悟る一年に
~噺家として育てられてきた時間のありがたさ

柳家 小志ん
2026/01/14

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第18回
優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/11/29

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第20回
優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(後編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/11/30

シリーズ「思い出の味」 第11回
食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶
~焼肉は落語

桂 笑金
2025/08/17
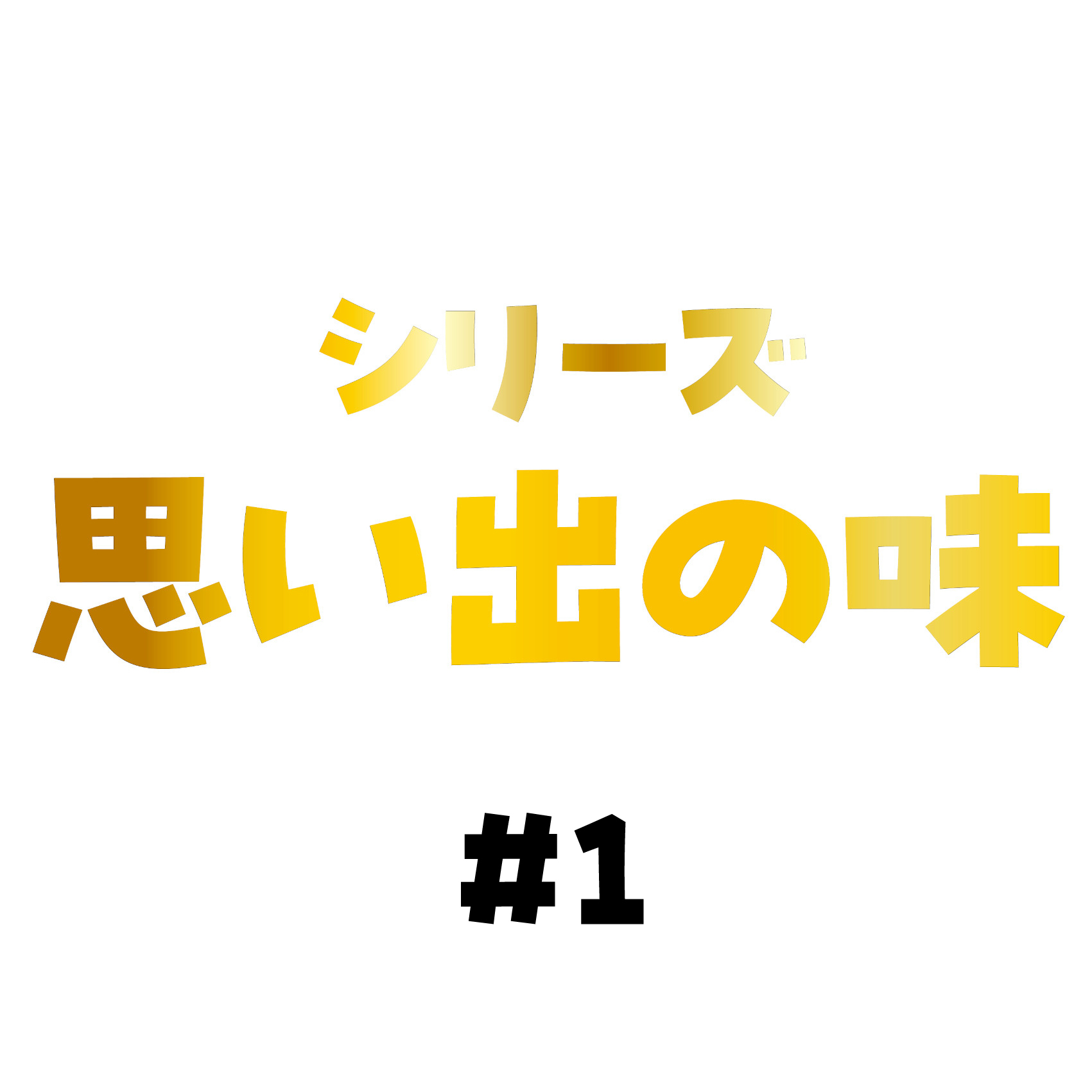
シリーズ「思い出の味」 第1回
21900のいただきます
~師匠との食卓

三遊亭 司
2025/05/13

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回
昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!
~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭
2026/01/10

「お恐れながら申し上げます」 第5回
新年のご挨拶
~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太
2026/01/11

「講談最前線」 第14回
2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2026/01/15

「くだらな観音菩薩」 第9回
伎芸天
~髪の生え際から、呼ばれて飛び出た仏様

林家 きく麿
2026/01/16

「噺家渡世の余生な噺」 第9回
今年も、自分を悟る一年に
~噺家として育てられてきた時間のありがたさ

柳家 小志ん
2026/01/14

「二藍の文箱」 第8回
麹町の雑煮、目白のおせち
~噺家の正月風景

三遊亭 司
2026/01/02

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

月刊「浪曲つれづれ」 第9回
2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)
~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋
2026/01/09

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/29

「二藍の文箱」 第8回
麹町の雑煮、目白のおせち
~噺家の正月風景

三遊亭 司
2026/01/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回
昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!
~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭
2026/01/10

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第22回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(中編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第23回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(後編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/31

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回
〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)
~「見えない序列」の正体

杉江 松恋
2025/12/24

「浪曲案内 連続読み」 第8回
浪曲ほど素敵な商売はない
~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎
2025/12/22

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回
落語家の夢
~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎
2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第15回
水茄子とジンジャーエール
~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三
2025/11/25

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「令和らくご改造計画」
第四話 「初心者よ永遠なれ」
~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回
上方落語大会議「なんぼでなんぼ」
~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎
2025/10/24

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回
シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト
~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭
2025/11/13

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回
ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋
~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春
2025/11/03
編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回
浪曲ほど素敵な商売はない
~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎
2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回
弥勒菩薩(半跏思惟像)
~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿
2025/12/16

「講談最前線」 第12回
2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2025/12/15

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回
にらみ返し、大工調べ、短命
~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平
2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回
今日は宇宙一の美が誕生した日
~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春
2025/12/03


