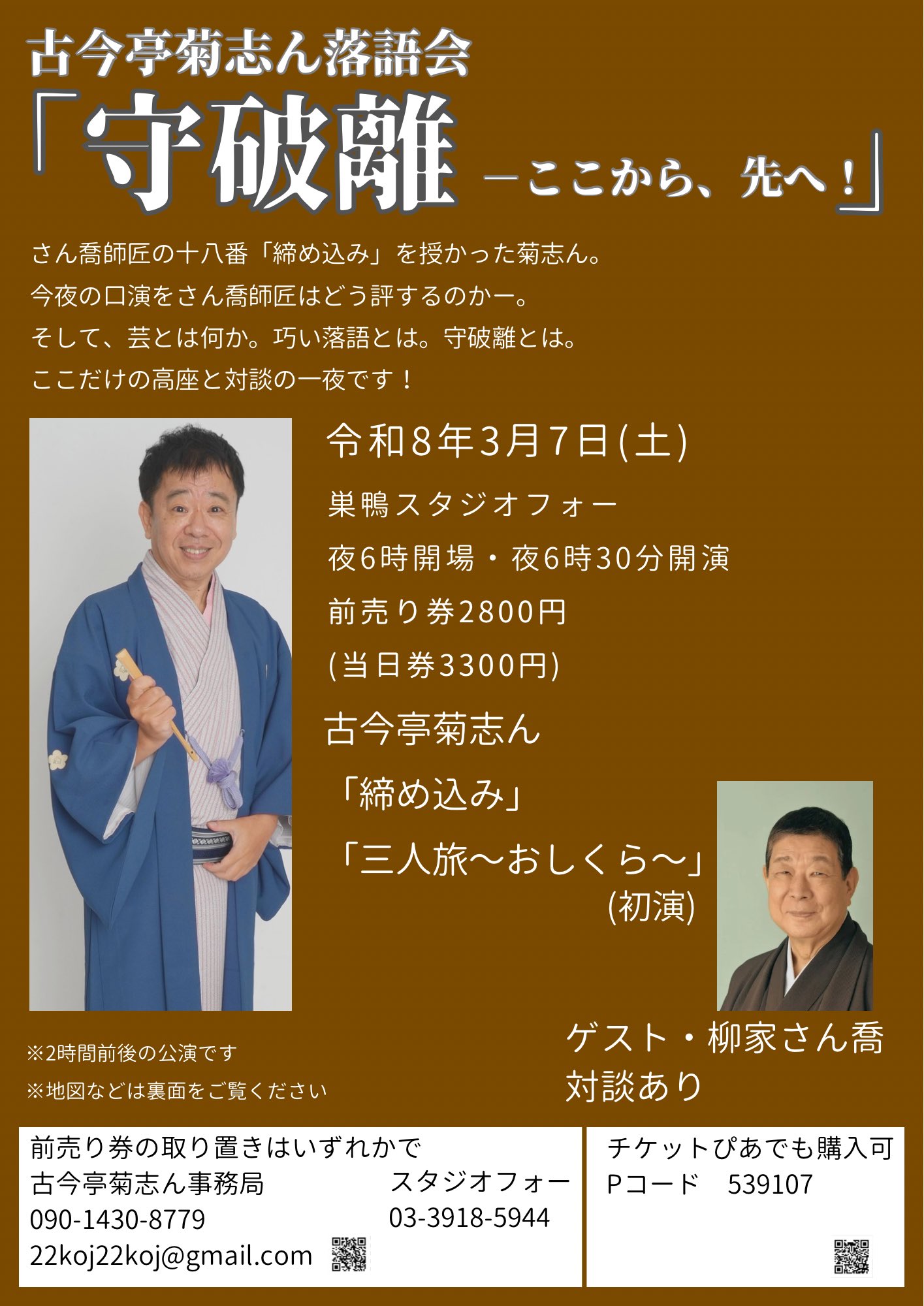2025年10月の最前線【後編】 (聴講記:日本講談協会定席、講談のオススメ入門書②)
「講談最前線」 第10回
- 講談
- Books

神田昌味 近影(日本講談協会HPより)
講談はいつも面白い。そして講談はいつも新しい――。講談の魅力って? 講談ってどこで聴けるの? どんな講釈師がどんな講談を読んでいるの?と、それにお応えするべく、注目したい講釈師や会の情報、そして聴講記……と、講談界の「今」を追い掛けていきます。(2025年10月の前編/後編のうちの後編)
常に人気の高い講談定席
日本講談協会(神田紅・会長)の定席に久々に足を運んでみた。ここ数年は神田松鯉・伯山の人気もあって、前売りの段階で満員ということもあり、敬遠していたということもある。この日は、当日券が出るということと、トリを務める神田昌味の『二宮金次郎 ~宇都宮物語』を聴いてみたくもあり、出掛けてみた。
当日の番組は、次の通りである(2025年9月20日、お江戸上野広小路亭)。
神田松樹 「三方ヶ原軍記~五色備え」
神田若之丞 「越の海勇蔵」
神田紅佳 「細川ガラシャ」
松林伯知 「桜田門外の変外伝~鯉淵要人」
神田松鯉 「浅妻船」
(中入り)
神田鯉風 「赤穂義士銘々伝~不破数右衛門」
神田昌味 「二宮金次郎~宇都宮物語」
結論から記せば、大変に面白い番組であった。語弊があるかも知れないが、山陽一門は演目の出どころが一緒であったりするので、異なる会であっても演者こそ違え、番組に並ぶ演目が一緒であることもある。
この日は、細川ガラシャ、鯉淵要人(こいぶちかなめ)、不破数右衛門(ふわかずえもん)、二宮金次郎と、他では聴くことができない演目が並び、松鯉の英一蝶(はなぶさいっちょう)を入れれば、人物特集であったとも言える。そして個性のある演者がそれぞれの主人公がどんな人生を送り、そのどんな部分にスポットを当てるかが聴きどころであった。
人物伝の魅力全開
神田紅佳は、先日公開した前編のインタビューでも話しているように、出身の九州にまつわる人物から「細川ガラシャ」を読んだ。
ガラシャという名の意味、女が政治の場でいいように利用されていた時代にキリスト教を信仰していく過程。そして何故、本能寺の変以降に彼女の運命が変わっていくのかを丁寧に読み、軍(いくさ)に翻弄されるも、己の道を生き抜いた女性の姿を、時に強い言葉で、心情に迫る時には柔らかな口調で描き出した。
山陽一門にあって唯一「松林」を冠する、松林伯知(しょうりんはくち)は、お得意の幕末の歴史から、水戸出身の伯知によるライフワークの一つとも言える、同郷の人物伝のうち、幕末の尊攘運動家であり、桜田烈士(桜田門外の変に加わった浪士)の一人である鯉淵要人に迫った。
歴女だけあって、北海道や京都の歴史舞台を「伯知さんぽ」してきた際に、明治期の碑や説明板が残っていないことに不満を示しつつ、水戸様は乗る舟に権威を保っていた(今風に言えば、イキっていた)件と、それが今の茨城県人の運転に繋がるのではと、講談に必要とも言える、自身の見解を取り入れながら、その舟から起こる一つの事件を楽しく聴かせた。
舟つながりで言えば、中入り前の松鯉は多賀朝湖(たがちょうこ、のちの英一蝶)が描いた見事な「春山夜桜」の絵に、書家の佐々木文山(ささきぶんざん)がとんでもない一筆を入れることからひと騒動が起こる「屏風の蘇生」。続いて多賀朝湖の不運な人生を解き明かす「浅妻船」までを読んだ。なお、「あさづまぶね」は「朝妻船」とすることもあるが、ここでは『浅妻船』とした。