“施設長X”の献身
「噺家渡世の余生な噺」 第6回
- 落語

柳家 小志ん
2025/10/14
五、制度の穴と人の心
制度の穴は、Xにとってまさに天の恵みだった。
補助金は潤沢に降り、人材不足は行政が「対策」を考えてくれる。実習生を受け入れれば感謝され、そのまま採用すれば、今度は求職者の「救世主」として称えられる。
本来は、人手不足の解消のために採用したはずなのだが、その功績はいつの間にか、Xの虚栄心を満たすための飾りに変わっていった。
Xは搾取の構造に無自覚ではなかった。むしろ、仕組みを理解した上で、巧みに温存していた。
だが、その結果はあまりにも明白だった。
人の老いと暮らしを支えたいと願い、専門性を磨いて入職した職員たちは、現場で待ち受けていた現実に、次第に心をすり減らしていった。
入所者という名の「Xのお客様」への過剰な迎合、Xに評価されるための献身、そして「お手伝いさんの延長」としか見なされない扱い。
誇りを持っていた者ほど、傷は深く、去り際は静かだった。疲れ果てた介護職は、その地域で再び福祉職に就こうとは思わない。近隣施設の施設長は顔見知り同士で、地域内での転職には抵抗がある。結局、職員は地域を離れるか、業界を去るしかない。
X自らは高級車で出勤し、職員は軽自動車で去っていく。その格差を当然のように受け入れ、笑顔で見送る。それでもXにとっては、その静けさこそが支配の証なのだ。
しかしこれは、Xにとっても業界にとっても不都合ではない。むしろ好都合である。入所者数と介護度で収入が決まる介護施設において、収益の天井はあらかじめ定められている。
その限られた枠の中で、勤続年数の長い職員が増えることは「コスト増」でしかない。
だから、適度に経験者が退職し、若手が入れ替わってくれる方が、計算上も、運営上も効率が良い。しかも、長く勤めた職員が他地域や業界に去ってくれれば、内部の実情が外に漏れることもない。
Xにとっては、これほど都合のいい循環はなかった。
それでも外から見れば、Xは地域に尽くす「献身的な一族」として称えられる。老いて会長となれば、息子が施設長に座る。制度は変わらず、構造もまた壊れない。
――“献身”という名を借りた虚栄と権力の継承。それは、介護という名の聖域に、静かに、そして確かに根を張り続けるのだ。
いま読まれています!

「くだらな観音菩薩」 第9回
伎芸天
~髪の生え際から、呼ばれて飛び出た仏様

林家 きく麿
2026/01/16

「講談最前線」 第14回
2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2026/01/15

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「噺家渡世の余生な噺」 第9回
今年も、自分を悟る一年に
~噺家として育てられてきた時間のありがたさ

柳家 小志ん
2026/01/14

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第18回
優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/11/29

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第20回
優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(後編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/11/30

シリーズ「思い出の味」 第11回
食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶
~焼肉は落語

桂 笑金
2025/08/17
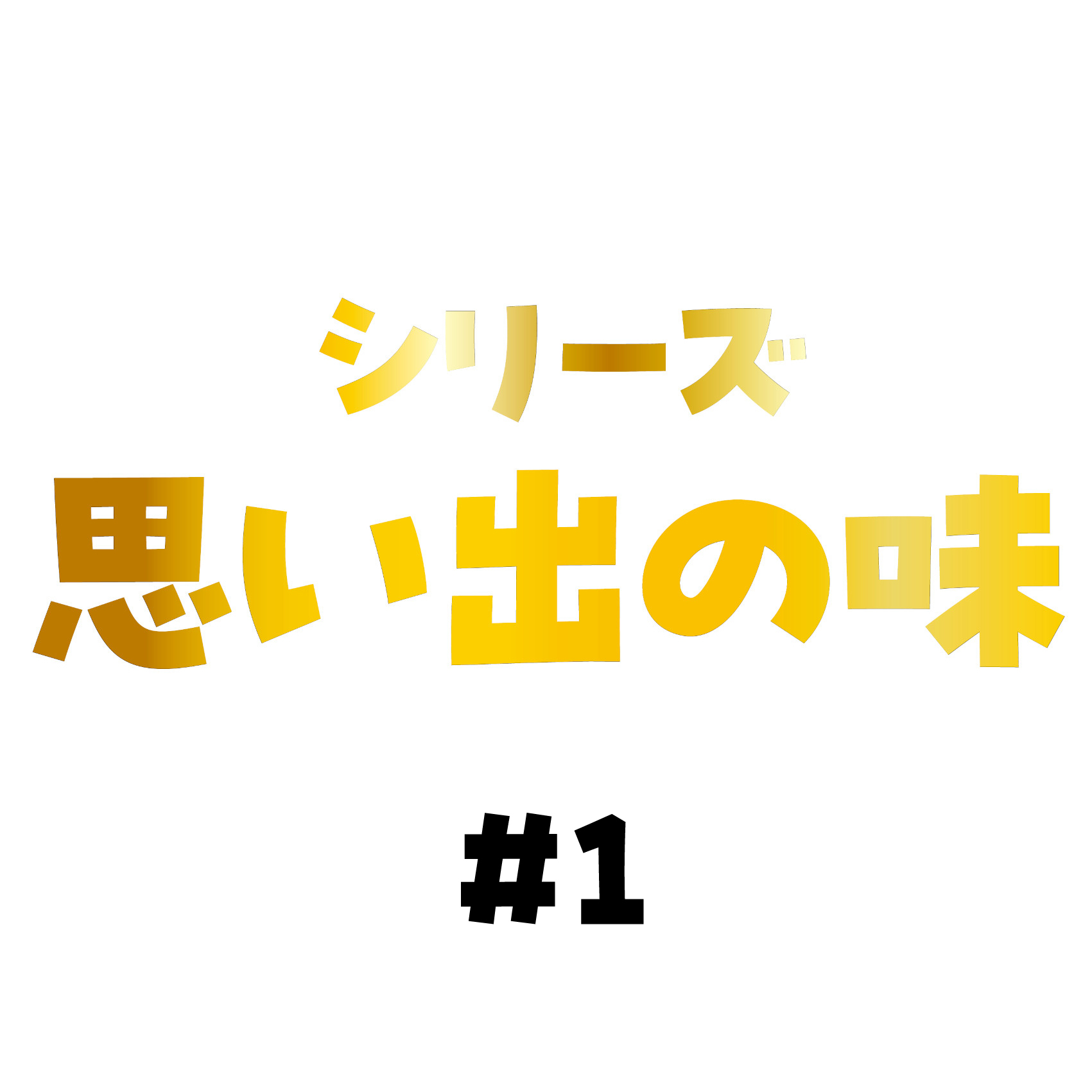
シリーズ「思い出の味」 第1回
21900のいただきます
~師匠との食卓

三遊亭 司
2025/05/13

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回
昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!
~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭
2026/01/10

「お恐れながら申し上げます」 第5回
新年のご挨拶
~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太
2026/01/11

「講談最前線」 第14回
2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2026/01/15

「くだらな観音菩薩」 第9回
伎芸天
~髪の生え際から、呼ばれて飛び出た仏様

林家 きく麿
2026/01/16

「噺家渡世の余生な噺」 第9回
今年も、自分を悟る一年に
~噺家として育てられてきた時間のありがたさ

柳家 小志ん
2026/01/14

「二藍の文箱」 第8回
麹町の雑煮、目白のおせち
~噺家の正月風景

三遊亭 司
2026/01/02

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

月刊「浪曲つれづれ」 第9回
2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)
~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋
2026/01/09

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/29

「二藍の文箱」 第8回
麹町の雑煮、目白のおせち
~噺家の正月風景

三遊亭 司
2026/01/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回
昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!
~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭
2026/01/10

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第22回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(中編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第23回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(後編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/31

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回
〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)
~「見えない序列」の正体

杉江 松恋
2025/12/24

「浪曲案内 連続読み」 第8回
浪曲ほど素敵な商売はない
~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎
2025/12/22

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回
落語家の夢
~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎
2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第19回
雪のココア
~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび
2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第15回
水茄子とジンジャーエール
~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三
2025/11/25

「令和らくご改造計画」
第四話 「初心者よ永遠なれ」
~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/11/12

「令和らくご改造計画」
第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」
~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ
2026/01/12

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回
上方落語大会議「なんぼでなんぼ」
~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎
2025/10/24

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回
シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト
~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭
2025/11/13

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回
ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋
~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春
2025/11/03
編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回
運と皆様のおかげです
~人間は弱い生き物です

桂 三四郎
2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回
日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)
~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁
2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回
浪曲ほど素敵な商売はない
~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎
2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回
弥勒菩薩(半跏思惟像)
~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿
2025/12/16

「講談最前線」 第12回
2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)
~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁
2025/12/15

「令和らくご改造計画」
第五話 「ヨセジャック事件」
~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ
2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回
にらみ返し、大工調べ、短命
~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平
2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回
今日は宇宙一の美が誕生した日
~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春
2025/12/03


